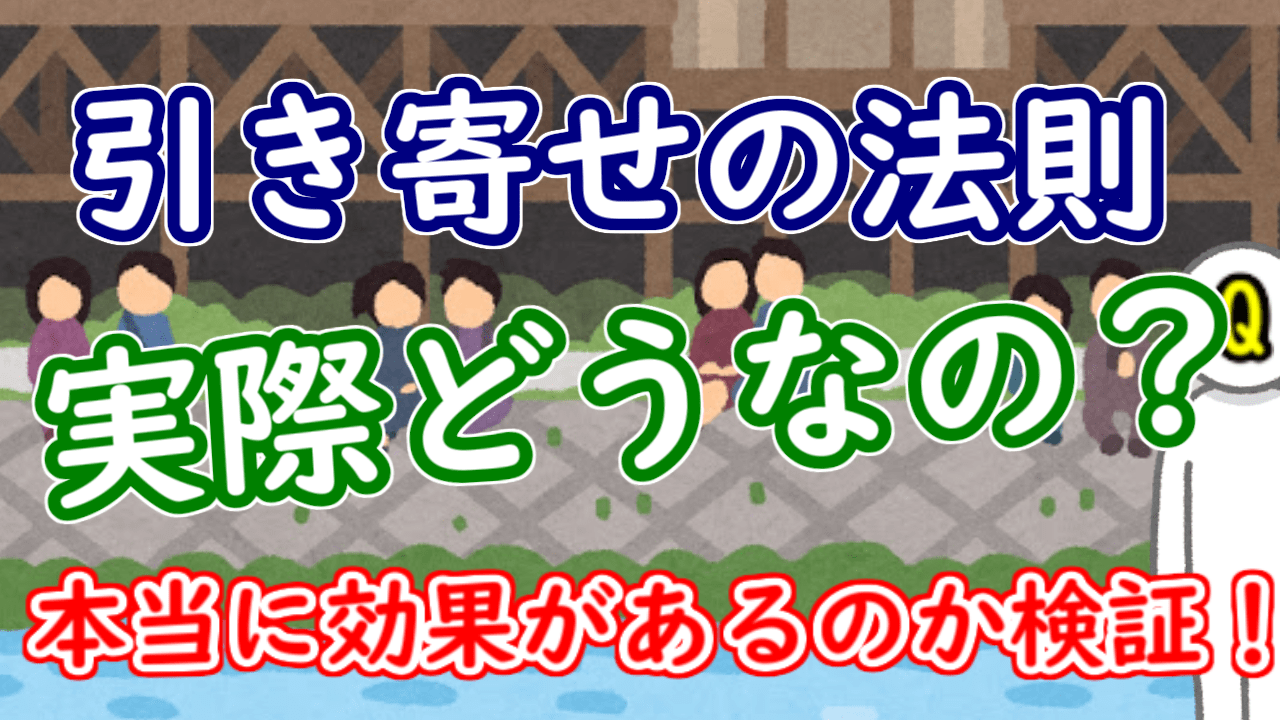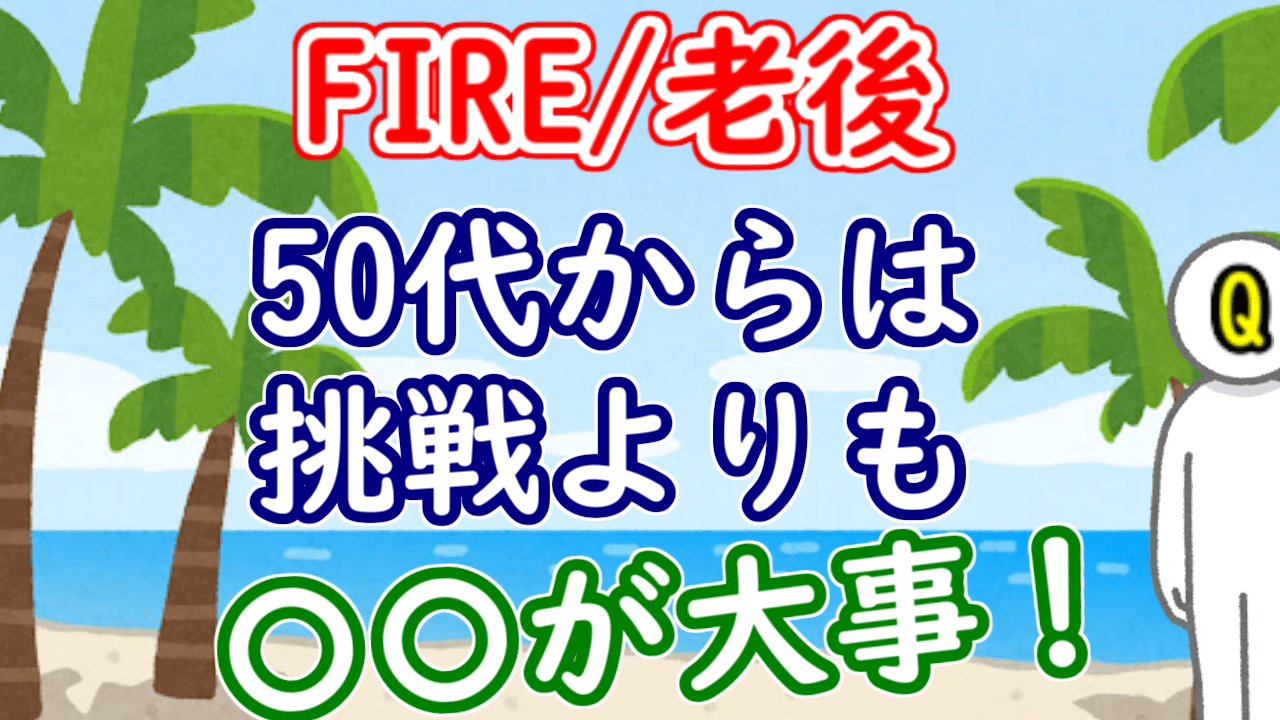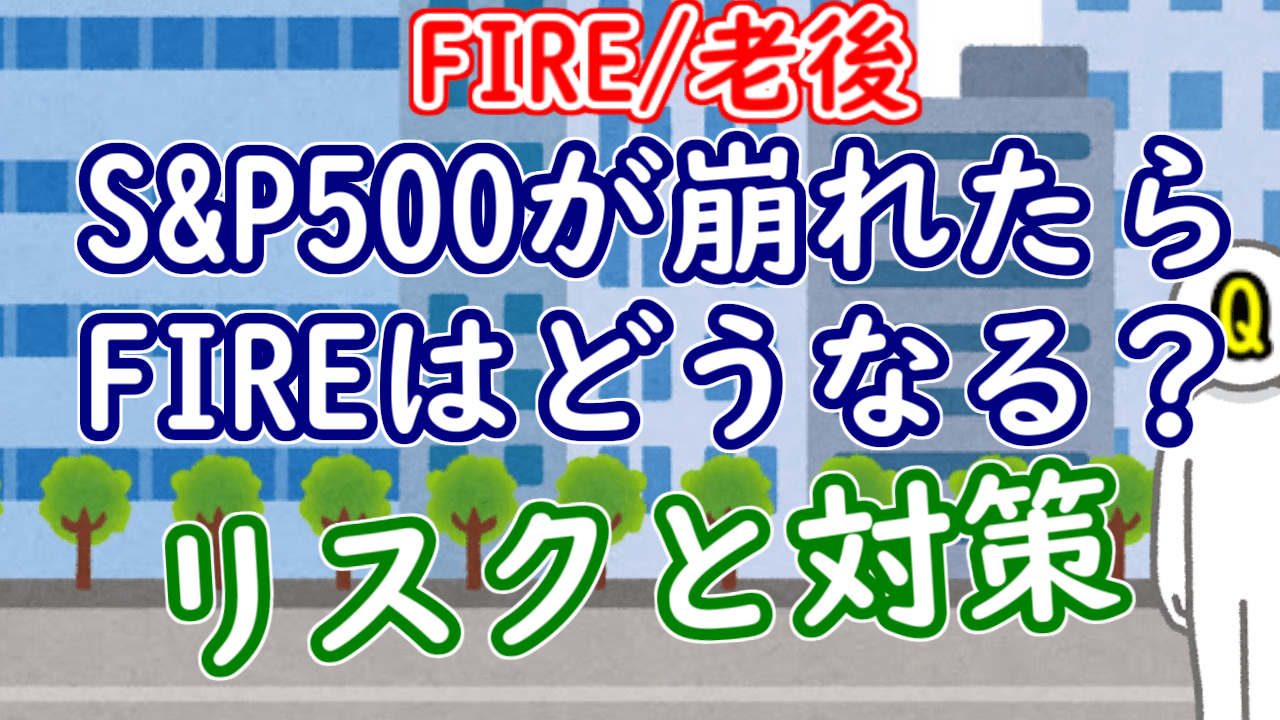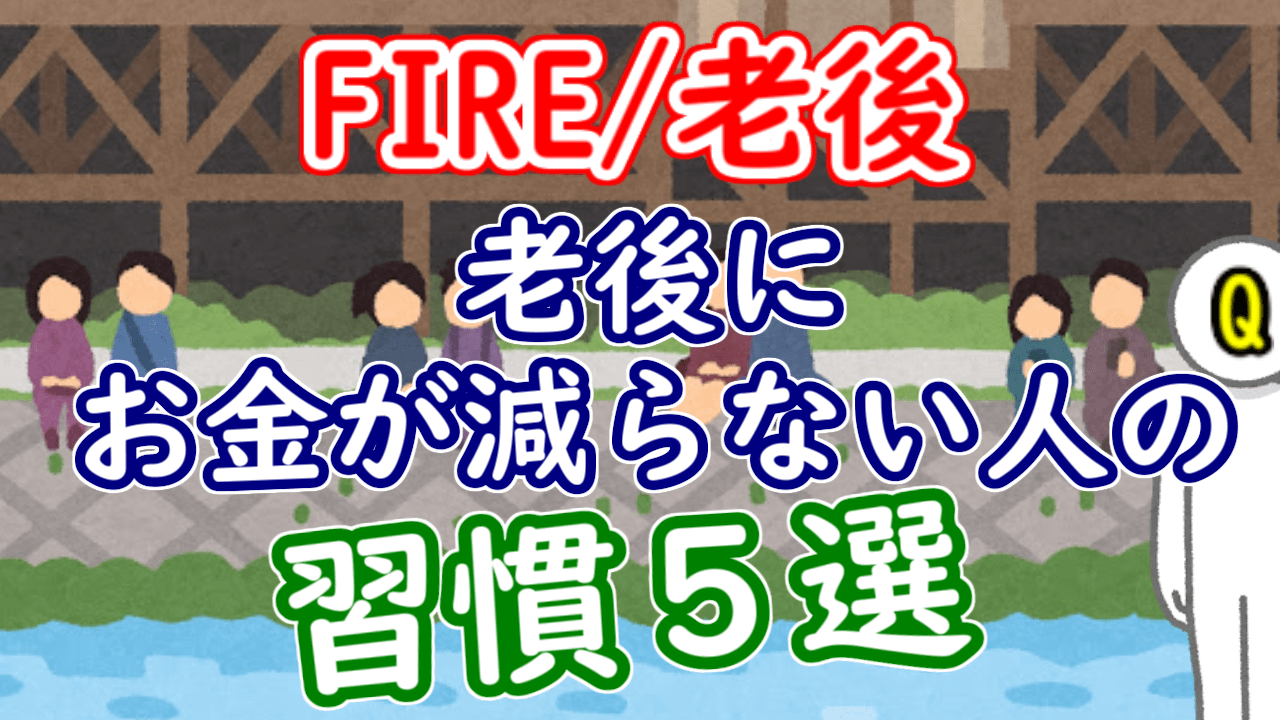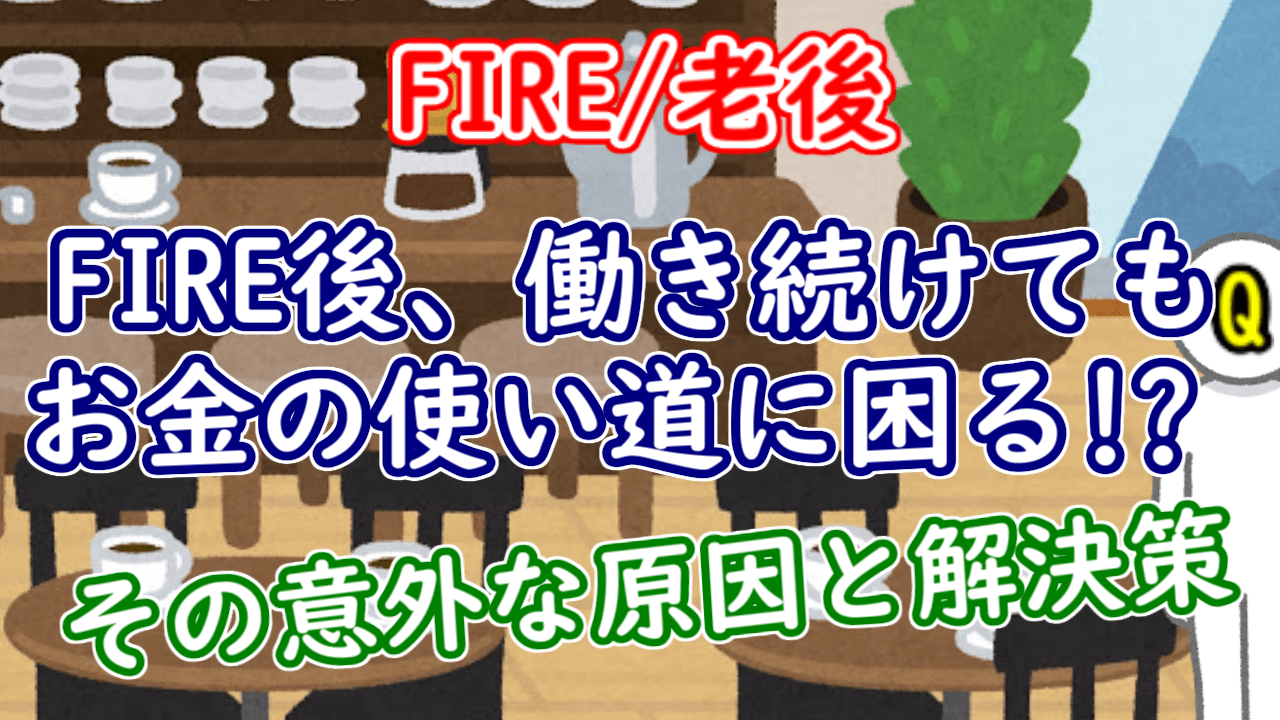
新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は、FIRE後に稼いだお金の使い道についてです。
本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから。
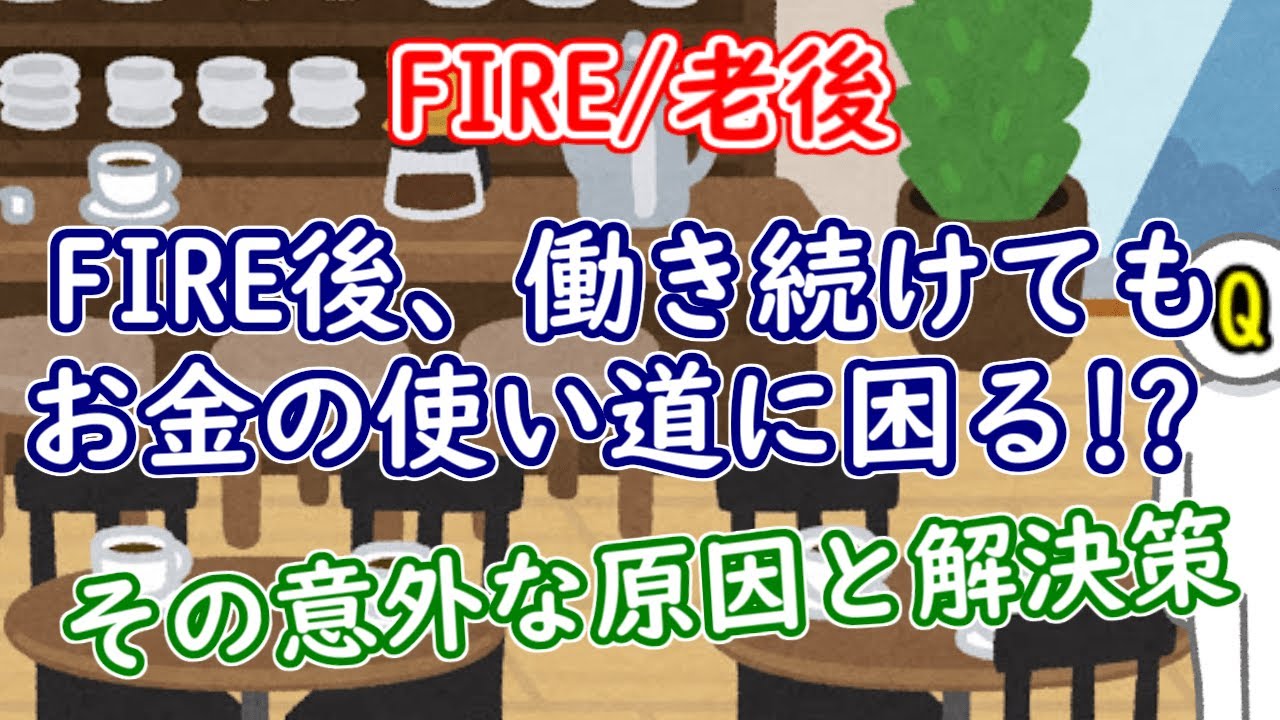
欲しい物のためにFIRE後に働く
こんなご質問をいただきました。
「FIRE後の労働とお金の使い方について質問があります。
私はまったく働かないというのは世の中との繋がりも無くなってしまうことから、自分の性格では無理そうなので、バリスタFIREという形でFIREしました。いろいろなFIRE情報を集めていると、多くの人が最初は遊んでいるだけで楽しかったけど、だんだん飽きてきてしまって鬱になるというケースが多いようです。
とくに最近読んだ本ですと、働くということは世の中のために仕事をすることなので、働かないということは、誰からも必要とされずに、自分がこの世に存在しない空気のような存在になってしまうということです。この状態を受け入れられる人はほとんどいませんので、やはりFIRE後も働いた方が良いとは思います。
私は現在、前の仕事のつてで週三日ほどの仕事をしています。給料もそこそこ良いのですが、実の所、お金を稼いでも別に使い道がありません。単に仕事をして、お金を貯めているという状態になっています。
寄付については、NPO団体が信用できないということもあって(ほとんどが職員の給料に消えてしまうので)、困っている知り合いに直接援助するのだったらいいのですが、よくわからない団体に寄付してもまともに使われているのか心配で、あまり良いお金の使い方には思えません。
地球の裏側の会った事の無い人たちに寄付しても、何だかもやもやするだけです。ユニセフもあまりよい噂を聞きません。トランプ大統領がUSAIDへの資金を止めようとするのにも一定の理解を示しています。世の中性善説だけでは回らないと思っています。
能登の震災など大きな事件があって、緊急で寄付が必要な場合には寄付しますが、毎月コンスタントに寄付を続けるというのは何か違う気もしています。
そう考えると、仕事を続けて得たお金の行き先が無いと、何のために働いていてお金を得ているのかよくわからなくなります。働くのは自分のためですが、働いて得たお金が何のためかという話ですね。
単に貯金や投資ばかりするのもどうかと思う一方、無駄遣いも嫌いです。こういう余剰資金に対してどういう考え方をすればよいのでしょうか。何かアイディアがありましたら教えてください。今後も動画応援しています」
とのことです。
ビルゲイツとかもそうですが、お金が余り過ぎている人は、どこかに寄付するのではなく、自分で財団を立ち上げて直接援助するみたいな形をとっていますね。他人にお金を渡すと、投資とおなじでどうなるかは他人次第なので運任せということになりますが、自分で財団を運営すれば自分の方針に沿った活動や運営ができます。他人任せではなく、自分でコントロールしているという感覚があった方が、有意義なことをやっているという実感があるのですね。
それと慈善事業団体をつくることは、自分のブランドをつくることにもなります。自分が亡くなった後も団体は残りますので、死後も世の中に対する影響力を持つことができますし、みんなも名前を忘れないでしょう。あと海外の場合は節税にもなりますので、いろいろとメリットがあるわけです。
日本でも公益社団法人の場合、寄付金が全額控除対象になりますし、相続税や贈与税の軽減にもなります。政治団体と同じで相続税対策や節税目的で使えないこともないですし、実際に東日本大震災の時に公益法人が、震災支援のために集めた寄付金を、実際には震災復興に使用せずに私的な利益に流用していた事件もありました。寄付金を適正に使用せず、関係者の生活費や事務所の運営費、役員の報酬や事業運営に使われていたことが判明したという、性善説に頼り切ってチェックあまあまな日本らしい事件というか、なかなかエグいことも行われていたりします。
そんなわけで質問者様がこういう団体を信じられないというのもわからないでもありませんので、質問者様が、それこそお金が有り余るレベルでお金を持っているのでしたら、自分でNPOでも立ち上げて、自分が支援したい分野に直接支援しに行くという活動をするのも良いとは思います。
ちなみに公益社団法人を作るにはちょっとハードルが高くて、内閣府の承認が必要になります。つまるところ政治家とずぶずぶな関係になる必要があったりなかったり、そもそもの政治家が自分で立ち上げてその資金を選挙目的で使ったりで、いろいろと闇が深かったりします。
NPOの方も認定NPOになるためには都道府県知事への登録申請が必要になりますが、公益社団法人よりは作りやすいです。税制的には公益社団法人よりだいぶ不利ですが、別に節税目的とか相続税対策でやるわけではないのだったら気にしなくていいとは思います。
申請するのも面倒だったら、非認定NPOでもいいですね。税制の優遇はありませんので寄付が集めにくいというのがありますが、その分面倒な会計報告義務もありません。
そんなわけでわけのわからない団体に寄付して、職員の生活費や役員報酬に消えていくのが嫌であれば、自分でNPO団体を立ち上げるというのも一つの手段です。
質問者様は世の中とのつながりを大切にしているようですし、自分でNPO団体を運営するのは案外あっているでのはないかとは思います。NPOといっても世界を救おうみたいな大きな話ではなくて、例えば日本は今少子化が進んでいる一方で子供の貧困問題もありますし、そういう子供達の支援をするのもいいんじゃないかと思います。
これも日本全国みたいな大きな範囲でなく、自分の住んでいる地域限定で支援すればいいですね。自分の目で見える範囲がよくなっていくという実感があればモチベーションも上がるでしょう。
NPOとまでいかなくても、料理が好きなら自宅で子ども食堂を運営して、近所の子供たちにふるまうというのでもいいとは思います。もしくは、勉強する場所を貸すということもできます。勉強を教えられるなら教えてあげてもいいでしょう。
それか近所で子ども食堂をやっている方がいれば、お金を寄付するなり食材を寄付するなりで、助けてあげるのもいいとは思います。すでに近所で活動している人がいれば、それに加わるのが一番楽ですね。
とにかく範囲は大きくしない方が良いです。目に見える範囲の、自分の地域を助けるぐらいで十分とは思います。子供たちのために自分の給料を使うのであればよい使い方とは思いますし、将来的にその子供たちはあなたに感謝するでしょう。人とのつながりを得たいという目的にも合致しているとは思います。
まあ、そこまで大きなことを考えずに、まずは近所からでいいとは思いますね。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・寄付先の団体が信じられない、寄付したことにストレスを感じるのであれば、お金の使い方としてはやめたほうがいいかと。
・自分で公益社団法人やNPO団体を立ち上げることで、自分で運営や使い先をコントロールできる。
・公益社団法人は寄付金控除や相続税や贈与税の軽減にも利用できるため、実際にえぐい事件が起こっている。また申請には内閣府の承認が必要なのでハードルが高い。
・認定NPOは都道府県知事への登録申請が必要だが、公益社団法人に比べればハードルは低め。
・非認的NPOであれば、寄付金控除などが無いので寄付を集めにくいが、報告義務も無いので自由に運営できる。
・そもそもそんなに大きなことを考えずに、近所の子供たちの支援など、地域に根付いた活動をした方が、目に見える範囲で効果がわかるし、人とのつながりもできるかと。(子ども食堂や勉強する場所を貸すなど)
・すでに近所で活動している人がいれば、それに加わるのが楽。
となります。
自分のためにお金を使うよりも、目に見える範囲の地域の人達を直接支援する形で使うというほうが、質問者様の性格に合っているんじゃないかとは思います。
これからの社会はお金を稼ぐことよりも、こういう目に見えない資本、いわゆるソーシャルキャピタルを稼いだほうが、のちのちの自分のためにもなりますしね。
そんなわけであまり無理に大きいことを考えず、まずは近所からやっていけばいいとは思います。すでに近所でやっている人がいれば、それに加わるのもいいですね。