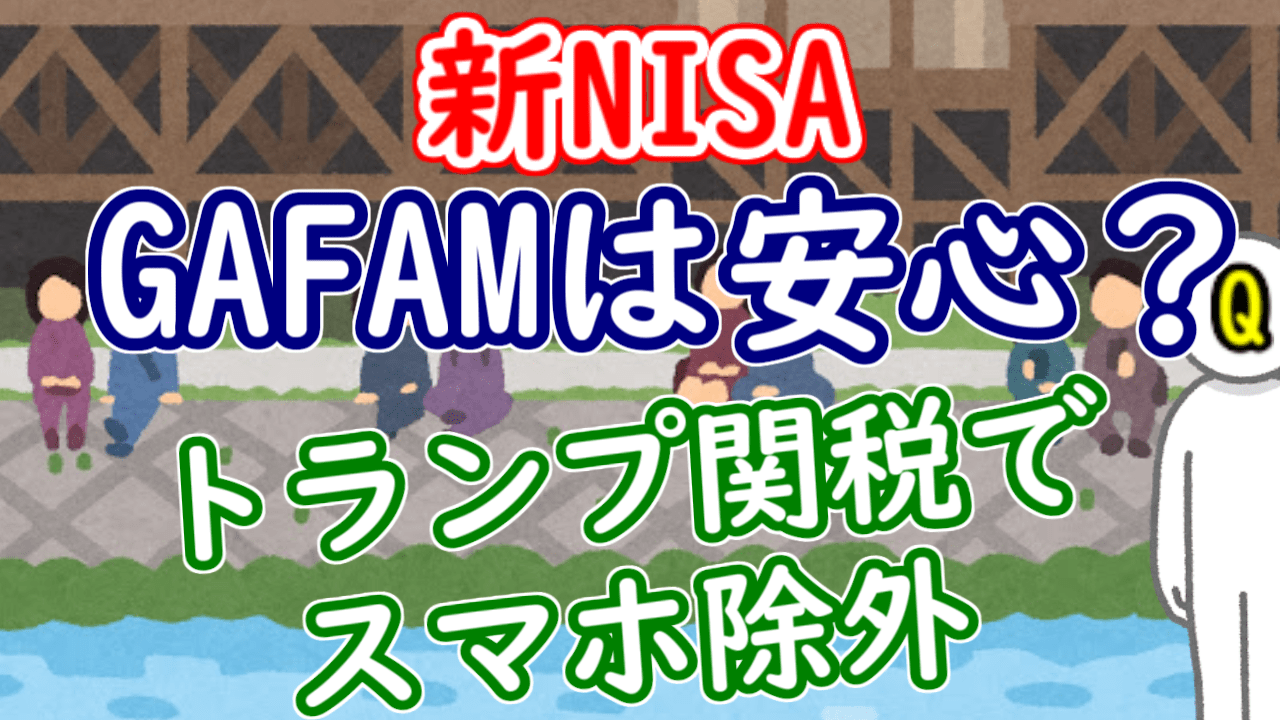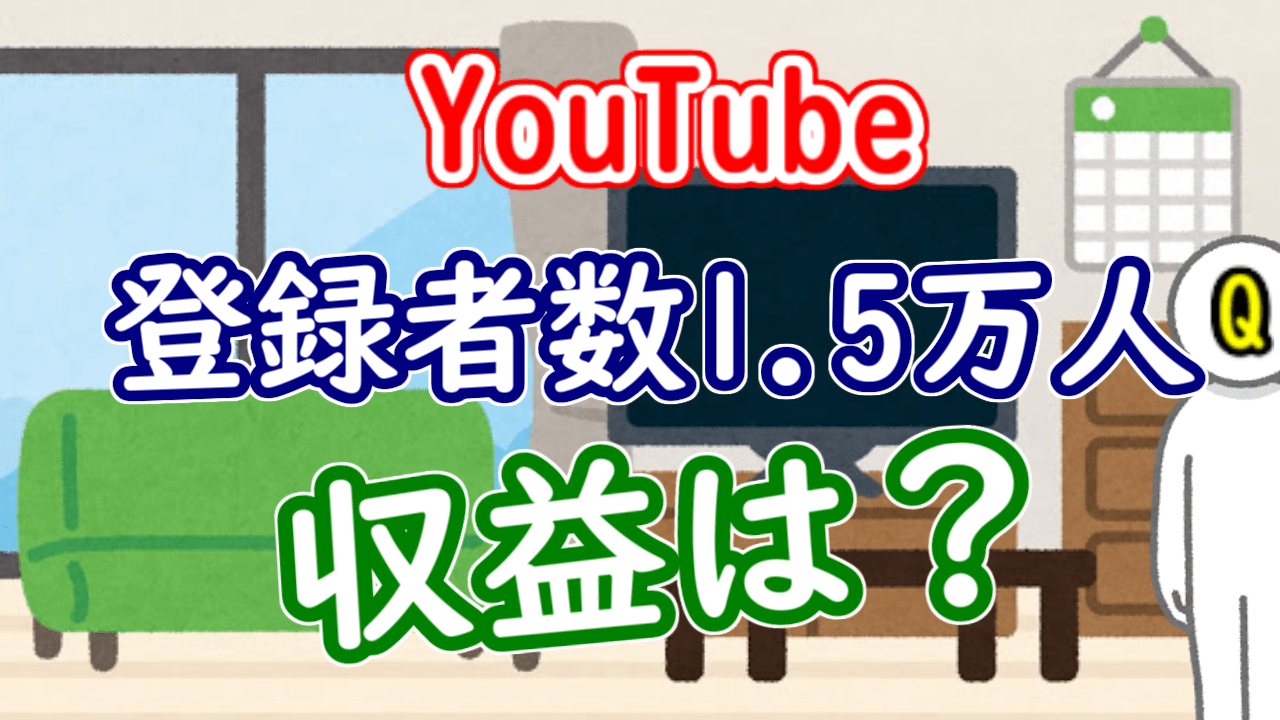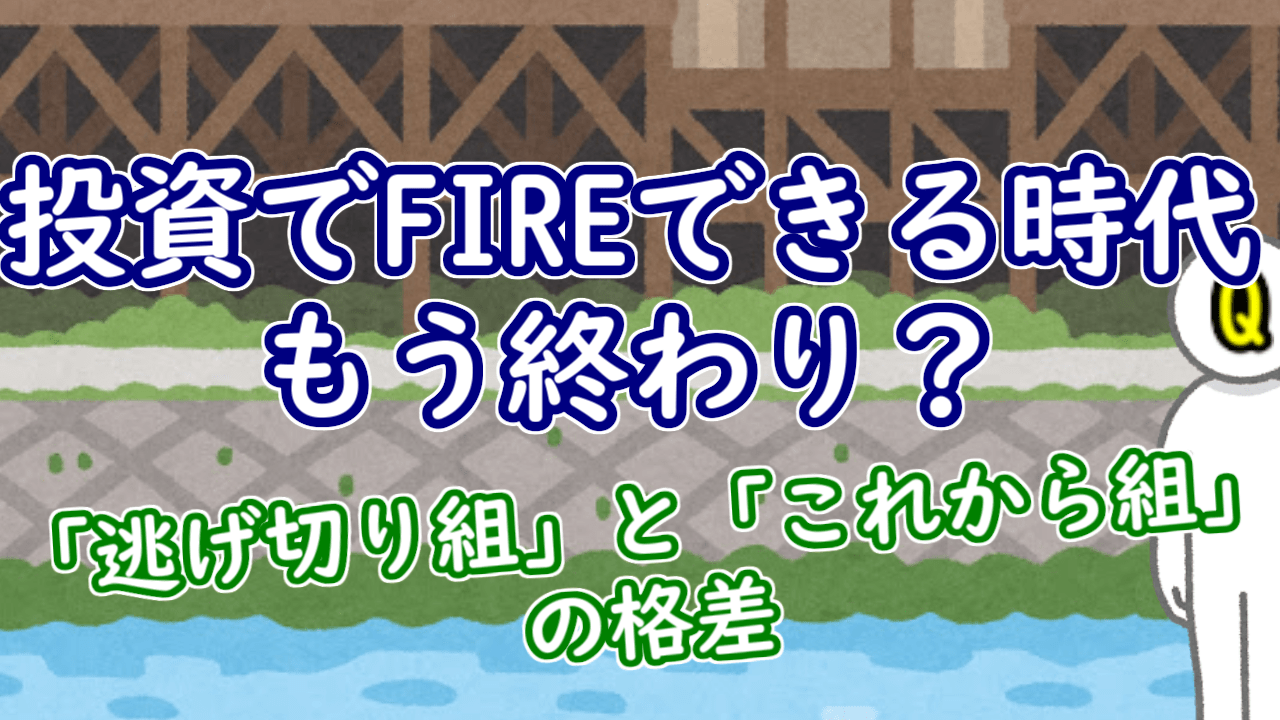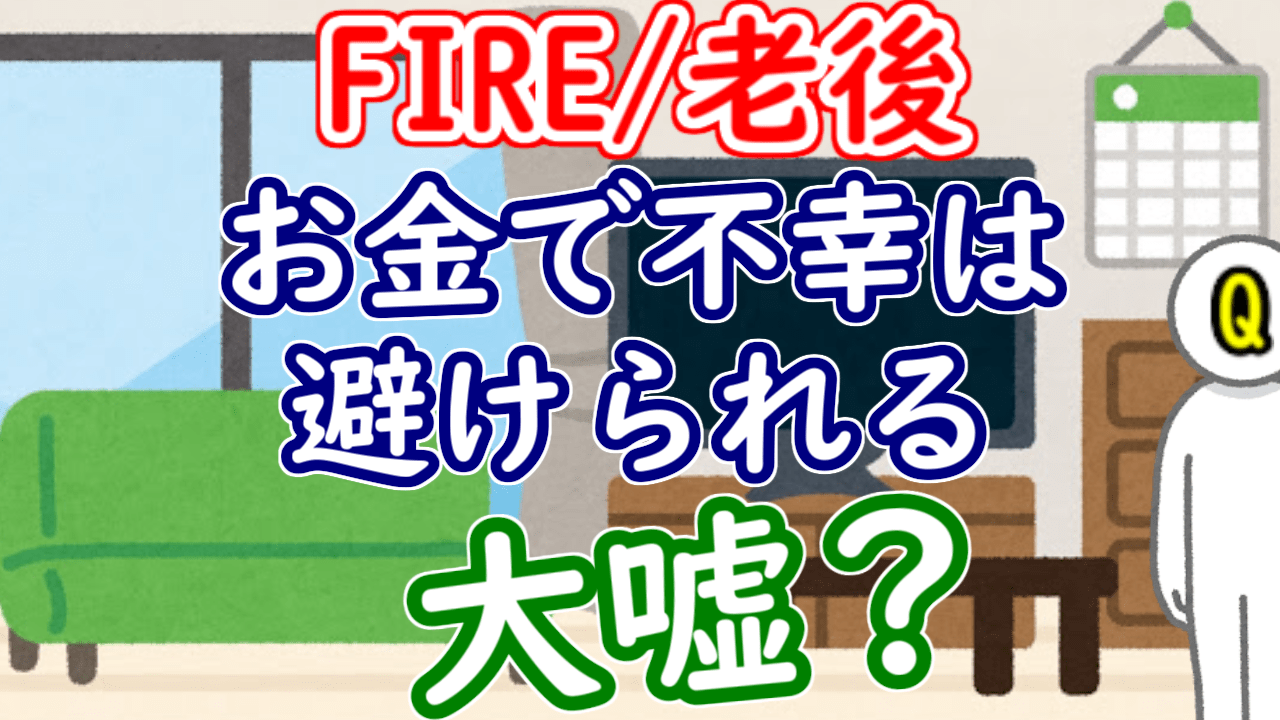
新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は、世間でよくいわれている「お金で幸せにはなれないけど、不幸は避けられる」ということは嘘ではないかとことについてです。
本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから。
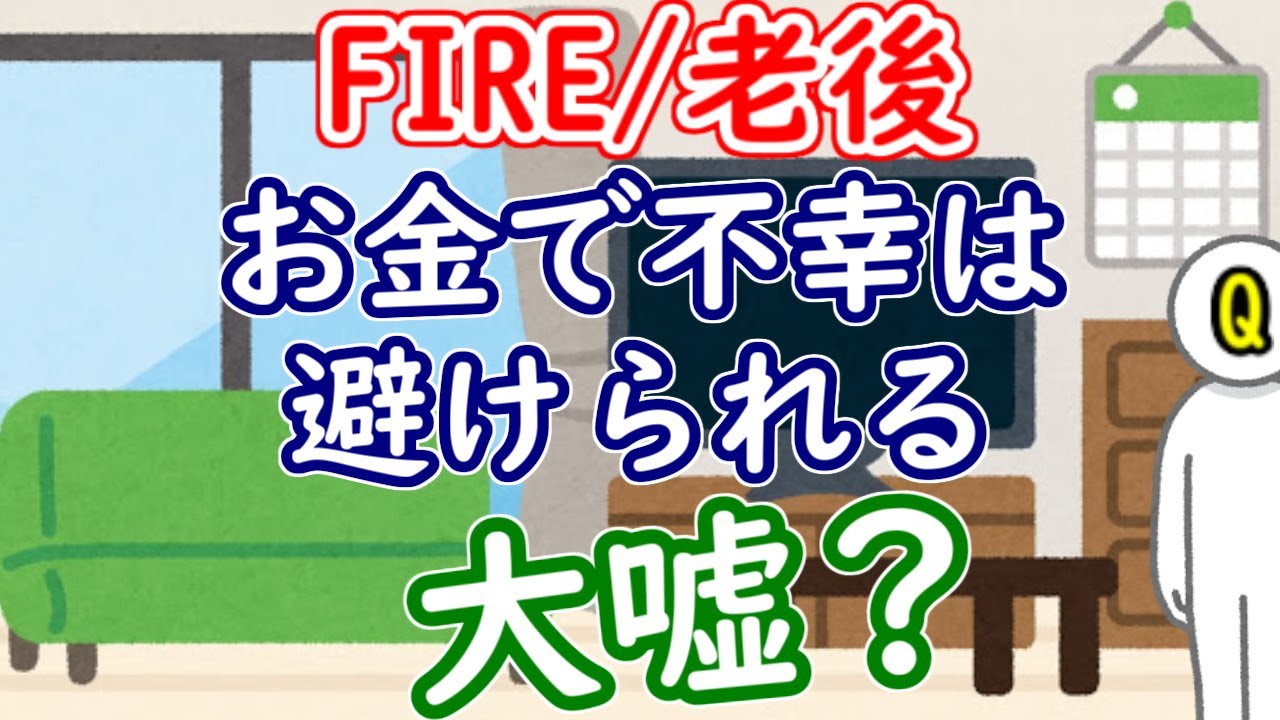
お金で不幸は避けられるは嘘?
こんなご質問をいただきました。
「いつもFIRE動画を拝見しています。
私は資金的にはFIREできるのですが、もうすぐ定年退職なのでする必要も無いと思い、そのまま勤めています。
忙しく働いているわけでもないですし、特に仕事がつらいとか感じたこともないため、ゆるゆるとコーストFIRE的な生活をしています。
それでFIRE後や老後ですが、多くの人が暇を持て余して不幸になっていると感じます。
お金があれば幸福になれるわけではないが、不幸は避けられると言いますが、お金があっても不幸すら避けられていない人も多いんじゃないかと思います。
例えば世界的に有名な映画俳優のロビン・ウイリアムズも、お金に困っているわけでもないうえに社会的地位も高いのに、最後は自殺してしまいました。
マイケル・ジャクソンやエルヴィス・プレスリーも薬物依存により、破壊的な生活を送って亡くなっています。
お金があれば不幸は避けられるも大嘘なのではないかと思えてきます。
これについてのQ太郎さんのご意見を聞きたいので宜しくお願い致します。」
とのことです。
いやー、なんか、本当にすみません。芸能人のこと、本当に疎いというか興味がなさすぎるので、ロビン・ウイリアムズが亡くなられていたことをこのご質問でいま初めて知りました。
マイケル・ジャクソンはさすがにわかりますが、ロビン・ウイリアムズも亡くなられていたのですね。
『いまを生きる』とかヒューマンドラマ系の映画に多く出演なされた方なのに、そんなことがあるのですね。いまさらですがちょっとびっくりしました。というか、調べてみたら、亡くなったのって2014年で、もう10年ぐらい前ですね。疎いにもほどがありますね。
それで亡くなる前には薬物中毒やアルコール依存症があったようですが、亡くなったときは違法薬物や中毒量のアルコールは検出されなかったそうなので、自殺と判断されたようです。
なんか芸能人=薬物みたいなイメージがありますが、どんどん達成と刺激を求め続けると、結局そういう形でしか満たされなくなってしまうのかもしれません。本当にいまさらですがお悔やみ申し上げます。『いまを生きる』の映画は好きだったのですけどね。そんなこともあるのですね。
そんなわけでご質問にある、よく一般的に言われている、「お金があれば幸福になれるわけではないが、不幸は避けられる」という話ですが、Q太郎的にもこれは物事の本質では無いとは思います。
他の動画でも何度か取り上げている、ショーペンハウワーの書いた『幸福について』ですが、この本では幸福について「すべては主観」としており、主観が豊かな人でなければ幸福は得られないとしています。これはローマ皇帝であるマルクス・アウレリウスの『自省録』でもおなじような話がされています。
客観的事実は万人にとっておなじものですが、主観は人によってちがいます。そしてその主観となる精神が豊かであるかどうかで、幸せの度合いが決まるとされています。
例えば株式市場が大きくズドンしたとします。ここでの客観的事実は「株式市場が大きく暴落した」ということだけでして、これに対して良いも悪いもなく、ただそこには暴落したという事実があるだけです。これは誰にとってもおなじ事実です。
ただこれをそれぞれの主観を通して観た場合、たとえば株を買っている人からすれば腹が立つとか悲しいとかいう話になりますし、株を空売りしている人からすれば大喜びな話になるわけです。
株を買っていない人からすればどうでもいい話ですね。
また例えば人が亡くなったとして、人が亡くなったというのは客観的事実ですが、その人の家族とかだったら悲しいわけですし、もしその人を恨んでいる人から見れば嬉しい話になります。その他大勢にとってはどうでもいい話でしょう。
つまり客観的事実があることと、それに対する主観はまったく話が違うわけで、幸せかどうかというのも客観的事実の問題ではなく、主観の問題ということにもなります。
先ほどの話にも出てきた有名人たちですが、たとえば彼らが「お金を持っていて、社会的にも高い地位」であることは、これは客観的な事実であるわけです。
これに対して個々人の主観は違うわけで、「お金を持っていて、社会的にも高い地位」という客観的事実に対して、主観として幸せを感じない人は、お金や社会的地位では幸せになれないわけです。
この手の幸せの問題というのは、達成するまではいろいろ頑張るのですが、達成したあとは、しばらくは幸せかもしれませんが、すぐにその状態に慣れてしまって、さらなる別の目的を探そうとするのですね。
そのため、達成で幸せを感じる人たちが、真の意味で幸せになるのは難しいということになります。けっきょく「もっともっと」になってしまうだけなのです。
芸能人とかも、ある程度のぼりつめてしまうと、ほかに達成できるものが見つからなくなるので、その代わりとして薬物に手を染めてみたりとか、べつの方法で達成時に得られる幸せを追い求めようとするのですね。
目標を持って生きるのはいいですが、どこかで歯止めが必要なわけで、この「もっともっと」になると主観がおかしくなっているので、ひたすら不幸な主観へ一直線になるわけです。
お金を貯めている人が陥りやすいのもこの点でして、たとえば銀行口座に6000万円あったとして、客観的事実としては「銀行口座に6000万円がある」ということだけです。
ただこれを主観で見た場合、人によっては「こんだけあればもう十分」と思う人もいれば、「6000万円では足りない。もっと稼ぎたい」と思う人もいるわけです。「苦労して貯めたから減らしたくない」と思う人もいるでしょう。
でも客観的事実は「銀行口座に6000万円」というだけで、それ以上でもそれ以下でもないわけです。主観が勝手にこの状況を幸福にしたり不幸にしたりしているわけです。
カツカツでも幸せな人はいますし、6000万円あっても足りなくて不幸せと思う人もいます。
それで「お金があれば不幸は避けられる」という言葉ですが、この言葉がおかしいのは客観と主観が混ざってしまっているからなのですね。
「お金がある」は客観的事実です。「不幸は避けられる」は主観です。不幸が避けられるかどうかは状況によりますし、その人の考え方にもよります。不幸の定義も幸福とおなじく主観だからですね。
つまるところ「お金がある(客観)=不幸が避けられる(主観)」ではないのです。
たとえばお金があれば病院に行けるといいますが、病院に行けたとしても助かるとは限りません。
ロビン・ウィリアムズもお金があって病院に行っていますけど、助かってはいないのです。
さらに言えば「病院に行って助かった」というのも単に客観的事実であって、これが幸福なのかどうかはその人の主観によります。
すごいつらい病気で、楽に死ねそうなタイミングで蘇生させられたりとかだったら、「ふざけんな」と思う人もいるかもしれません。
病気自体は治ったかもしれませんが、一生病院のベッドから動くことができないとかだったら、主観的にそれを不幸に思うかもしれません。
そのため「お金がある」と「不幸が避けられる」はまったく関係のない話でして、病気が治るとか欲しい物が買えるとかも単にそれは客観的な事実なだけで、その人の主観でそれが幸福かどうかはまったく別な話なわけです。
「病気が治る(客観)=不幸が避けられる(主観)」はイコールではなくて、すべてはその人の主観の問題なわけです。病気をその人が不幸と考えているかどうかの問題もありますしね。
そのため、「お金があると不幸は避けられる」というは、客観と主観というまったく別の論議を一緒くたに混ぜてしてしまっていることから、なんでやねんという話になるわけです。「お金があると幸福になる」とロジック的にはまったく同じことをいっているのですね。客観と主観が混ざっているのです。大嘘というか、そもそものロジックがおかしいわけです。
それでこの主観ですが、ショーペンハウワーはこのことについて、「私たちは何を幸福とし、何を享受するかということにとって、主観は客観とは比べ物にならないほど重要である」と述べています。
さらには「個性によって、その人に可能な幸福の範囲はあらかじめ決まっている」といい、「精神的能力が狭いと、外部からどんなに尽力しても、どんな幸運に恵まれていても、半ば獣めいた人間の幸福と心地よさの程度を上回ることができず、官能的な楽しみ、気楽でにぎやかな家庭生活、高尚とはいいがたい社交、通俗的な暇つぶしに頼り続けることになる」となかなかに辛辣ですが、けっこう当たっているとは思います。
こういうことを今から230年以上前に生まれた人が語っているのですから、人類がどれほど進化しないのかがわかるとは思います。
「通俗的な暇つぶしに頼り続けることになる」というあたりも、ゲームやスマホの登場を予見していたかのようですね。
教育によって、この主観の領分を広げることはできますが、ショーペンハウワーに言わせれば、「教育は主観の領分を広げるにはちょっとは役に立つかもしれないけど、総じて役に立たない。もっとも高尚で多様性に富み、もっとも長続きする喜びは(外部に依存しない)精神的な喜びであり、これは主としてもって生まれた力に左右される」と述べています。ある程度は生まれ持った性格や遺伝で決まってしまうということですね。
ちなみに遺伝の仕組みを発見したメンデルさんが生まれたのは1822年で、ショーペンハウワーは1788年なので、遺伝の仕組みを発見するよりも前なのですね。
いまでは努力できる・できないすらも遺伝が関係しているという身もふたもない事実も判明してしまっていて、遺伝の影響がかなり大きいことがわかっていますが、ショーペンハウワーは感覚的にそのことに気づいていたのではないかとは思います。
ショーペンハウワーは「幸福とは、各人の個性に左右されるのは明らかだ。内面が豊かであれば、何を持っているのかや、いかなるイメージをあたえるのかという点で多くを要求しない」と述べており、けっきょくのところ、個人個人の資質によって主観が決まり、うまれつき幸せになりやすい人となりにくい人がいるという身も蓋もない話に落ち着いてしまうわけです。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・客観的事実は万人にとっておなじだけど、それに対する主観は個々人で違う。
・「お金がある(客観)」と「不幸が避けられる(主観)」はまったく別のことなので、それを混ぜていることにロジックのおかしさがある。「お金があると幸福になる」と言っていることはロジック的にまったく一緒。
・個性によって、その人に可能な幸福の範囲はあらかじめ決まっている。
・精神的能力が狭いと、外部からどんなに尽力しても、どんな幸運に恵まれていても、人間の幸福と心地よさの程度を上回ることができず、享楽や通俗的な楽しみにふけることになる。
・もっとも高尚で多様性に読み、もっとも長続きする喜びは(外部に依存しない)精神的な喜びであり、これは主としてもって生まれた力に左右される。
・遺伝の影響は大きい。個人個人の資質によって主観が決まり、うまれつき幸せになりやすい人となりにくい人がいる。
となります。
そんなわけで、「お金があれば不幸は避けられる」というのは大ウソというよりも、ロジック的に客観と主観が入り混じった話になってしまっているため、「お金があれば幸福になれる」とまったくおなじロジックを展開しているだけなのです。
お金があって楽になることは客観的事実であったとしても、楽になることが主観的に幸福なのかどうかは全く別の話なのですね。病気の話もおなじです。
そんなわけで不幸かどうかは主観の話なので、お金があることと不幸が避けられることはまったく別のロジックなので、そこを混同してしまうと物事の本質が見えにくくなるとは思います。
もしお時間ありましたら、ショーペンハウワーの『幸福について』を読んでみるといいとは思います。