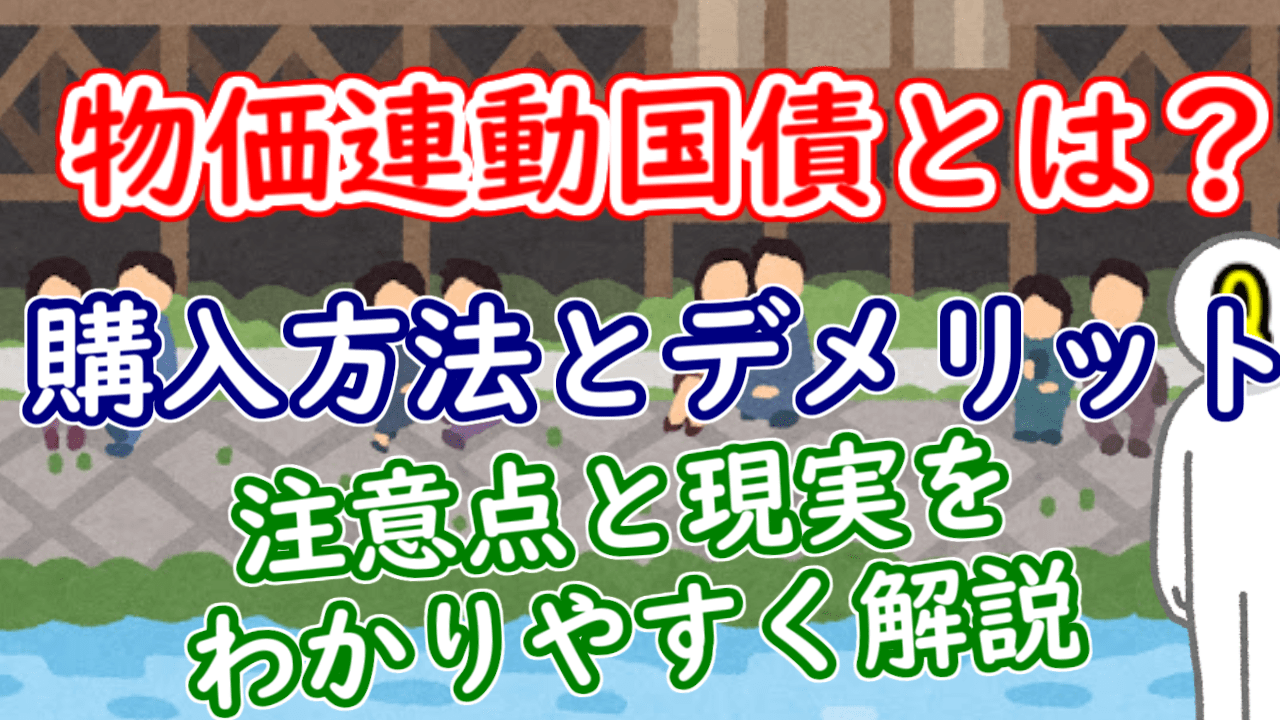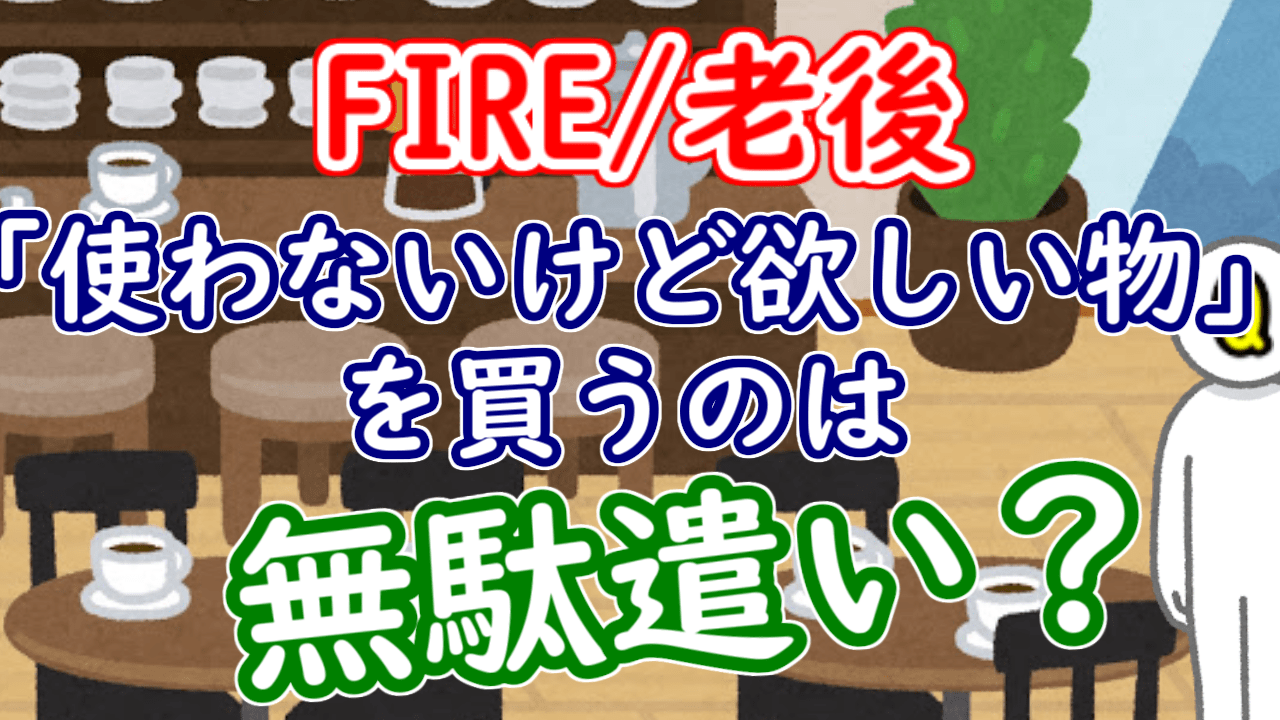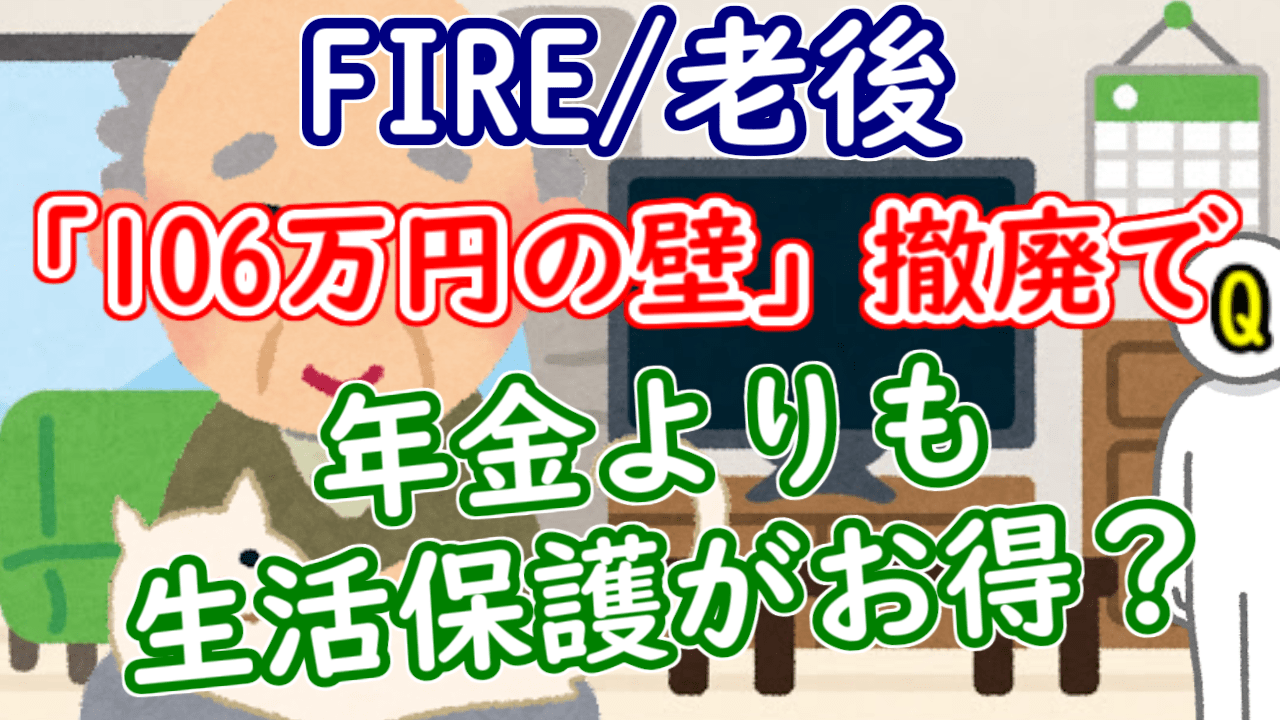
新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は106万円の壁撤廃により、年金よりも生活保護をとったほうがいいんじゃないかというご質問についてです。
本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから。
年金よりも生活保護?
こんなご質問をいただきました。
「106万円の壁廃止が決まり、国民の負担がますます増えることになりました。
政府側としては、パートの人でも厚生年金が増えるのでいいことなのではないかとのことですが、そもそも何十年後かに厚生年金が増えているかどうかなんて誰にもわかりません。今より減っている可能性もあります。「将来増える」などと思える人は、さすがに頭お花畑としか思えません。
どう考えても目先の保険料が足りなくて、無理やり徴収しに来ているだけとしか思えません。
こうなってしまうと、働くのがますます馬鹿らしくなってしまい、年金よりも生活保護を目指した方がいいようにも思えてきます。中途半端に年金をもらうと、むしろ生活保護が取りづらくなります。
生活保護は医療費完全無料なので、額面以上のメリットがあります。低収入の人が下手に働くと馬鹿を見るだけです。
老後戦略として、70歳にもなって働くという馬鹿馬鹿しいことをするよりも、おとなしく生活保護を受け取った方がよほど豊かな生活を送れるのではないでしょうか。この点についてどう思われますか?」
とのことです。
「106万円の壁」ですが、基礎控除を上げる「103万円の壁」みたいにいかにもお得そうな名前なので勘違いされがちなのですが、これまで厚生年金保険料を払わなくてよかった年収106万円以下の人たちが、年収にかかわらず全員厚生年金保険料を保険料を払わなくてはならなくなったので、単純に毎月の手取りが減ってしまう可能性があります。
ただ、注意しなくてはならないのが、一方で手取りが増える人もいます。いわゆる自営業や年収の低い人たちなど、「第1号被保険者」です。会社員は「第2号被保険者」ですね。
Q太郎もそうですが、自営業者や個人事業主などの国民健康保険料は所得の15%などけっこうえぐい金額をとられますので、こういう人たちが生活費を補うために賃金労働していた場合も、稼ぎが少ないと、会社員よりも多い健康保険料を取られることになります。
それで106万円の壁が撤廃された場合、自営業者が賃金労働をすることによって低収入でも「第2号被保険者」になることができます。「第2号被保険者」のほうの保険に入ることになるため、保険料は雇用主が最低50%を負担してくれますし、賃金労働のほうの低い収入で計算されますので、国民健康保険料はかなり安くなります。
健康保険はどこか1か所で加入していればいいので、自分の本業で1億円稼いだとしてもその収入から保険料を払わずに、雇用の安い収入のほうから保険料を払うという、いわゆるマイクロ法人節税みたいなテクニックが使えそうな感じがあります。自分でマイクロ法人を作って、本業とは別の仕事としてそこから安い給料払って、保険料も安い給料で計算して払うことで、本業の収入からの保険料を計算させないというせこい節税方法のことですね。
やる気はないですけど、ルール的にはできるんじゃないかという感じで、保険料の確保という面からすればどうなんだろうという気もしてきます。というか、税金増やしたいのに、いまだにマイクロ法人を取り締まらないのが意味不明な気がします。国民健康保険料の上限が109万円程度なので、大した金額じゃないといえばそうなのかもしれませんが。
そんな感じで全員が損するわけではなく、自営業者がうまくやれば保険料を節約できるお手軽マイクロ法人みたいな感じで節税できそうな気はします。
ちなみに現在、雇用による年収が足りなくて「第2号被保険者」になれずに、「第1号被保険者」の高い健康保険料を払っている人たちが70万人ほどいるといわれていますので、この人たちが「第2号被保険者」になれば健康保険料は安くなりますから、手取りが増えることになります。
そのため、一概に手取りが減るわけではないことは注意が必要です。得する人もいます。
それで損する人たちは誰かといえば、パートをしている主婦などの「第3号被保険者」です。「第3号被保険者」はパートナーが保険料を払っているため、そもそも保険料を払わずに国民年金がもらえます。こちらは90万人ほどいますが、これらの人たちが「第2号被保険者」になってしまうため、保険料を負担しなければならなくなるので、手取りは減ることになります。
まとめれば、「低収入の第一号被保険者は「第2号被保険者」の保険料をつかえるので手取りが増えるけど、第三号被保険者は払わなくてよかった保険料を払わなくてはならなくなるので手取りが減る」ことになります。パートナーが「第2号被保険者」として働いているケースですね。
年金は減る?
それで質問者様のおっしゃられるように、将来的に厚生年金がいくらになるかなんてわかりませんので、単純に「将来の年金が増える」と思ってしまうことはできないとは思います。そもそもの実質年金が減っている一方で、年金保険料が上がっている状況ですしね。
未来のことは本当にわかりませんし、何十年後かに年金崩壊どころか最悪日本自体が滅びているケースもありますので、不確定な何十年後にあまり希望を持つのもどうかという気もするとは思います。単純に「保険料アップ=年金アップ」じゃないことは、今の年金を見ればわかるわけです。そもそもこれからも日本はどんどん人口減っていきますし、現役が高齢者を支えるという構造である以上、減るのはほぼ確定ですしね。
その一方で、氷河期世代や低所得者が本当に必要としている国民年金の底上げは見送られました。取る方はたくさん取るけど、払う方はしぶるという感じで、まあ将来的にもそんな感じが続きそうです。そもそも現役世代が減ってますしね。
それで「106万円の壁」についてですが、ちゃんと見ていきますと、厚生年金加入条件の週20時間以上は撤廃されていないため、厚生年金保険料を払いたくない「第三号被保険者」である主婦パートの方々たちによる働き控えが起こる可能性もあります。労働力確保という点では微妙なことになりそうな気もします。
それで年金と生活保護のどちらが良いかという話ですが、そもそも年金額が生活保護に届かなかった場合、生活保護を申請すれば不足分が補われる形になります。
生活保護はあくまでも最後のセーフティネットなので、最初から狙って取りに行くようなものでもないとは思います。将来的に制度が変わる可能性もありますし、いますでに70歳とか80歳なら現状の制度が使えるのでOKですが、まだ現役世代で今からそれを狙うと、将来制度が変わったりなどの不測の事態に備えられなくなるので、ろくな結果にならない気もします。
とにかく国の制度が将来にわたって確実につづいていくという考えは持たない方がよいとは思います。諸行無常の世の中です。そのときそのときの状況から手を打っていくのがいいでしょう。コントロールできるのは、せいぜい5年ぐらい先の未来までですね。それ以上先は本当になにが起こるかわかりません。
生活保護が年金よりお得かどうかも、そのときじゃないとわかりませんしね。スマホの登場なんて、誰もわかりませんでしたしね。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・106万円の壁撤廃は、全員が損するわけではない。
・自営業者など国民健康保険を払っていた「第1号被保険者」は、保険料の安い「第2号被保険者」になれるので、保険料を減らすことができる。(本業で稼いで、保険料は安い給料から出すというマイクロ法人テクニックも使えそうな感じはありますがどうなるかわかりません)。
・主婦など「第3号被保険者」は、払わなくてよかった保険料を払わないといけないので、手取りが減る。
・将来年金が減るかどうかわからないが、そもそもの現役世代が減るので年金も減る確率は高い。
・年金額が生活保護に届かなかった場合、生活保護を申請すれば不足分が補われる。
・生活保護はあくまでも最後のセーフティネット。最初から狙って取りに行くようなものでもない。(いますぐ取りに行くならいいですけど、何十年後のために最初から狙って取りに行くと、制度が変わってしまうなどのリスクがあります)。
・国の制度が将来にわたって確実につづいていくという考えは持たない方がよい。コントロールできるのはせいぜい5年先までぐらい。(変化していく世の中なので、変化が当たり前と思ったほうがいいでしょう。諸行無常ですね)
・生活保護が年金よりお得かどうかも、そのときにならないとわからない。
となります。
日本は変化を好まない社会ですが、人は時間とともに老いますし、いつ死ぬかなんてわかったものではありませんので、あまり先を見て計画を立てすぎるのもどうなのかという気はします。
老後のためにいまから生活保護を目標にするよりは、老後は老後でそのときに考えて、だめそうなら生活保護をとるぐらいの感じでいいんじゃないかとは思いますね。生活保護を取るのはいつでもできますしね。そのときには制度が変わってるかもしれませんけどね。ベーシックインカムが導入されてたら、これまでの苦労はなんだったんだみたいなことにもなりかねません。
そんなわけであまり将来を観すぎずに、50歳もすぎればせいぜい5年ぐらいの感覚で、気楽に将来計画をしていけばいいんじゃないかとは思います。たぶんスマホの登場みたいに、こっちが想像もつかないようなことが起こっている可能性もありますしね。