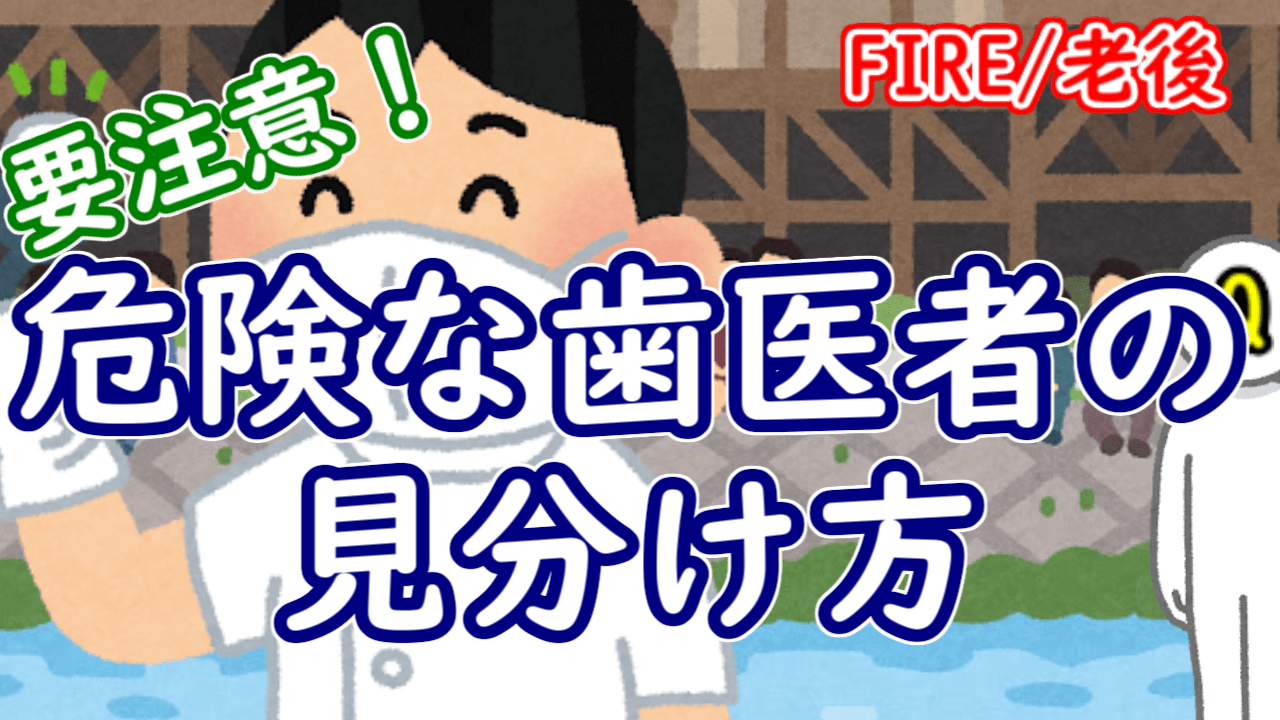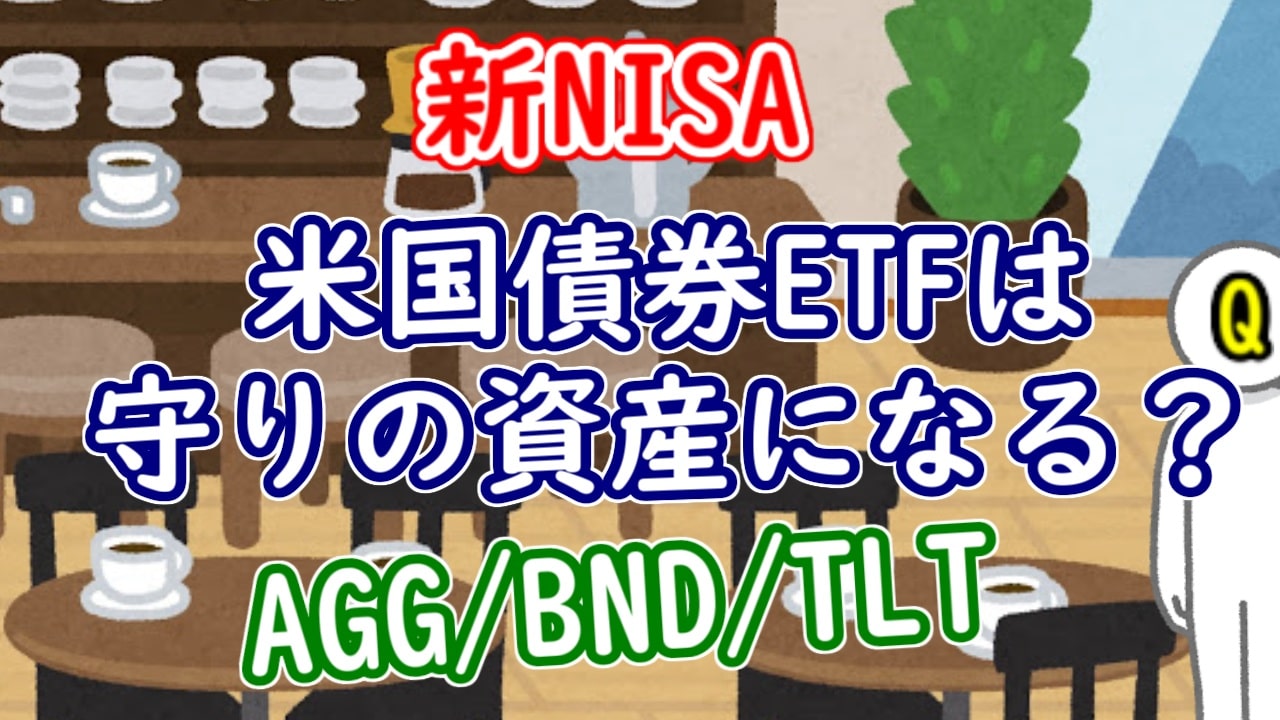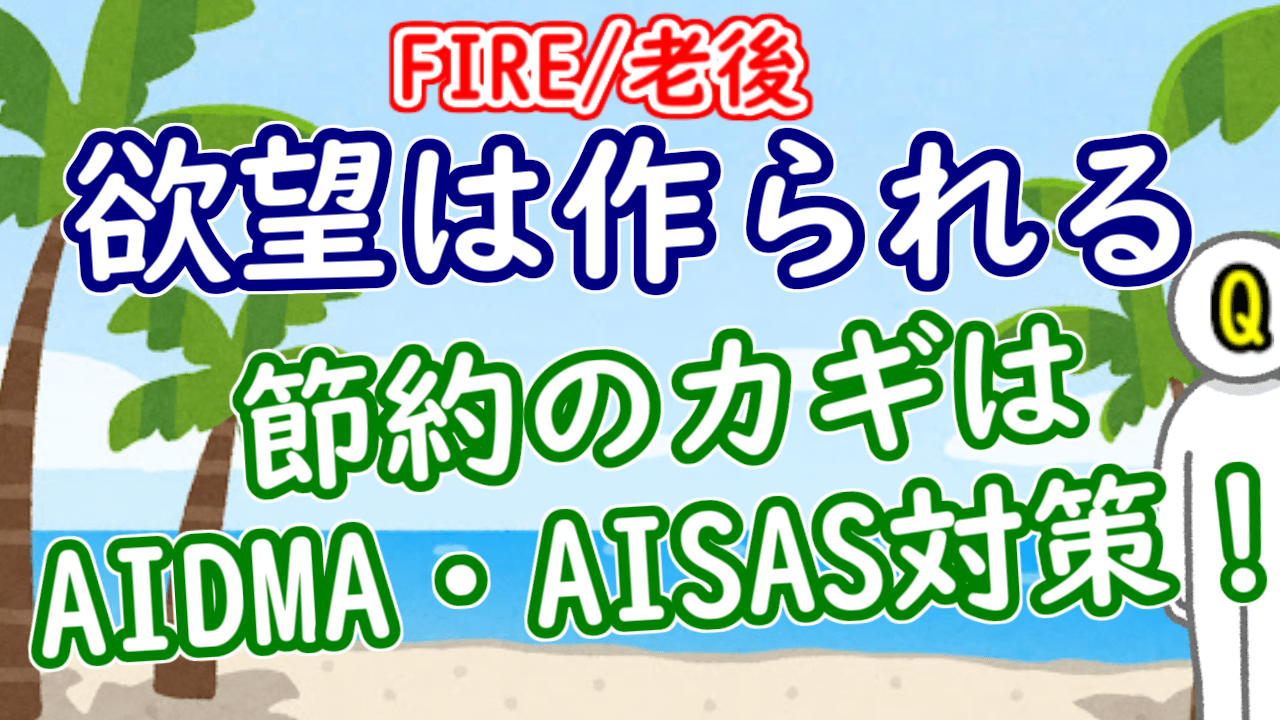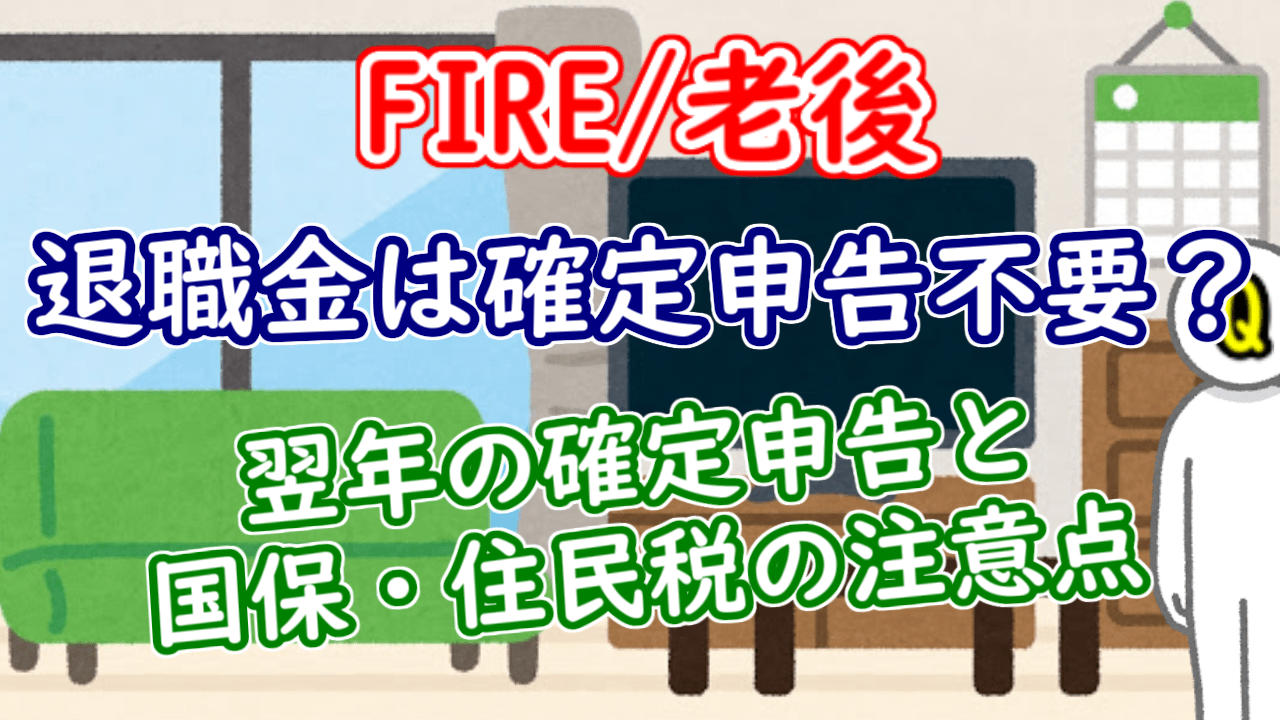
新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は、退職した翌年の確定申告についてです。
本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから。
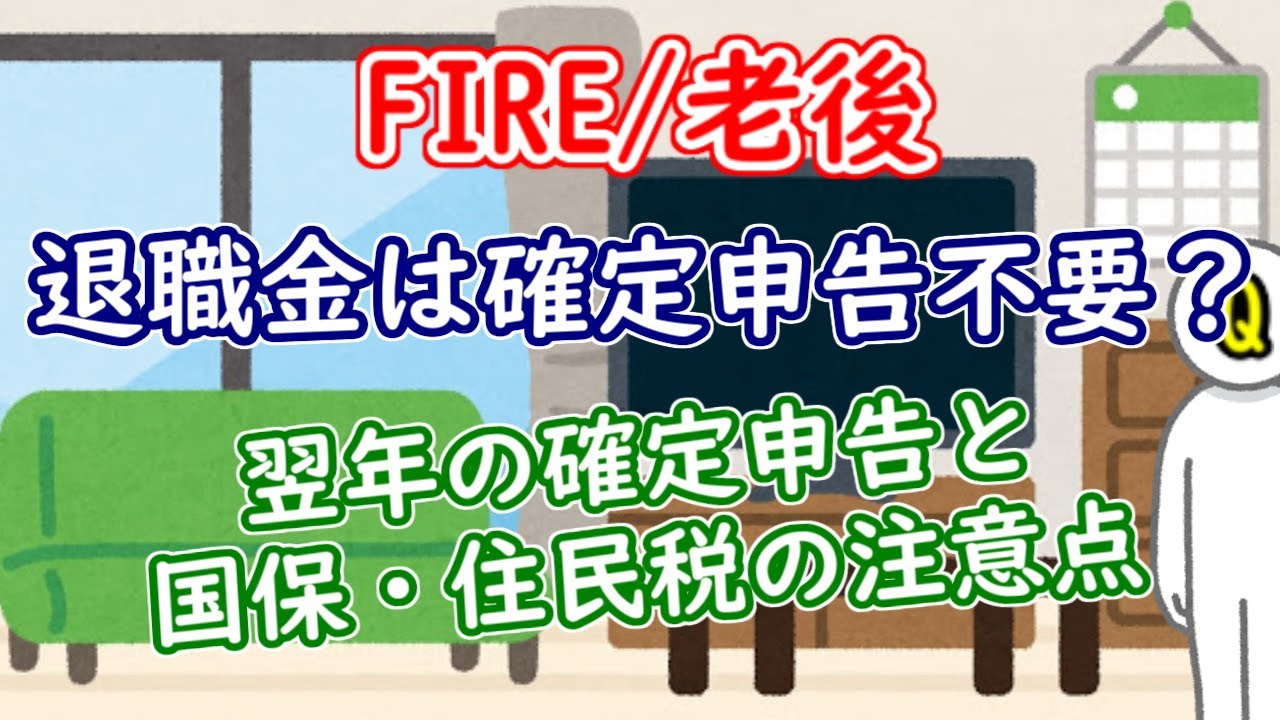
退職金は確定申告不要?
こんなご質問をいただきました。
「いつも楽しみに聴いております。どうもありがとうございます。1つ質問です。
普通の一般的な会社員かつ正社員の場合で 退職金➕給料の確定申告と、その住民税と国民健康保険料の増額等に関する質問です。
例えばですが2025年3月に退職した場合で、 退職金をもらった場合、 2025年1月から3月までの給料と退職金を 確定申告した場合、その内容が反映された国民健康保険料と住民税が高くなってしまうなどのマイナスの影響がありますか?
こちらの基本的な認識としては、 退職金は社会保険料の増額に関係しないので、1月から3月の給料を確定申告する際に、退職金の額を申告しても、翌年度の社会保険料(国民健康保険料)の増額には関係しない。
住民税における退職金の考え方は、勤続年数によって、かなり税額控除が適用されるため、かなり限定的に住民税に反映される。よって、驚くほどの住民税増額とはならない。退職手当に関しては、確定申告の有無にかかわらず、翌年度の住民税に反映される。
以上のような認識ですが、住民税と、国民健康保険料の2つにマイナスの影響が出てしまうようなら、確定申告しないほうがいいのでしょうか?
2025年1月から3月までの給料のみについて確定申告を行うと言うことも可能でしょうか?
退職した人間が確定申告を行った方が良いかどうかについて悩んでいる人も多いかと思います 動画等でご回答いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。」
とのことです。
まず基本的に退職金は分離課税ですし、会社側で源泉徴収されますので、基本的には確定申告は不要です。確定申告不要であるため、国民健康保険料は発生しません。
これについては国税庁のサイトにも「退職金は、勤務先に所定の手続をしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。」ともろに書いています。
それでここで注意なのですが、「勤務先に所定の手続をしておけば、」の部分ですね。これは退職金を受け取る前に、「退職所得の受給に関する申告書」を会社側に提出しておく必要があります。これを提出することによって、勤務年数に応じた退職所得控除が受けられます。
提出しなかった場合どうなるかと言えば、退職所得控除が受けられず、退職金に対し一律20.42%の所得税等が源泉徴収されて、その残った金額をいただくという形になってしまうのですね。そうなると確定申告して退職所得控除分を取り返す必要があります。取り返したくないならそのまま放置でもいいですが、退職所得控除はけっこう額になるので、普通は取り返すために確定申告しておいた方が良いでしょう。
そういうのが面倒な人は、退職金を受け取る前に、会社側に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておくといいでしょう。これは国税庁のサイトにPDFがありますので、それを印刷して記入し、会社側に提出することになります。会社側で用意してくれる場合もあるので、このあたりは自分の会社に前もって聞いておけばいいとは思います。
退職所得控除が優れているのは、控除額がかなり大きいのですね。
20年以下:40万円×勤続年数
20年超の部分:70万円X勤続年数
とかなり控除してくれます。
たとえば30年勤めていた場合、40万円×20年+70万円×10ですから1500万円まで無税になります。かなりでかいですね。利用しない手はないわけです。
そのため、確定申告が面倒で損したくない人は、退職金を受け取る前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社側に提出しておいてください。提出しなかったらこの控除がなくて、一律20.42%が源泉徴収されます。
たとえば30年勤務で退職金が2000万円だったとしたら、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していた場合、税金のかかる部分は500万円ですが、これがさらに2分の1になるという特典もついているので、250万円になります。
250万円に対する所得税は累進課税で10%ですので、250万円X10%ー97,500円=15.25万円が税金になります。退職金はかなり優遇されていますね。
ところが「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかったら、受け取った退職金収入に一律20.42%が源泉徴収されてしまいます。翌年確定申告すれば、退職所得控除分を取り返せますので、「確定申告面倒だし、数百万円ぐらいいいや」という太っ腹な人以外はやっておいたほうがいいでしょう。
なんにしろ、退職金を受け取るまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておかないと、退職所得控除が受けられないので注意してください。
それで仮に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないので確定申告をした場合、国民健康保険料が発生するかどうかについてですが、国民健康保険料の算定基準は 前年の総所得金額等です。「退職所得」は総所得金額等に含まれませんので、国民健康保険料は発生しないことになります。
ちなみに株式の分離課税は確定申告した場合、総所得金額等に含まれますので、国民健康保険料の計算に含まれます。特定口座であれば、譲渡損失が無い場合はする必要はないでしょう。
それで退職前の1~3月分の給料についてですが、こちらは確定申告をした方が良いでしょう。
3月退職だと、会社に所属していない以上年末調整はしてくれません。ただ源泉徴収自体は会社側でしてしまっているため、そのままだと「源泉徴収の仮精算」の状態になります。このままだと税金を多く取られている状態になるため、確定申告をして還付してもらうことになります。
また1~3月分の給料を確定申告することにより、国民健康保険料と住民税の金額も決まります。
さらに仮にこの1~3月分の給料を確定申告しなかった場合にどうなるかと言えば、しなかったとしても会社側から 源泉徴収票 の内容が市区町村に提出されます(給与支払報告書)。そしてそれをもとにして住民税や国民健康保険料が決まりますので、確定申告しなくても役所から請求書が来てこれらを払うことになりますし、おそらく計算上は多めに払うことになるとは思います。
そんなわけで税金を安くしたければ、1~3月の給料分は確定申告はして、還付金をもらっておいた方が良いでしょう。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・退職金は分離課税で源泉領収されるので、基本確定申告は不要。
・国民健康保険料の算定基準は 前年の総所得金額等。「退職所得」は総所得金額等に含まれないため、確定申告した場合も国民健康保険料の計算には入らない。
・ただ会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、退職所得収入に一律20.42%が源泉徴収されてしまう(退職所得控除無し。翌年の確定申告で取り返せるが、できれば提出しておいた方が良い)。
・退職所得控除は
20年以下:40万円×勤続年数
20年超の部分:70万円X勤続年数
の残りの金額をさらに2分の1にしたものを退職所得にしてくれるのでかなりお得。
・1~3月分の給料は確定申告必要。多めに取られている場合が多いので還付が受けられる。
・1~3月分を確定申告しなかった場合でも、源泉徴収票 の内容が市区町村に提出されるので、住民税と国民健康保険料の請求は届く(高めに計算されるので確定申告した方が良いです)。
となります。
そんなわけで、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していて、退職所得控除をすでに受けているのであれば、1~3月分の給料だけを確定申告しておけばいいとは思います。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなくて、一律20.42%を取られてしまっているのであれば、取り返すために確定申告をしたほうがいいですね。した場合でも退職所得は国民健康保険料の計算には入りません。
そんな感じで、まずは退職金の源泉徴収票を見て、どういう税金の取られ方をしているかを確認しておくのがいいでしょう。