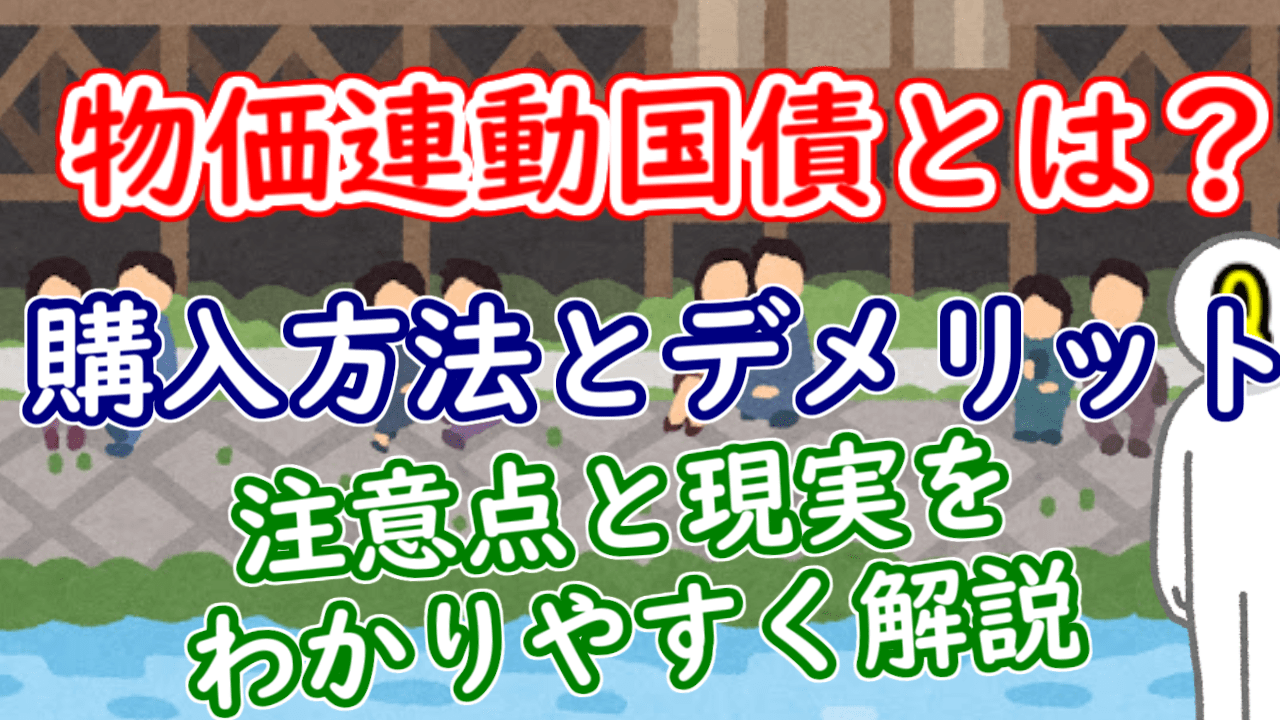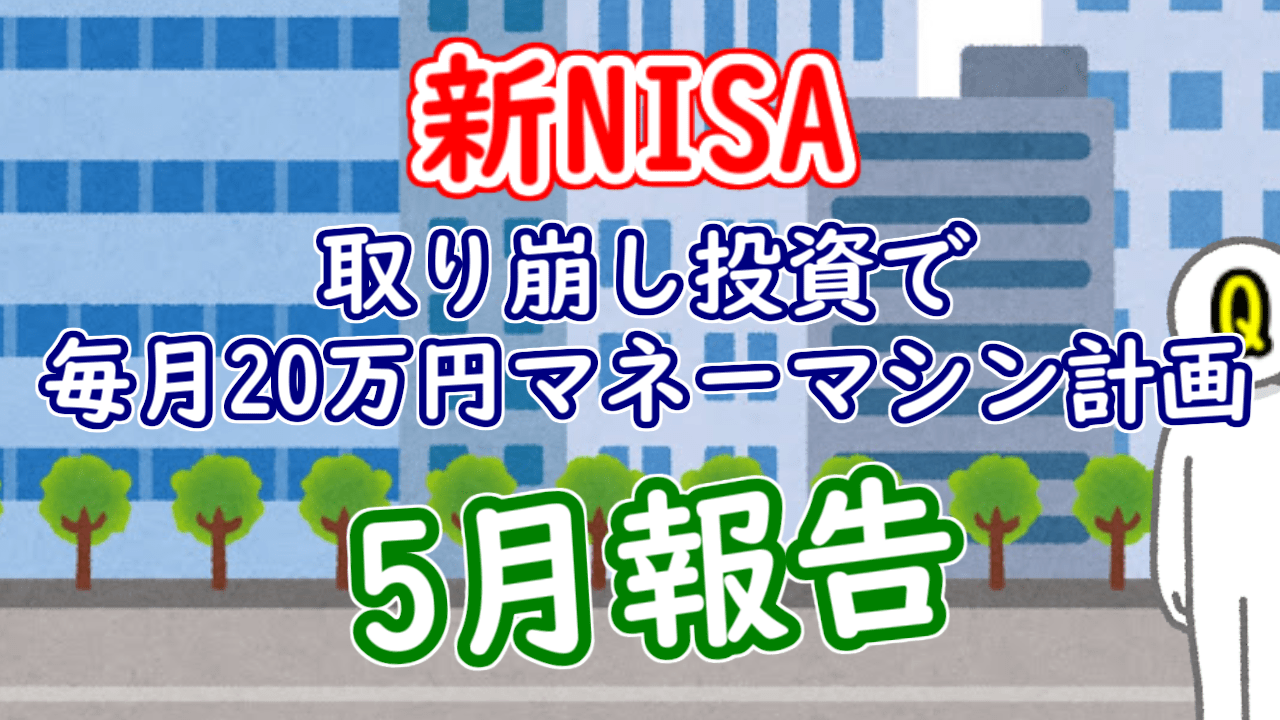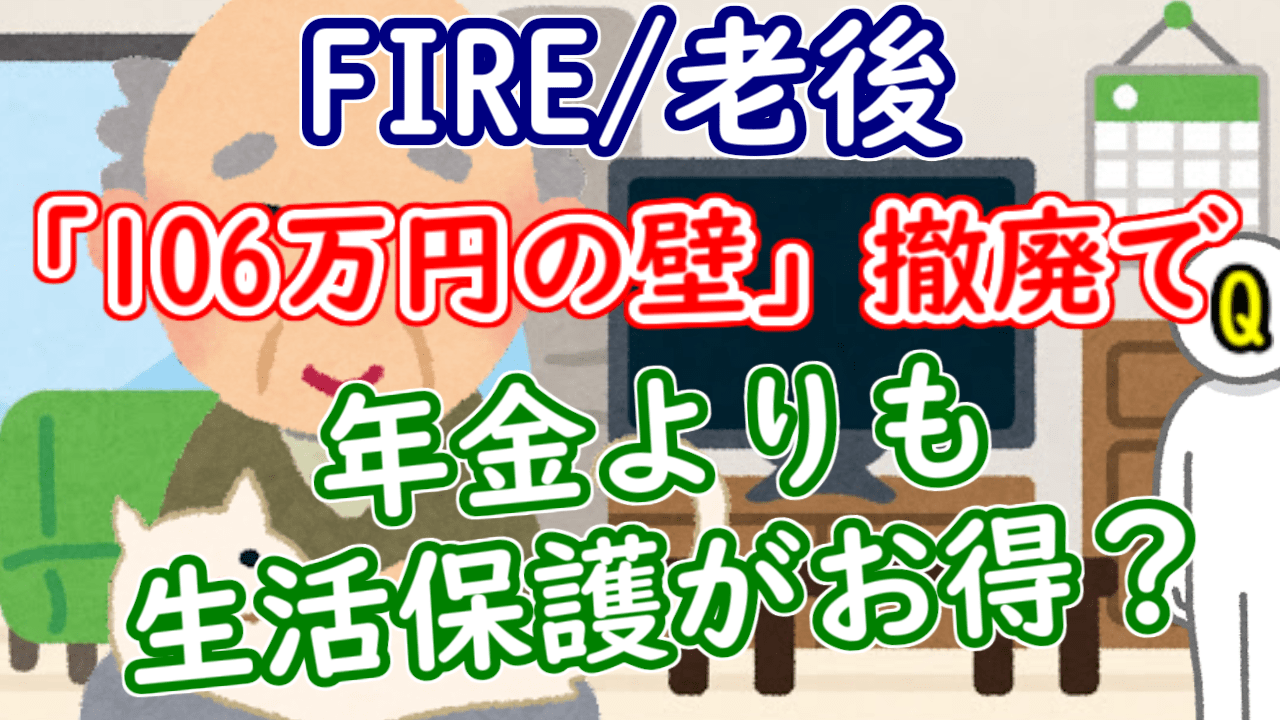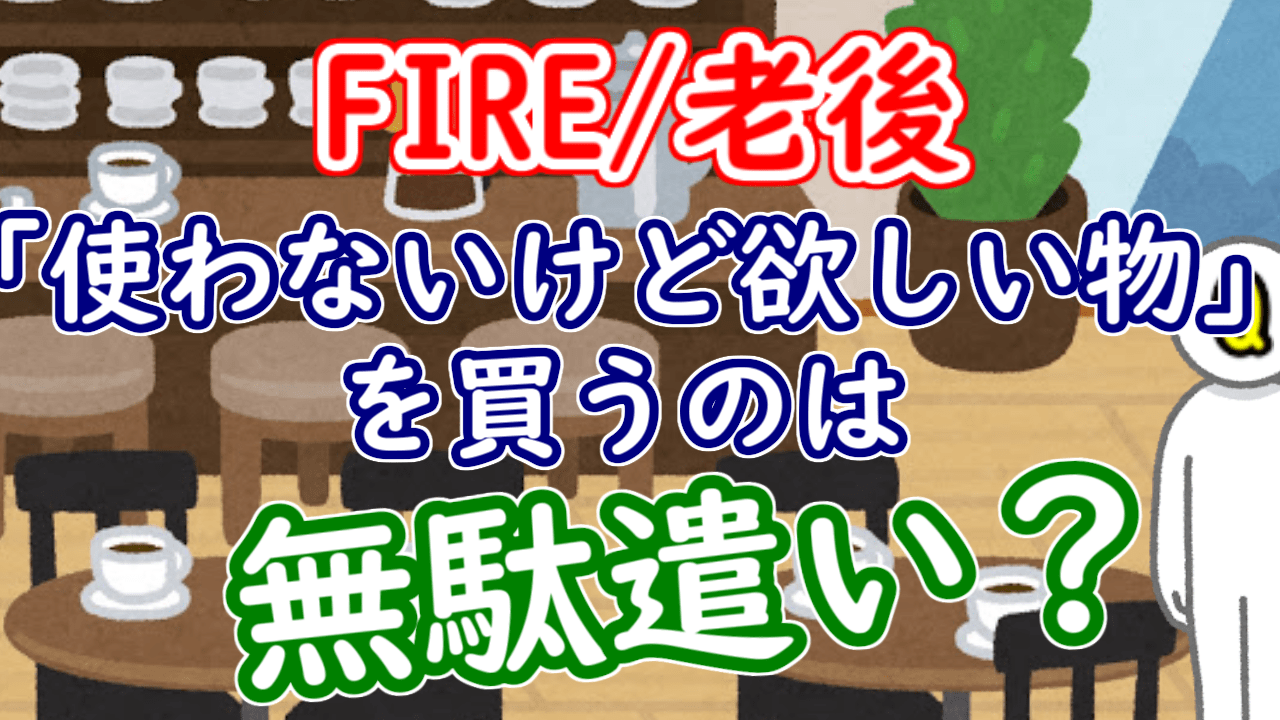
新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は、使わないけど欲しいものを買う事は無駄遣いかどうかについてです。
本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから。
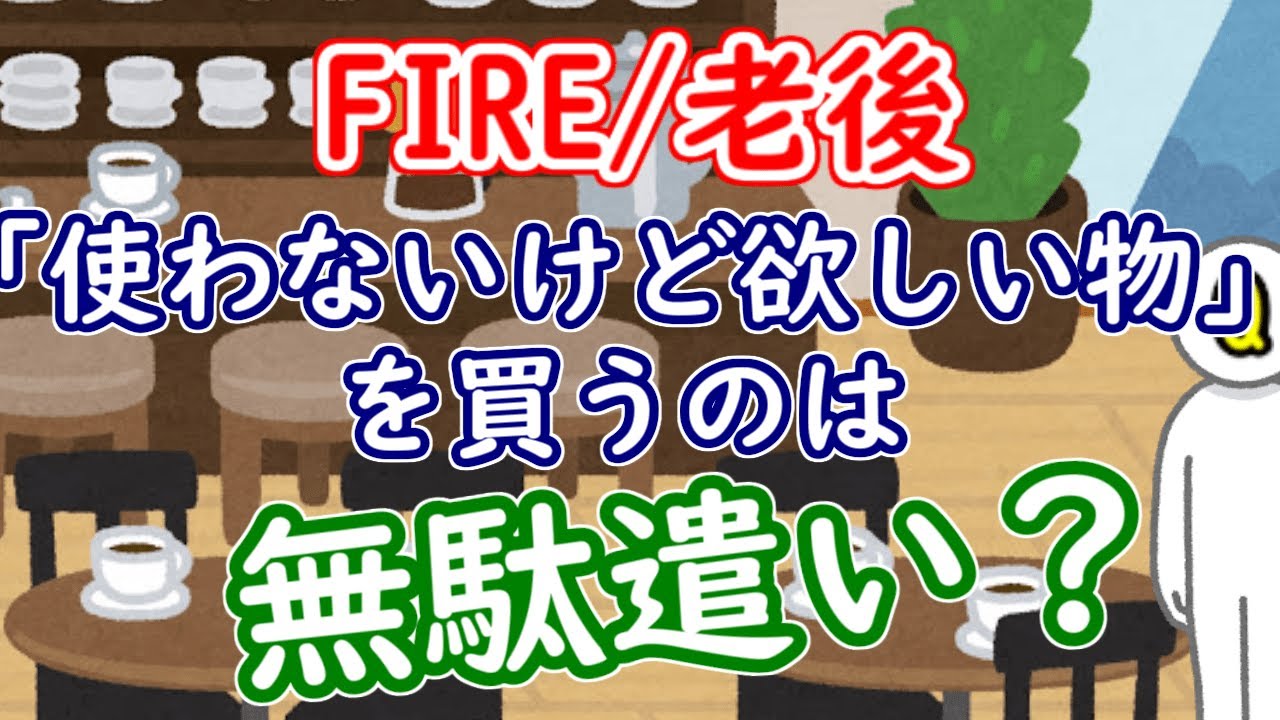
使わないけど欲しい物は無駄遣いじゃない?
こんなご質問をいただきました。
「節約関連の動画を拝見させて頂いています。
「買っても使わないと無駄になるから、定価でいいから使う直前だけ買った方が結果的に無駄遣いが減る。セールで安いからといって物を買わない」との事ですが、私もこれを実践していてセールだから物を買ったりということはしません。欲しい時は値段を気にせずに定価で買います。
しかし「使うか使わないか」という点に関しては疑問があります。つまり「必要性」で物を買う事ですね。
例えば食品や生活必需品は、生きていくためには「必要」なので必ず買わなくてはなりません。食品を買い過ぎて冷蔵庫をパンパンにして、何があるのかも覚えてなくて賞味期限が来て腐らせてしまうのは論外ですが、これらはどうしても買わなければいけないものになります。
しかし「人はパンのみに生きるのではあらず」と言うように、必ずしも必要ではないけれど自分にとっては「重要」というものがあります。
例えば芸術品などは使うことはできませんが、精神を潤してくれるので、必要ではないけれど重要という事になります。
ゲームも、遊ばなくても持っているだけで満足という人もいるでしょう。つまりこれは「必要」ではなくて、芸術品と同じような精神的に重要ということにもなります。この辺りどうお考えなのか聞かせてください。」
とのことです。
以前の動画も言いましたが、まず買い物の前提条件として「自分の価値観に本当にあっているのか」という部分があります。というのも、現代社会は頭のいい人たちが考えた広告が巧妙になりすぎていて、自分が本当に求めているものと、外部によって作られた欲望の区別がつかなくなっているレベルになっています。
以前言った『モンスターハンター』というゲームの話ですが、世間では流行っていますが、Q太郎は努力して何度も遊んでみましたが、どうやっても面白いと思えないわけです。これは明らかにQ太郎の価値観に合わないわけです。ここでいう価値観というのは、「モンハンが苦手」というゲームそのものへのピンポイントな話ではなく、「3Dアクションが苦手」という自分の性格を抽象化した話になります。つまり他の「3Dアクションゲーム」も自分の価値観に合わないわけで、遊んでも楽しめないわけです。『ダークソウル』みたいなのも世間で流行っていますが楽しめませんね。
これらのゲームを遊ぶことはあきらめました。あきらめるとは、仏教的には「明らかにする」という意味ですね。楽しめないということを明らかにしたわけです。
ここでQ太郎がモンハンをプレイしようとした動機としては、やはり「外部によって作られた欲望」なわけです。なんか世間で流行っているからとかで遊んでみて、世間で流行っているからきっと面白いものなんだろうと努力してプレイしていたわけです。
案外自分の好みというのは自分ではわからないもので、抽象化作業というのがやはり必要になっていきます。どういう部分が駄目なのか、どういう系統が楽しめないのかなど、自分自身を掘り下げて理解していく必要があります。ちょっと遊んですぐ飽きてしまうゲームなど、理由をちゃんと突き詰めないと、また同じことを繰り返してしまうのですね。
これは自分の価値観に合わないものを「作られた欲望」によって買わされている状態なので、無駄遣いということになります。最初のうちは合うか合わないかはわからないので、ある程度の失敗のための投資は必要なのですが、さすがに同じことを繰り返すのはどうなのかと思います。
ドラクエとかファイナルファンタジーとかの人気ゲームも実際にクリアできている人は3割にも満たない状況ですし、つくられた欲望で買ってけっきょく遊ばないという人がほとんどということになります。普段本読まないのに、ノーベル文学賞で大江健三郎の本を買うのとおなじようなものです。ほとんどの人は読んでません。価値観があっていないのに、つくられた欲望で、自分の欲望だと思ってしまって買ってしまっているのですね。
最近思う事の一つとして、パラドックス社の歴史ゲームというのがあります。『Hearts of Iron 4』とか『Victoria3』とかですね。
Youtubeでこれらのゲームの動画は人気なのですが、動画を観た影響で実際に買ってプレイして、「難しすぎて意味が分からん」と投げ出している人がほとんどなんじゃないかとは思います。
この時点で「自分はプレイすることよりも、動画を観ることのほうが楽しい」ということに気づければ、今後は動画だけを見て、ゲーム自体は買わないことで無駄遣いを減らせるわけです。プレイすること自体は自分の価値観に合っていないのであきらめるわけです。あきらめるとは、さっきもいったように自分自身のことを明らかにしたわけです。
逆にここで抵抗して、「なにがなんでも遊んでやる」となって、お金と人生の時間を無駄遣いすることになるのは、あきらめるとは逆の執着でしかありません。明らかにした時点でぱっと手放せることは、今後の人生を生きやすくするとは思います。
それで芸術品ですが、これは判断がかなり難しいです。多くの人が欲しがるのは、いわゆる「世間で有名な作品」です。つくられた欲望である可能性が高いのですね。
ルーブル美術館に毎年世界からたくさんの観光客が来ますが、あの中で作品を実際に楽しめている人がどれだけいるのかかなり疑問です。作品の背景とか歴史とかを理解している人がそんなにいるとも思えませんし、ほとんどが「有名な作品だから」とか「観光地だから」とかいう理由で記号を楽しんでいるだけで、そのもの自体を楽しんでいるわけではないのです。
世界三大幸福論の一つであるアランの『幸福論』では観光について、「旅行者は名所を見て回るが、そこに生きているものは見逃してしまう。真の旅人は、どこにいようと、自分の目で世界を見ることができる」と述べています。理解もしていないものを急ぎ足で見ても幸福にはつながらず、そのもの自体を理解して観るのであればどこにいても楽しめるということです。
これを抽象化すると、外的な体験があっても、自分の内側でそれを楽しめる能力がないと幸福にはつながらないわけです。どんなにすばらしい外的な体験があっても、だらだらテレビを見るように受け身で見て、右から左へ流しているだけでは「退屈」を感じてしまうわけです。
そんなわけで芸術品も自分の内側の価値観に合っていて、理解して、実際に楽しめているのであればいいのですが、いわゆる「外部によってつくられた欲望」によって、たんに記号を消費しているだけなのであれば、それは無駄遣いになります。ここの見極めが重要になってきます。
ゲームも、遊ばないけどパッケージが好きとかで集めていて、それが自分の価値観に合っていれば無駄遣いにはなりません。ただ自分の内部にそれを楽しむ能力がないのに、外部によってつくられた欲望によって、自分が望んでいるものだと勘違いさせられて、買ったはいいけどけっきょく全然楽しめてないみたいなことは往々にしてよくあります。
野球が得意じゃないのにひたすら野球の練習をさせられるようなものです。自分が何が好きで何が苦手かなど、価値観を見極めていく必要があるでしょう。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・現代社会は「外部によってつくられた欲望」が巧妙になっており、自分の本来の価値観とミスマッチを起こしやすい。
・自分の価値観に合っていないものを買うのは無駄遣い。
・自分の価値観を見極めて、楽しめないものを抽象化し、すっぱりあきらめる(あきらかにする)ことが時間とお金の無駄遣いを防ぎ、幸福感を上げることになる(自分が本当に楽しめることに時間とお金を割くことができますしね)
・合わないのに「何が何でも楽しんでやる」と抵抗すると執着を生み、不幸になっていく。
・外的なすばらしい体験があっても、自分の内側でそれを楽しめる能力がないと幸福にはつながらない。(野球が得意じゃないのにひたすら野球の練習をさせられるようなものですね)。
・自分が何が好きで何が苦手かなど、価値観を抽象化して見極めていく必要がある。
となります。
そんなわけで、ゲームは遊ばないけどパッケージが好きでゲームを買うのは、自分の価値観に合った買い物なのでOKですが、たんに世間で流行っているからで買って全然遊んでないとかは、自分の価値観とのミスマッチが起こっているので無駄遣いといえます。
見極めができれば、これまで執着していたものはすっぱりあきらめるというのは、人生を手軽にしていくためにも必要でしょう。ゲームも遊ぶより動画を観ることのほうが楽しいのだったら、ゲームを買う事や遊ぶことをすっぱりあきらめれば、お金も時間も浮いて動画を楽しむ時間が増えることにもなります。
アランの有名な言葉に「人は幸福だから笑うのではない。笑うから幸福なのだ」というのがありますが、これは抽象化して考えれば、「外部の状況(お金、健康、環境)が幸福をつくるのではなく、自分の「態度」や「意志」という内部の状況が幸福を生み出す」ということになります。
買い物をするにしても、外部の状況ではなく、自分の内部の価値観に沿ったものであるのかどうかをよくよく見極めたほうがいいでしょう。