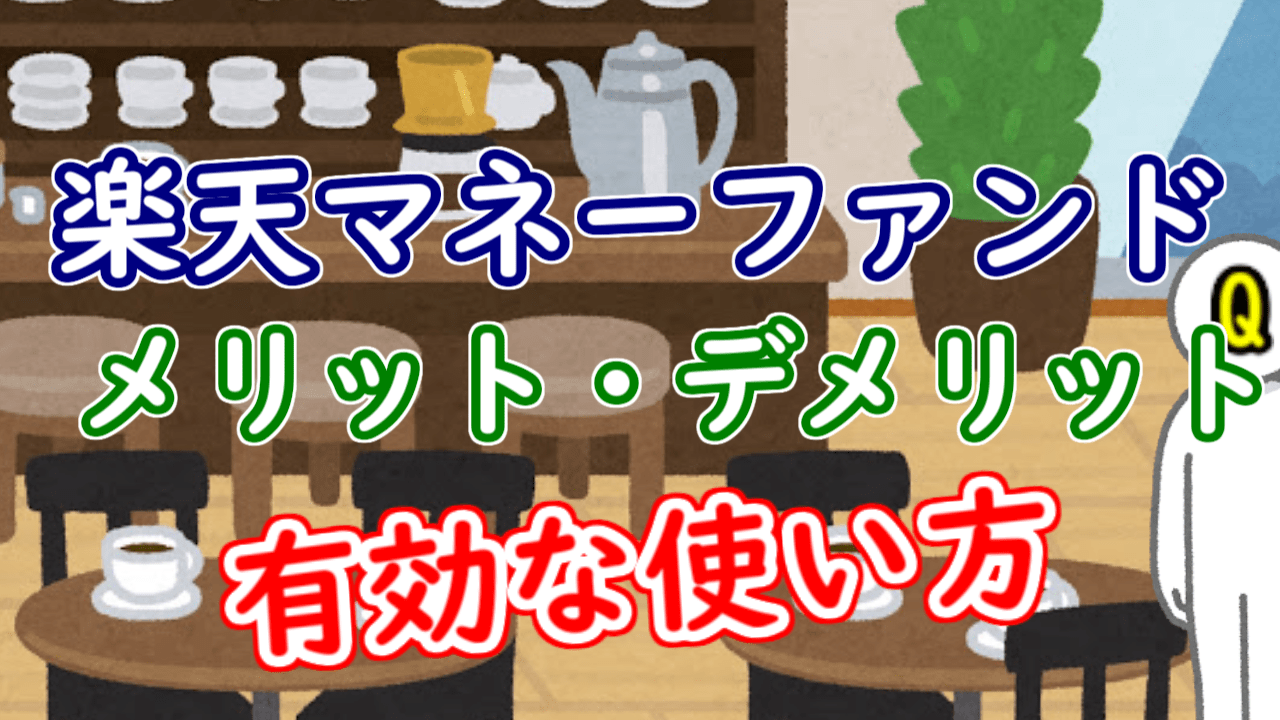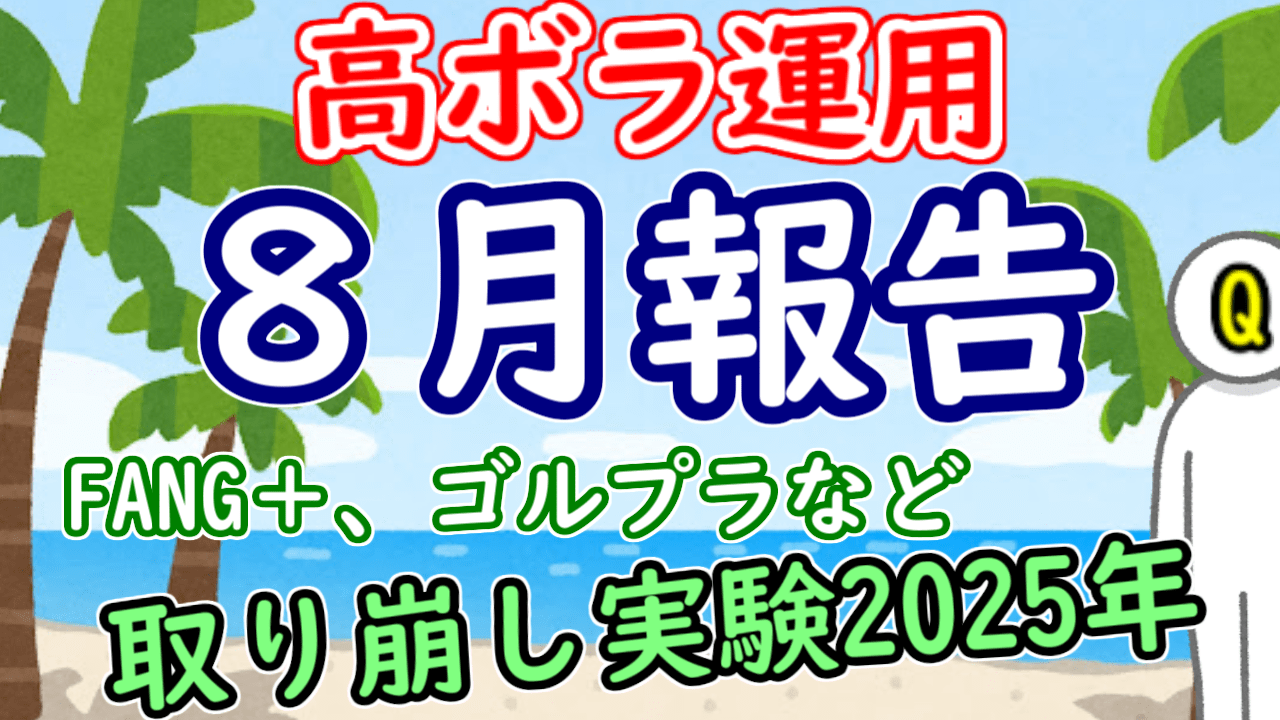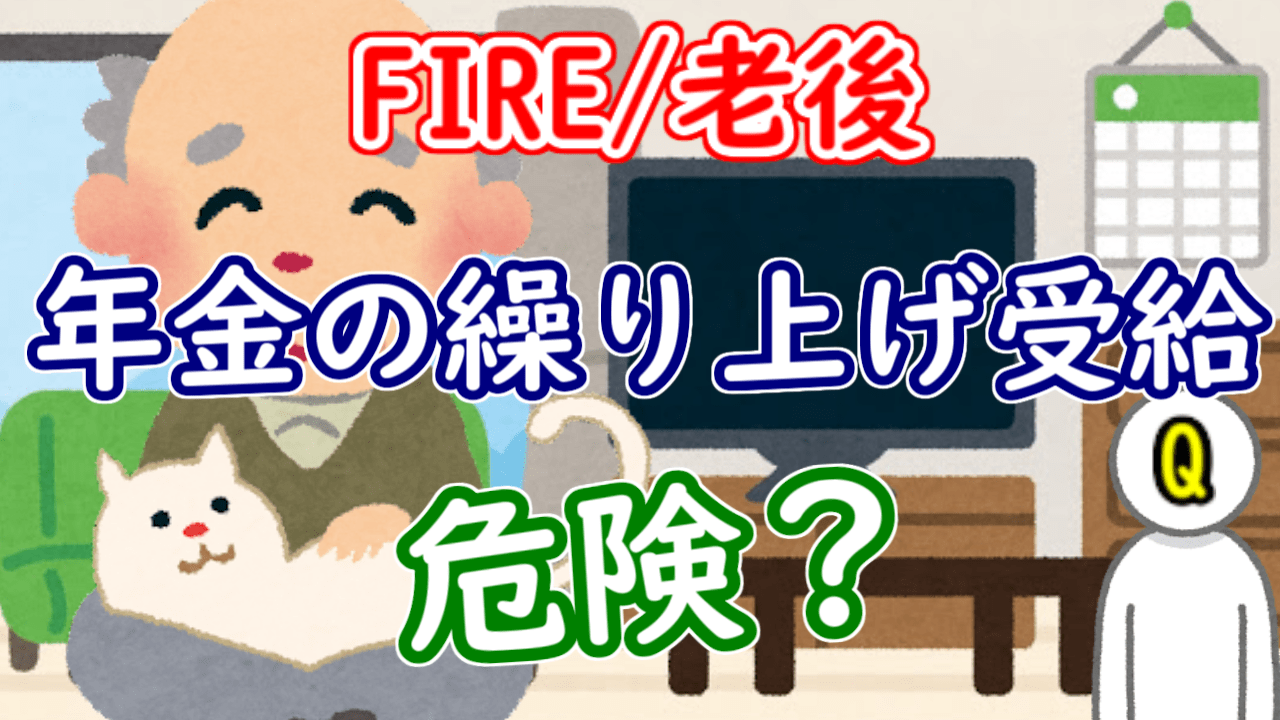
新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は年金の繰り上げ受給が危険かどうかについてです。
本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから。
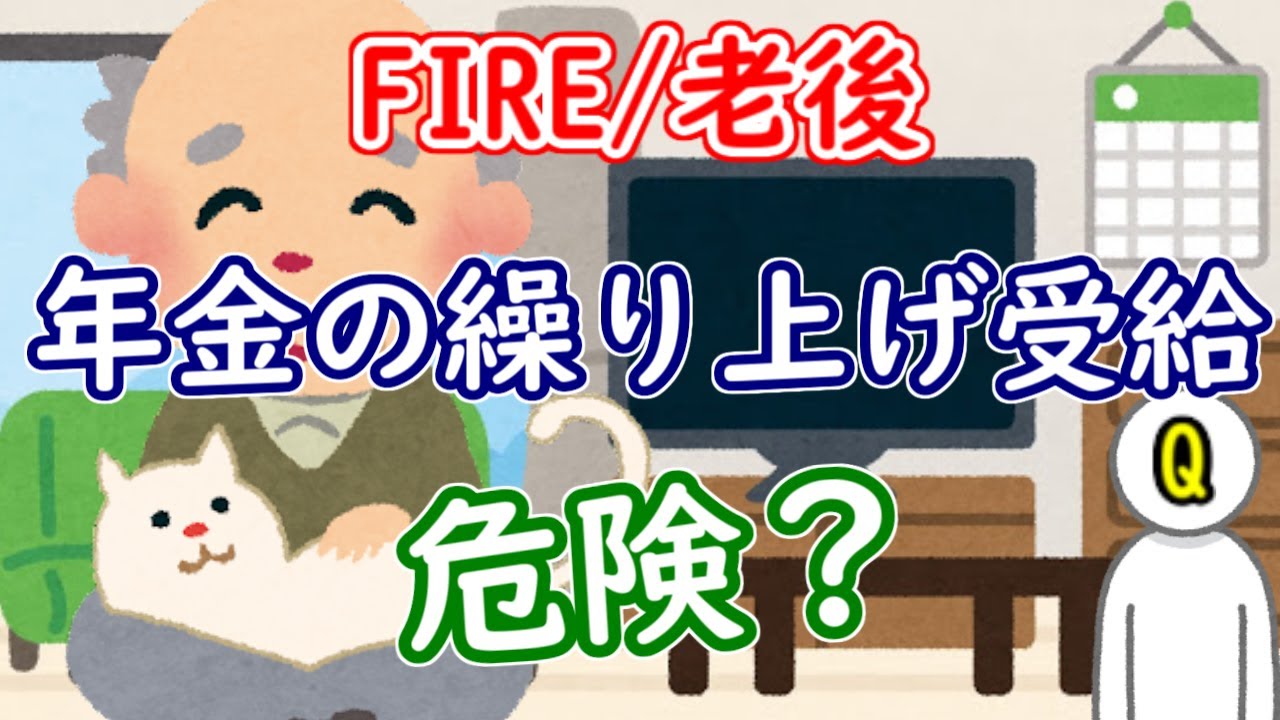
年金の繰り上げ受給は危険?
こんなご質問をいただきました。
「年金の繰り上げ受給について質問があります。
以前の動画で、インフレなどを加味すると繰り上げの方が良いという話でしたが、デメリットとして障碍者年金が受け取れないというのがあります。
障碍者年金は老齢年金との併用ができないので、65歳受け取りの場合でも、どのみち65歳以降は障碍者年金が受け取れません。そのため、このデメリットについてはそれほど大きなものではないとは思います。あくまで60~65歳までの5年間に限定した話で、それ以降は結局障碍者年金は受け取れません。
ただ長生きリスクの面では、60歳繰り上げでインフレを加味しない損益分岐点が81歳あたりなので、それ以上の長生きをした場合のリスクが気になります。
繰り上げ受給に今一つ踏み切れないのですが、どう考えればいいのでしょうか?」
とのことです。
年金受給開始年齢については、人それぞれいろいろな考え方があるとは思います。
繰り下げ受給の場合
それで繰り上げするかどうかですが、大きく分ければ年金を投資商品として見ているのか、保険商品として見ているのかでも変わってきます。
それで質問者様は長生きリスクを気にしているので、考え方的には保険商品として見ているのだとは思います。
たとえば死亡保険は亡くなったリスクに備えるためにお金を払っているのと同じように、年金は保険として考えれば長生きに備えるためにお金を払っていると言えます。
この場合は儲かるか儲からないかは考える必要がなくて、そのときが来るまで保険料を払い続ければいいのですね。
死亡保険はその日が来るまで保険料を払い続ければいいのと同じように、年金も長生きというリスクに備えたいのであれば、そのときが来るまで保険料を払い続ければいいわけです。
ここでいう支払わないといけない保険料というのは、65歳以降の場合は年金の繰り下げになりますね。つまり65歳でまだ生きていた場合は、さらに繰り下げていくという話になります。損得ではなく、あくまで長生きリスクに備えるという意味での、保険料代わりの繰り下げになります。
現在の制度だと75歳まで繰り下げることができますので、長生きリスクに備えたいという話なら、限界まで繰り下げるのが正解という話になります。あくまで損得ではなく、保険という面からの最適解ですね。
「75歳になる前に亡くなったらどうすんねん」という話ですが、それはそれでいいんじゃないでしょうか?
たとえば死亡保険は死亡に備えて払っていますが、実際のところは死亡したくないわけで、できるだけ長く保険料を払っていられる状態、つまり損している状態というのがその人にとってはよい状態ということになるのですね。元気に生きているわけなのですから、それはそれでいいわけです。
長生きリスクだと考え方が逆になります。長生きすることをリスクだと考えている以上、75歳までに亡くなったら、それはそれでいいじゃないでしょうか。さっきの「長生きしてよかったね」の逆で「長生きしなくてよかったね」という話なのですしね。あくまで損得の話でなくて、リスクに対する考え方の話です。そのためリスクが発生しないことが、その人にとってよい状態ということにもなります。
そのため、本気で長生きリスクを気にするのであれば、限界まで繰り下げて75歳受け取りにするのがいいとは思います。75歳以降も生きていた場合、長生きリスクが発生していることになるので、繰り下げをしたことでリスクに備えられたという話にもなります。何度もいいますが、あくまで損得の問題ではなく、リスクに備えられたかどうかという話です。
繰り下げ受給の場合、一か月につき0.7%が加算され、最大で84%が加算されます。一か月の年金が10万円の人だったら、18.4万円ということですね。
実際は金額が上がると税金とかで引かれてしまいますが、なんにしろ長生きリスクに限界まで備えたことにはなりますので、目的自体は果たされているわけです。75歳までどうやって生きていくかは、働くなり資産を取り崩すなりで何とかするしかないでしょう。ただ保険という考え方、かつ長生きリスクに備えたいという話であれば、繰り下げが最適解ということにはなります。
ちなみに年金が基礎年金のみで、税金や社会保険料を加味した場合の65歳と75歳の損益分岐点は91歳あたりです。年金が増えたことで健康保険料や住民税、所得税が増えるのですね。
ただあくまで長生きリスクに備えるという話であれば、91歳以降にも備えるという話なので、やはり受給の最適解は75歳になります。損得の話ではなくて、長生きしたときにどうするかの話なのですね。
そんなわけで長生きリスクに備えたいのであれば、75歳まで繰り下げるのがいいでしょう。仮に75歳前で亡くなったら、長生きリスクが発生しなかったのですから、それはそれでよかったのではないでしょうか。死亡保険と逆の考え方です。保険の考え方だとこうなりますね。実際によかったのかどうかはともかく、保険の考え方だとよかったことになりますね。保険は利用せずに済むのがベストですしね。
繰り上げ受給の場合
一方、繰り上げ受給の場合は、こちらは保険では無くて損得の話になります。損益分岐点を考えますので、これは投資的な考え方と言えます。
60歳と65歳での損益分岐点ですが、税金を考慮しなければだいたい81歳ぐらいになります。
これは日本人男性の平均寿命が約81歳なので、このあたりまでは速く受け取ろうとおなじにしておくという考え方ですね。
寿命の場合、資産と違って二極化しているわけではなく、中央値と平均値がだいたいおなじぐらいなので、言い方を変えると81歳までに半分の人が亡くなっているということにもなります。そのため、年金が破綻しないというのは、現役世代から奪い取る収入と、高齢者への年金支出が平均寿命あたりでだいたいトントンになるように調整すればいいだけなのですね。
ただやはり人口減少で現役世代が減っている以上、この調整方法だと年金がもらえないということはないのですが、受給年齢がどんどん上がって、金額自体はどんどん減っていくということになりかねません。あくまで現役世代から奪い取っている分を高齢世代で分けるという話なので、調整するとすれば受給年齢上げるか額減らすかしかありませんしね。
このあたりを何とかするというかごまかすために、多くの人に厚生年金に加入してもらって、それを基礎年金(国民年金)に横流しするという方法をとるというある意味合理的なことをやっています。
そんなわけで、年金が崩壊することはないと思いますが、調整によって受給年齢が上がったり、受給額が少なくなったりは普通にあるとは思います。そもそも現役世代が減りますしね。
そんなわけで損得の話だと、受け取れるうちに受け取るのが正解になってしまいます。そもそもいつ死ぬのかわかりませんので、損得の話だと最適解は受け取れるときに受け取るになりますね。
もし60歳以降も働いて、年金無くても生活できるという話でしたらという話でしたら、税金とか減額とかの問題もあるので無理に繰り上げる必要もないとは思います。
このあたりは年金をどう考えるかの問題になりますね。
あと国民年金しかないという方は、年金生活者支援給付金というのがもらえます。年間789,300円以下であれば、毎月5,450円 もらえるのですね。年間で65,400円になります。
ただし年間789,300円を超えるとどんどん減額されていって、887,700円を超えると0円になります。それとこれを受け取れるのは65歳以降になります。
たとえば国民年金満額の場合、65歳満額受給だと831,700円になります。これで計算すると、支援給付金は年36624円になるのですね。
そのため満額払っている人は、繰り上げ受給で年間789,300円以下ぎりぎりに近づけるように調整することで、損益分岐点を上げるということができます。
計算したのを並べると、支援給付金を加味した国民年金(満額)のみの損益分岐点は、
60歳 79歳
61歳 81歳
62歳 89歳☆
63歳 92歳
64歳 93歳(給付金減)
となります。平均寿命で考えたら61~62歳で受け取ればいいということになります。62歳から急激に損益分岐点が上がるので、62歳繰り上げがお得感があっていいかもしれません。
64歳だと年金額が年間789,300円を超えるので、支援給付金が6.5万円から4.7万円ほどに下がってしまうので63歳と損益分岐点で大きな差がつかないのですね。
まあ、多くの人は厚生年金が付きますので税金も増えたりで計算がややこしくなりますが、国民年金のみだと最適解と言えそうなのが90歳前後が損益分岐点になる62~63歳あたりなら、保険の役割もある程度果たしてくれるとは思います。
そんなわけで自営業や個人事業主で国民年金のみならこういう最適解もありますので、こういうのも合わせて考慮すればいいとは思います。
あと年金を低く抑えることのメリットとしては、生活保護が受けやすくなるということがあります。
中途半端に年金を受け取ると生活保護も取れないうえに、医療費自腹とかいう地獄が待っていたりしますので、このあたりも考えて調整しておいたほうがいいでしょう。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・年金を投資商品として見るか、保険商品として見るかで考え方は変わる。
・保険商品として見る場合、リスクが発生しないことがその人の人生にとって良い事になる。(死亡保険は死亡せずに保険料を払い続けていることがその人の人生にとってよいことになります)。
・保険として考えれば、年金は逆に長生きリスクに備えるための保険なので、限界まで繰り下げるのが正解。途中で亡くなった場合、長生きリスクが発生しなかったということで、保険としては成功。(繰り下げ中は働くなりなんなりして何とかすればいいでしょう)。
・投資商品(損得)として考えるのであれば、受け取れるときに受け取るのがいいかと。
・国民年金のみの場合は年間789,300円以下で年65,400円の支援給付金がもらえる。789,300円を超えて887,700円に近づくにつれて額は減っていき、887,700円を超えると0円になる。
・支援給付金を加味した国民年金(満額)のみの損益分岐点は、
60歳 79歳
61歳 81歳
62歳 89歳☆
63歳 92歳
64歳 93歳(給付金減)
となり、平均寿命で考えれば61~63歳で受け取るのがいいかと。まあ、62~63歳受け取りなら損益分岐点は90歳前後なので、長生きしてもそんなに損はしませんしね。
・厚生年金もある場合は税金の問題もあって、損益分岐点は複雑になる。
・年金を抑えるメリットとしては、生活保護が取りやすくなる。中途半端に年金を受け取ると、生活保護が受けれない上に医療費自己負担という地獄が待っている場合も。
となります。
そんなわけで国民年金のみであれば最適解というものは存在しますが、厚生年金があるとちょっとややこしい話になってきます。
なんにしろ、保険として考えるのであれば、長生きリスクに備えて限界まで繰り下げて、けっきょく年金を受け取る前に亡くなったのであれば、それはそれで長生きリスクが発生しなくてよかったという話なので、保険としては成功しているのではないでしょうか。
そんなわけで長生きリスクの怖い人は限界まで繰り下げればいいとは思います。これは損得の問題ではないですしね。