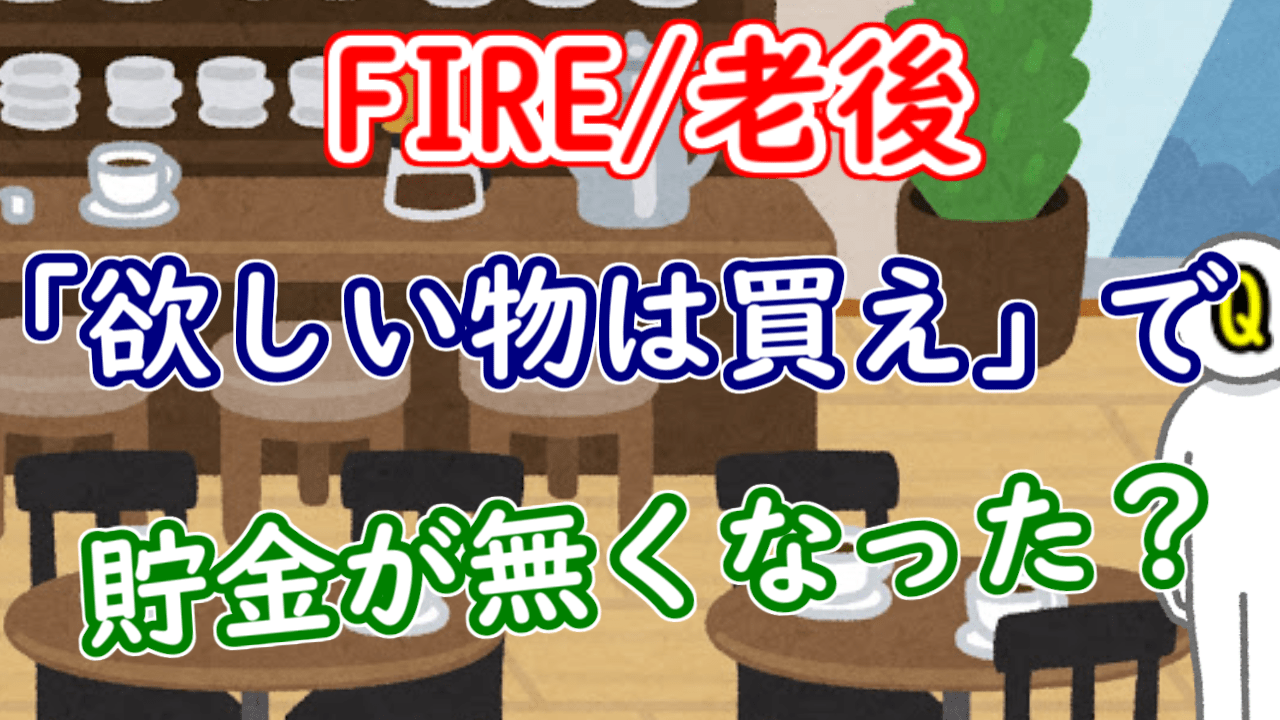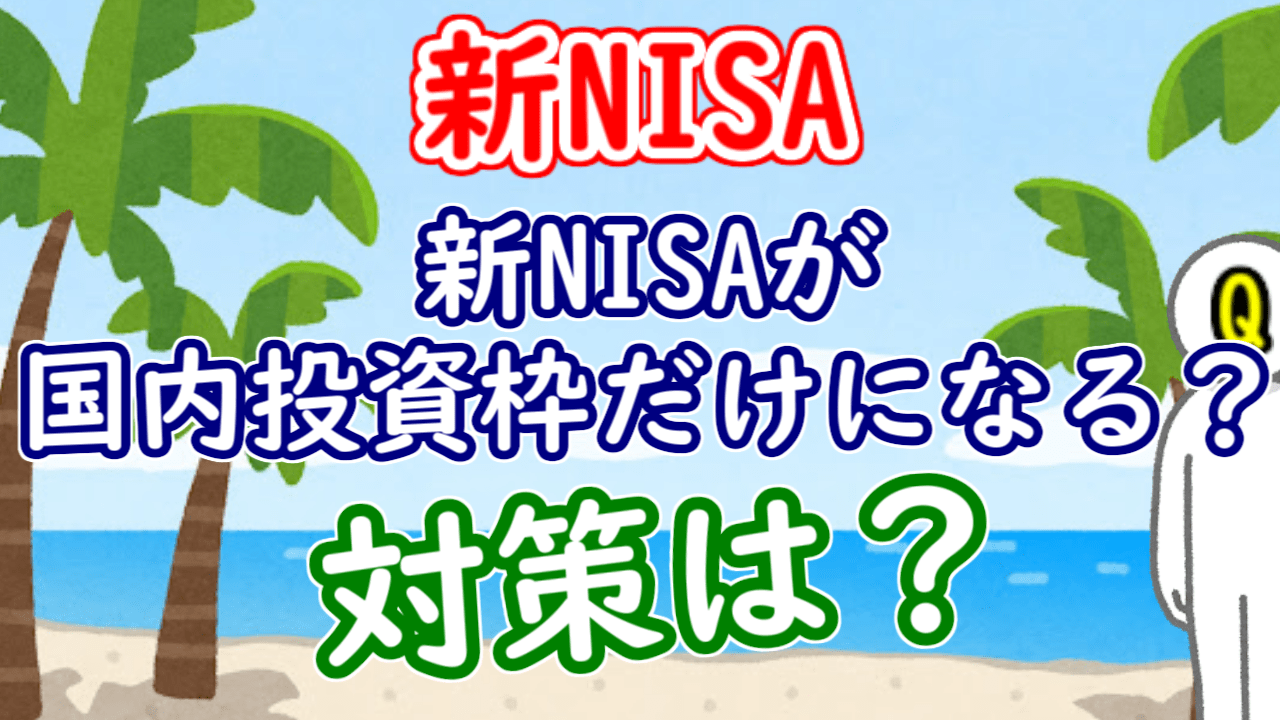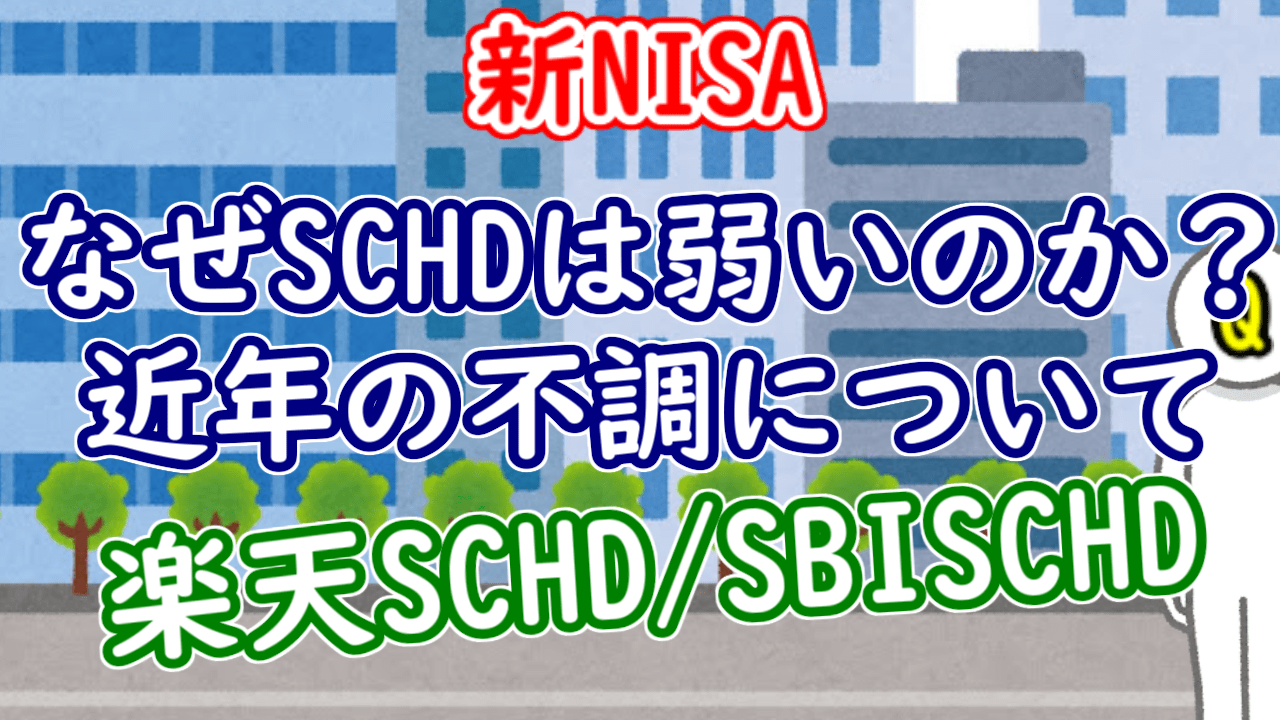
新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は最近SCHDが弱い件についてです。
本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから。
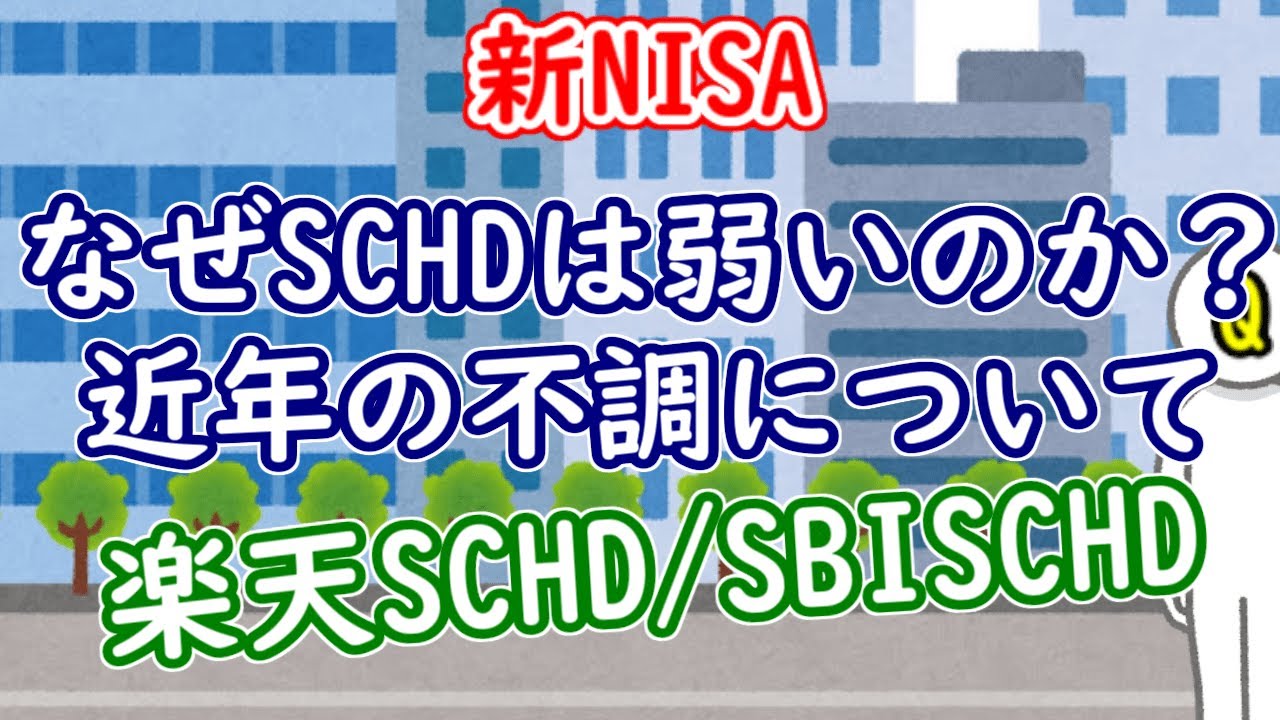
なぜSCHDは弱いのか?
取り崩し投資報告でも使っている楽天SCHDとSBIのSCHDですが、パフォーマンスが全然振るわないという結果になっています。
鳴り物入りで登場したわりにはなんか微妙な感じで、S&P500やNasdaqが今年に過去最高値を更新しているにもかかわらず、楽天SCHDもSBISCHDも、発売以来一度もプラテンしたことがないというていたらくです。今回はそのことについてです。
SCHDが注目されたのは、過去にS&P500よりも高パフォーマンスで低リスクという実績があったからです。
ところが楽天SCHDやSBISCHDの発売以降、とくに今年に入ってからのパフォーマンスはあまりよろしくありません。S&P500やNASDAQがしっかり上昇している環境下で、楽天SCHDやSBISCHDが落ち込んでいるという状況です。
ただこれは楽天証券やSBI証券が、日本が世界に誇る伝統芸能である「NAKANUKI(中抜き)」を発動させた結果、パフォーマンスが悪くなっているわけではなく、元となるETFのSCHDもドルベースでパフォーマンスがよくないという結果になっています。

実際にドルベースの年初来からのチャートを見てみますと、青がSCHDで黄色がS&P500ですが、あきらかにS&P500にかなり劣後しているのがわかります。かなりというか、現時点でS&P500は+14.4%なのに対して、SCHDはマイナスになっていますね。
SCHDの特徴としてディフェンシブの強さがありますが、今年の3月~5月にその強さがちょっと発揮されていましたが、そのあとの上昇力がなく、そこからS&P500にパフォーマンスが引き離されていった形になっています。
それでこれまでなんでSCHDが強かったかといえば、この下落耐性の強さがこれまでの相場にマッチしていたというのがあります。

チャートの期間を5年に延ばして観て見ると、2020年から2023年半ばまでのコロナ禍の状況ではS&P500のパフォーマンスを凌駕していました。これは下落トレンド中ということもあり、SCHDの得意分野であるディフェンシブ能力が働いていたということもあります。
ところが2024年、ようは昨年の大きな上昇トレンドになると、SCHDはその上昇についていけず、S&P500に大きく劣後することになります。下落耐性は強いけど、上昇力が弱いということですね。
このこと自体は、SCHDを発行している企業のファンド説明資料にも書かれいます。SCHDは評価倍率(P/E 等)や成長期待が低めの銘柄で構成されている、つまり「割安/安定」型の特性が強い銘柄で構成されているため、成長バブル的な相場では不利になりやすいということが記載されています。そのため、このこと自体はファンドの方針に沿った動きになっているわけです。
SCHD は配当株・高配当株を主に対象としたETFであり、ハイテク・成長株(特に AI・大手テック等)のウェイトが低めに設定されています。これに対して、昨年以降からの大きな上昇では、AI関連を中心にしたハイテク・グロース株が牽引していてそれについていけないという話ですね。
さらにいえば、SCHDの上位銘柄の売上・利益成長率が、S&P 500上位企業と比べてかなり低いという形になっているため、昨年のような上昇相場になるとS&P500に大きく劣後する形になります。
高配当系というのは、ようするにセクター的には「成熟産業」や「景気敏感・配当株」の割合が高くなります。
市場全体が上昇しているときというのは、企業の「成長」に価値を置いている局面なので、こういった配当重視・成熟企業は投資家の評価が抑えられがちです。
配当を重視する設計が、逆に「成長期待」という場面では弱みになってしまうわけです。これはSCHDだけでなく、高配当系全般の問題になっていますね。
そういう成熟企業で組んだファンドだと、AIとかの現在の市場の流行とかみ合わない場合が多いので、上昇局面で置いていかれるというのも当たり前といえば当たり前といったところでしょう。
かといって、SCHDがだめかといえば、ここは考え方の問題でして、上昇トレンド時でもS&P500を超えた高パフォーマンスを期待するのであれば厳しいものはありますが、「安定配当・インカム重視」「市場の暴落に備えた守備的なポジション」という観点での長期保有ならばいいんじゃないかとは思います。どこにポジションをとるかですね。
ようするに「配当を得ながらゆったり保有」するのか、「成長株でガンガン上げを取る」かの、どの視点で投資しているのかによるとは思います。

もう一度先ほどの5年チャートを見てみますと、S&P500の下落期間は結構安定したチャートなのですね。全体で見てみても、S&P500のように急激に上がることはありませんが、ゆっくりと上昇する形にはなっています。
ただそのぶん、落ち込んだあとの回復が遅いという問題もあり、このあたりも一長一短といったところですね。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・近年のSCHDはS&P500に大きく劣後する。(楽天SCHDやSBISCHDが中抜きしているわけではありません)。
・SCHDの銘柄は配当重視・成熟企業にウェイトが置かれているので、企業の「成長」に価値を置く上昇局面では後れをとってしまう(これが去年から今年にかけての動きになっていますね)。
・SCHDの上位銘柄の売上・利益成長率が、S&P 500上位企業と比べてかなり低い。割安・安定型の特性が強い銘柄で構成されているため、成長バブル的な相場では不利になりやすい。
・ただ2019年以降のS&P500不調時では下落耐性を発揮して安定したパフォーマンスを出していた。(差が出てきたの昨年の急上昇からですね)。
・ただ上昇力が弱いことから、一度大きく落ちるとS&P500に比べて回復は遅い。
・投資するかどうかは考え方の問題。上昇トレンド時でもS&P500を超えた高パフォーマンスを期待するのであれば厳しい。安定配当・インカム重視・守備的ポジションという観点での長期保有なら良いかと。
となります。
そんなわけで昨年から今年にかけての上昇局面ではS&P500に大きく劣後する形になりましたが、防御的なスタンスを取りたいのであれば一つの選択肢にもなるとは思います。
ただ上昇力が弱いため、ズドン後の回復が遅いことから買うのであれば一括より分割でちょこちょこ買う形の方がいいかなとは思います。もしくはズドンしたときに買うという高配当株系の買い方ですね。
ちなみに高配当ETFのSPYDも今年はあまり振るわない動きになっていて、チャート的にはSCHDとけっこう似た動きになっています。VYMとHDVのほうは今年は年初来でプラス5~6%ぐらい出ていますので、成長もとっていきたいとなるとVYMとかがバランス良いかなとは思います。
それと現在の取り崩し投資では、楽天SCHDが特定口座と新NISA口座に、SBISCHDがSBI証券の特定口座にありますが、ダブっている特定口座の楽天SCHDを処分してなにか別のものを来年の新NISAで使おうかなとは考えています。そんなわけで決まりましたらまた動画で報告します。