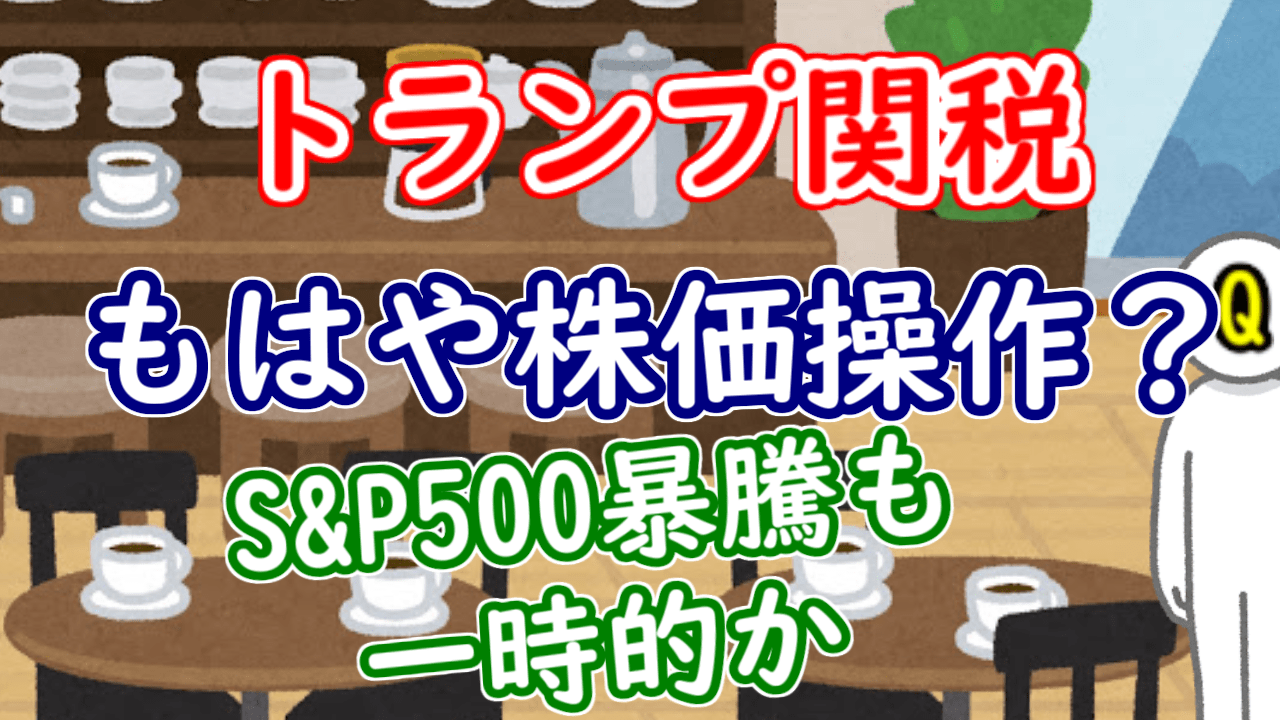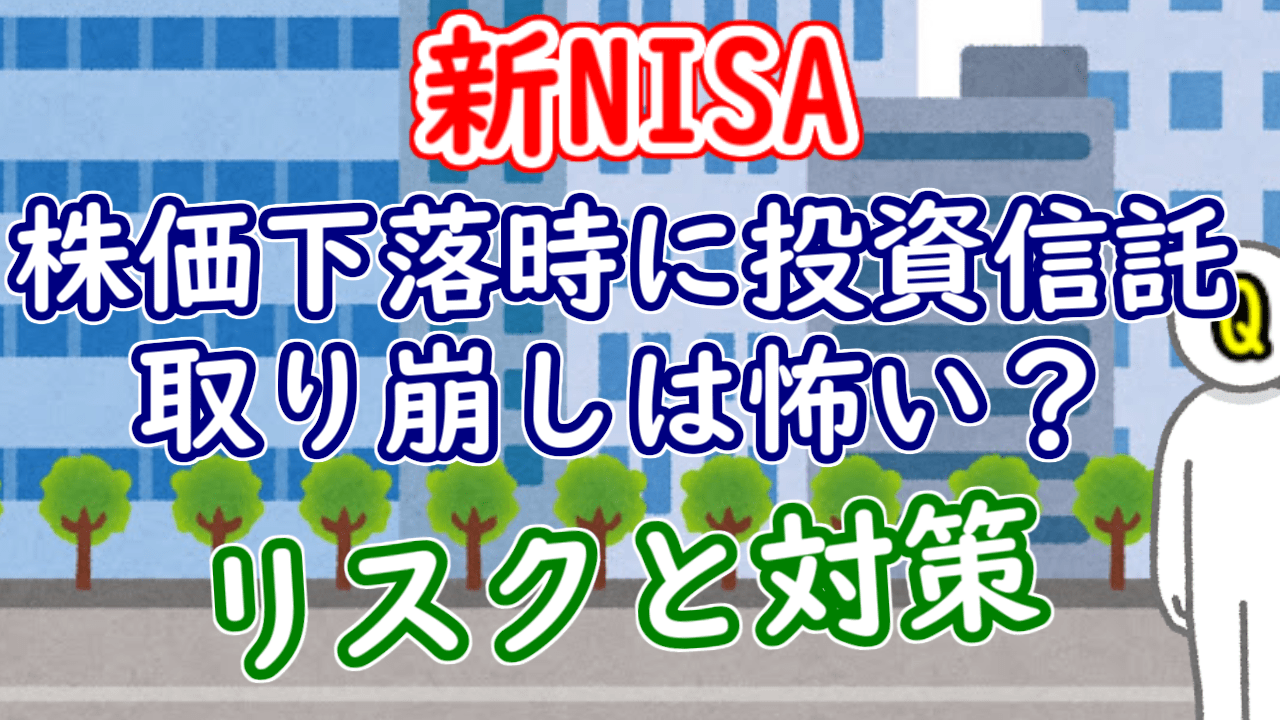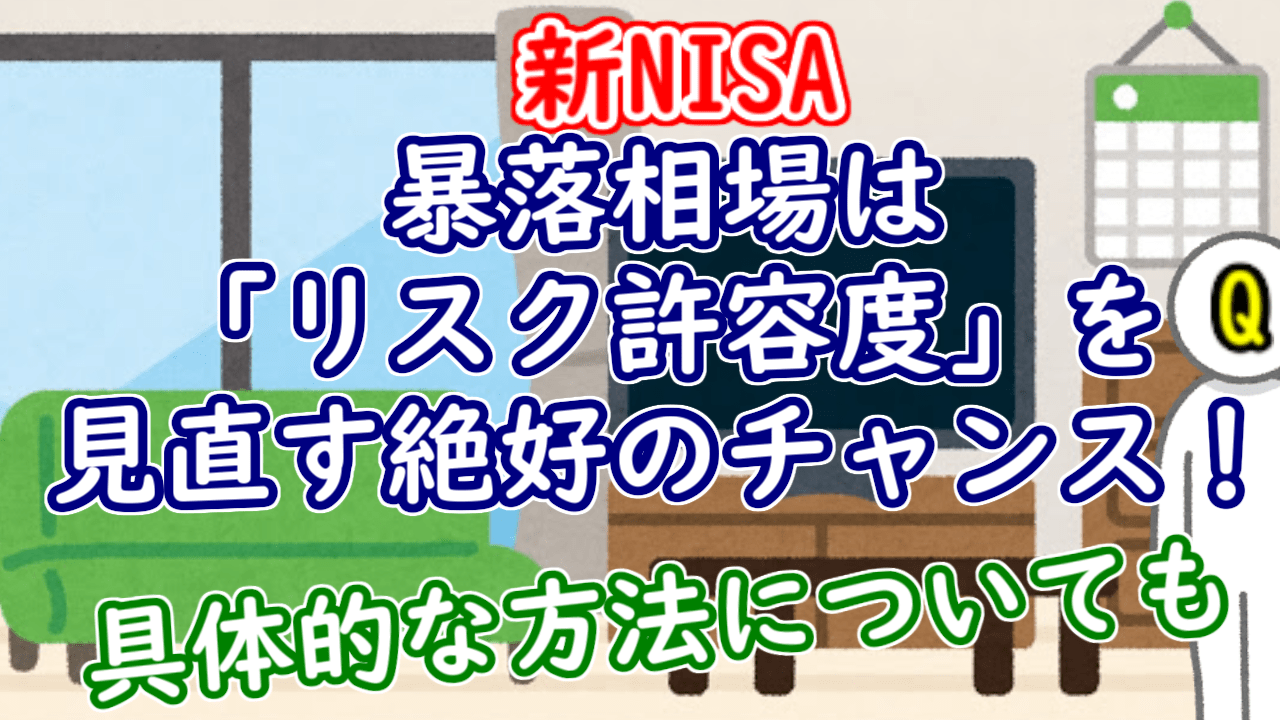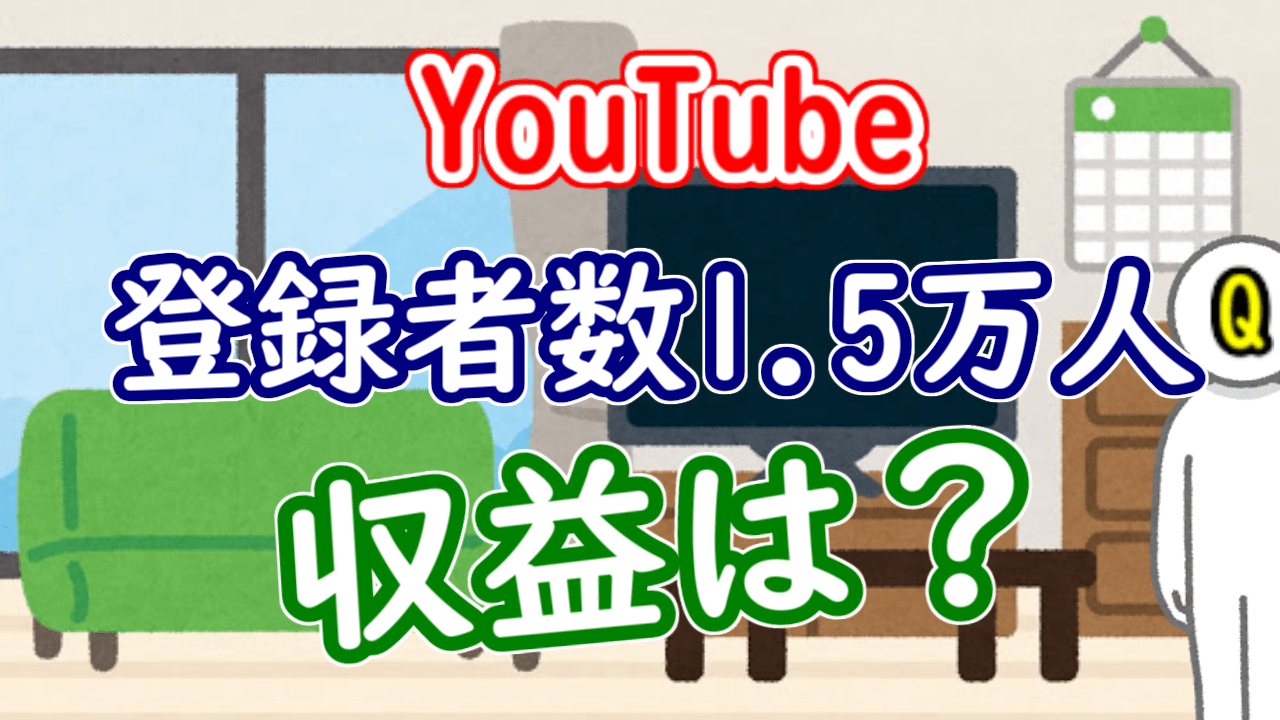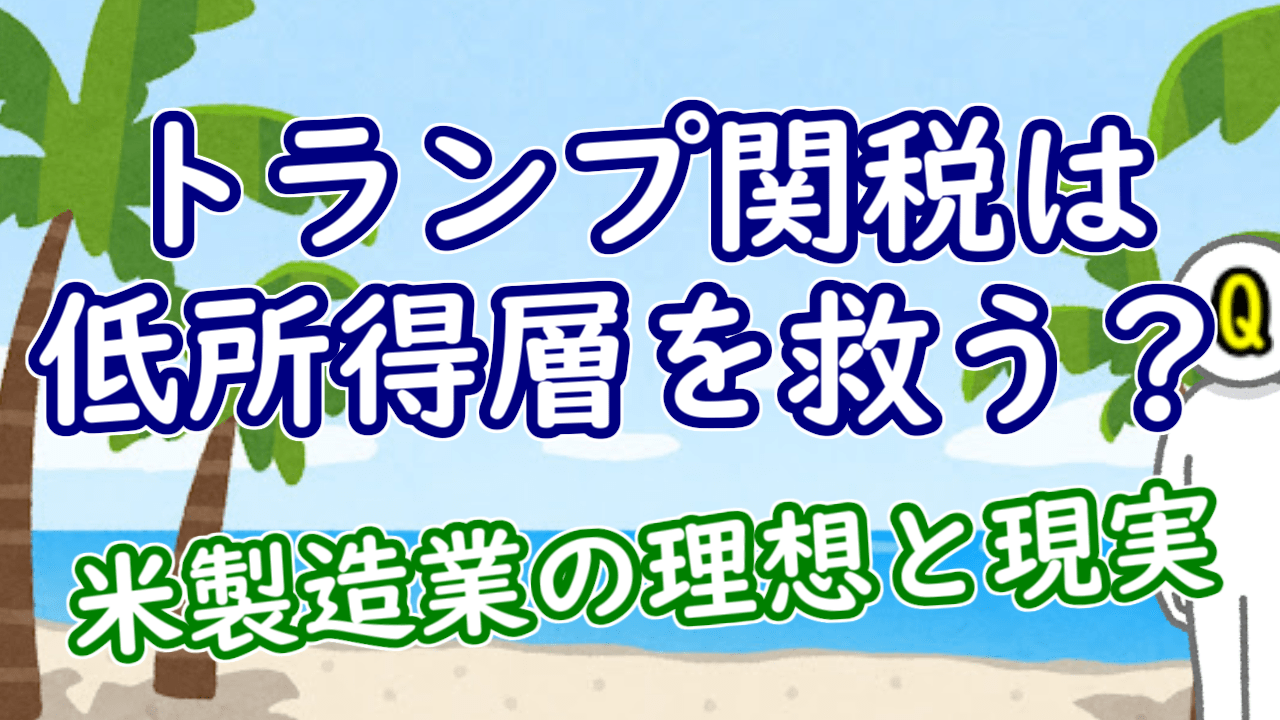
新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は、トランプ関税による製造業回帰によって、低所得者を救えるのかどうかについてです。
本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから。
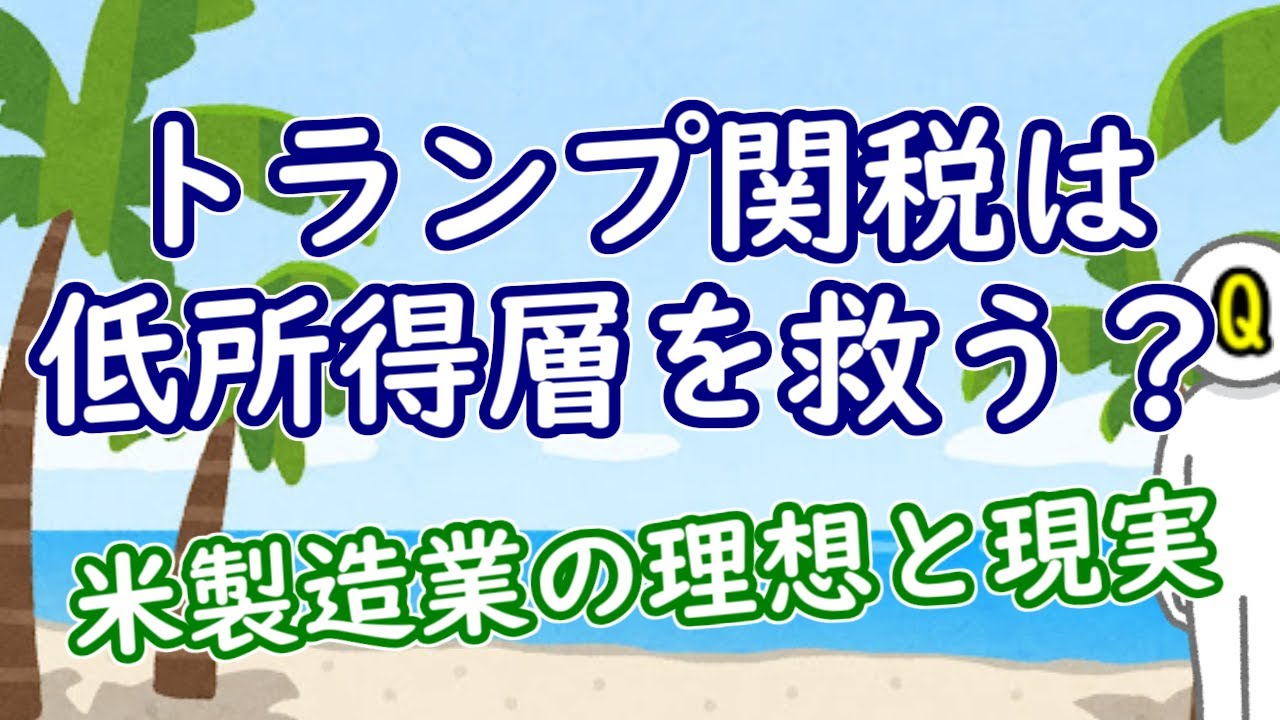
トランプ関税が低所得層を救う?
こんなご質問をいただきました。
「株式市場はトランプに振り回される毎日ですが、付き合うのも馬鹿馬鹿しいので冷めた目で見守っています。毎日毎日上がった下がったとか馬鹿馬鹿しすぎます。ニュースもこんなものいちいち報道しなくていいとは思います。
もっと本質的な問題ですが、トランプは高関税によって、米国に製造業を戻しそうとしています。しかし、今の高賃金の米国に製造業を戻しても、働き手がそもそもいません。飲食業は従業員不足で閉店している所もあるぐらいですし、低賃金労働の製造業を戻しても賃金が高くなければ誰も働かないでしょう。
また高関税によって輸入品も高くなり、仮に国内に製造業が戻った所で、高賃金の従業員による高コストの製品を買わされるので、状況的には同じです。
結果的に中国を中心にした、世界の新たな貿易構造が出来上がってしまうのではないかとも恐れています。
ところがこのような状況にもかかわらず、「トランプは空洞化した国内産業を復活させ、雇用を戻す低所得者の救世主だ」と信じている人達がいます。一体この状況のどこに低所得者を救うような真実があるのでしょうか?ご意見お聞かせください」
とのことです。
トランプ大統領を中心とした保守主義の人たちの考えですが、他の国の人件費が安いことからどんどん製造業が海外に流れていってしまい、国内の製造業が空洞化してしまったのというのがあります。
これ自体は事実でして、例えば1950年代のアメリカの製造業はGDPの25%を占めていましたが、現在ではせいぜい10%ぐらいになっています。
製造業の雇用についても、1980年代には約1,900万人いましたが、現在は約1,300万人前後と減っています。
とくにさびた工業地帯こと「ラストベルト」とか、製造業に頼っていた地方都市での失業が増加しました。これによってこれら地域の人々が中国やメキシコなどにヘイトを募らせ、それをトランプ大統領がうまく取り込んだ形になっています。
ただここでアメリカ保守層の勘違いがあるのですが、雇用人口減=製造能力減ではないのですね。
アメリカの製造業は、労働力不足を補うために機械化やAIを取り入れることなどで、高付加価値・高効率化にシフトしています。雇用はたしかに減りましたが、生産性自体は高いという状態になっています。
たとえばアメリカは、いまでも航空機、半導体、医薬品などの製造業は今も強いです。これらは高付加価値・高効率化にシフトできているからです。
たとえば高配当株で人気のみんな大好きファイザーとかも、ブランド薬品は国内生産で、とくにコロナのときに生産を戻す動きが顕著化しました。海外にも工場はありますが、ジェネリックなど低利益のものがメインになっていますね。
そんな感じでアメリカ国内の製造業は、機械化・AI利用によって高付加価値・高効率化にシフトしている時期なので、製造業が国内に戻る=雇用が増えるという単純な話ではないのです。
昔の感覚で、労働者がたくさんいるとたくさんものが作れるみたいな、そういう世界観ではなくなっているのですね。
製造業の雇用が減っているのも、海外に工場が移転したことで製造業が空洞化し、雇用が失われたという単純な話ではなく、そもそもの問題、製造業が高付加価値分野に移行していることによって、中間層の雇用を吸収していた従来型の製造業が縮小しているというのが実態です。
ようするにテクノロジーの進化が、多くのマンパワーに頼らなくていい状況をつくりだしているのです。
数人の従業員が製造を管理していればいいみたいな状況に、やがてはなっていくのです。
仮に製造業をアメリカに戻したとしても、企業が利益を得るためには、高賃金の労働者を雇う事よりも、機械やAIの導入によってひたすら効率化を進める方向に行くとは思います。
現状、単に海外のマンパワーが機械化するコストよりも安いので、天秤にかけてマンパワーをつかっているだけで、アメリカに製造業を戻して、どいつもこいつも高賃金みたいな話になれば、当然企業側は利益を出すためにモノの値段をめちゃくちゃ上げる一方で、機械化やAI導入を積極的に推し進め、人員削減の方向へと向かうでしょう。
これまで人間が管理していた部分も機械やAIが代替してしまうので、生産性は上がりますが雇用自体がどんどん減っていく方向に行きます。人間が必要なくなりますしね。
無人コンビニとか無人タクシーとか、すでにマンパワーを使わない方向での実験がはじまっています。
外食業でもタブレットによる注文や、配膳ロボットの導入など、働き手の人数を少なくする工夫がされています。
けっきょくのところ、これまでのように人の多さ=生産力の強さとならなくなってしまうのです。
ちなみに無人牛肉店とか無人餃子店で、機械化もせず、いっさい店員をおかずに「お金を入れてください」で、盗まれて文句をいっている人たちがいますが、それはさすがにだめだろうとは思います。
せめてお金を入れると商品が出てくるような、自動販売機にするなりすればいいだけとは思います。というか、それぐらいはしようよとは思います。そのコストをケチって、被害にあっているのであれば、どうなんだろうとは思います。
正直、日本以外でこういうことやってる国をあまり見たことがありません。日本は治安がいいから成り立つのかもしれませんけど、いまはそういう状況でもなくなっていますしね。
それはともかく、こういう日本のケースは例外として、人件費が上がれば、企業側は本格的に機械化導入を考えはじめてしまいます。そうなると、仮に製造業がアメリカに戻ったとしても、効率化によって最終的には人員が必要なくなる状態ができあがってしまいます。
ただ現状、それをおこなうには多額の投資が必要になるため、マンパワーでなんとかしている状態ですが、採算がとれなくなれば話は変わってきますので、現在はその過渡期にいるような状況ともいえるでしょう。
サービス業など機械で代替できない部分の多い分野だとまだまだマンパワーが必要ですが、製造業はそのうち機械化やAI化が進んで、保守派が望んでいた未来とはまた別の方向へと進む可能性もありますね。
それとこれは雇用面だけの話ですが、製造業はそれをつくるための材料とかも必要なので、高関税だとそのあたりも高コスト化してしまいますね。そうなるとモノの値段も上がりますので、低所得層ほどダメージは大きくなります。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・マンパワーの安い海外に製造業が流れたことで、アメリカの製造業が空洞化し、雇用が減っていったのは事実。
・ただアメリカはいまでも航空機、半導体、医薬品などの高付加価値の製造業は強い。
・雇用が減ったのは海外のせいだけではなく、国内の製造業が高効率・高付加価値分野に移行していることで、マンパワーを必要とする従来型の製造業が縮小したことも雇用減少の一因。(単純に海外のせいだけではないのですね)
・「製造業=マンパワーの多さ=生産量の多さ」という旧来の常識ではなくなっている。
・現状、機械化・AI導入への投資より、海外のマンパワーのほうが安いから、海外で生産をおこなっている。
・高関税によってインフレが進み、アメリカの労働者の賃金が高くなることで、企業はモノの値段をそれ相応に上げる一方、機械化・AI導入による効率化が本格的に進む可能性(無人コンビニとか無人タクシーなども出てきてますし、多くのマンパワーをつかわなくていい状態になってくるのですね)。
・高関税での材料高騰により、製造業のコストは上がり、モノの値段が上がる。低所得層へのダメージが大きい。
となります。
トランプ大統領など保守層の考えだと、製造業がぜんぶコモディティ化していて、単純に海外で生産して利益を得ていたものを国内に戻せば、その利益をアメリカが取れると思い込んでいますが、そもそも海外生産は安いマンパワーに頼った生産体制なので、それらを高賃金の国内に戻せば採算が取れなくなります。
企業側としてはモノの値段をめちゃくちゃ上げて採算をとらなければなりませんし、マンパワーを必要としないように機械化やAI導入で効率化をすすめるしかなくなるわけです。慈善事業をやっているわけではありませんしね。
じゃあ、こういう社会からあぶれてしまった人たちをどうすればいいかといえば、それは民間のやることじゃなくて、それこそ国が福祉で助けないといけないわけですが、イーロン・マスク氏とかがその予算削っちゃってしまってますしね。
無駄は省いて良いですが、本来政府のすることは、民間では助けられない弱者を税金使って助けることなので、そこも削って小さな政府にしたら低所得者層へのダメージも大きくなってしまいます。
まあ、トランプ大統領はいってることがころころ変わりますし、今後また何が起こるかわからないので、企業側もおいそれと国内に工場を作る気にはなりにくいとは思います。工場作ったあとに、「やっぱ関税やめるわ」とかいきなり言い出される怖さもありますしね。
そんなわけでトランプ大統領一人に振り回され続けている状況ですが、社会実験としては面白いので、どうなるか見守っていきたいとは思います。