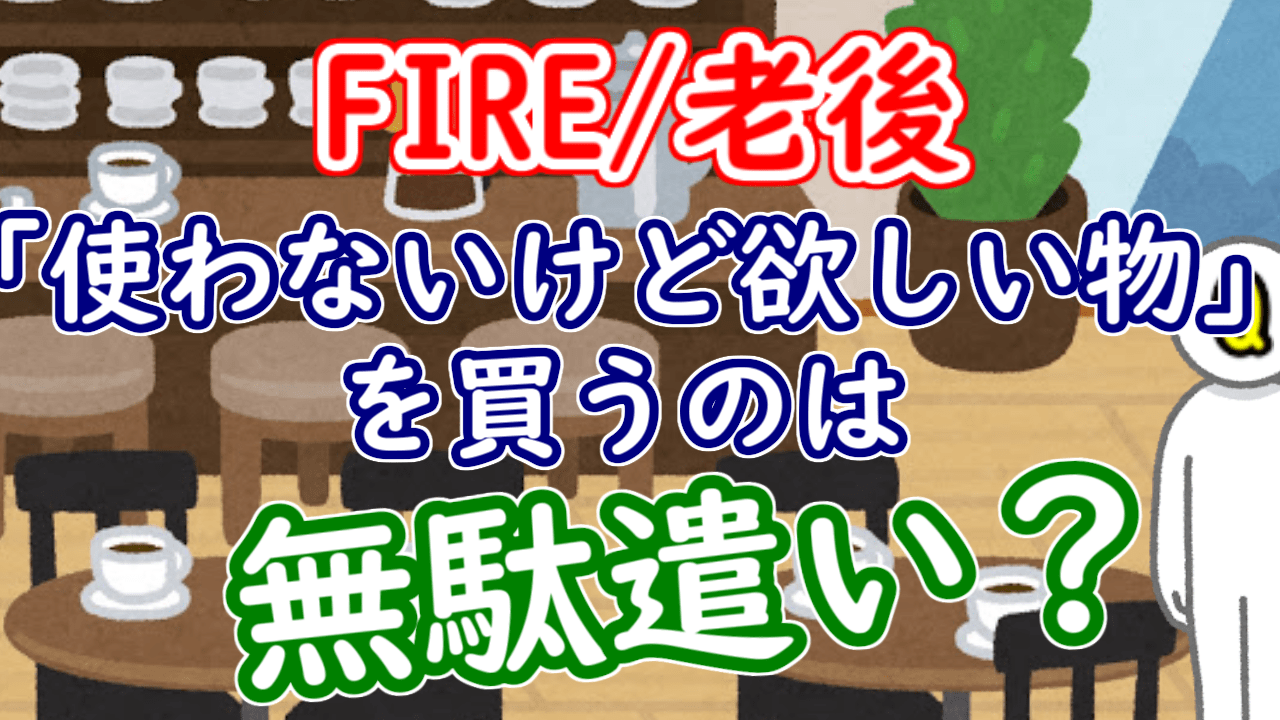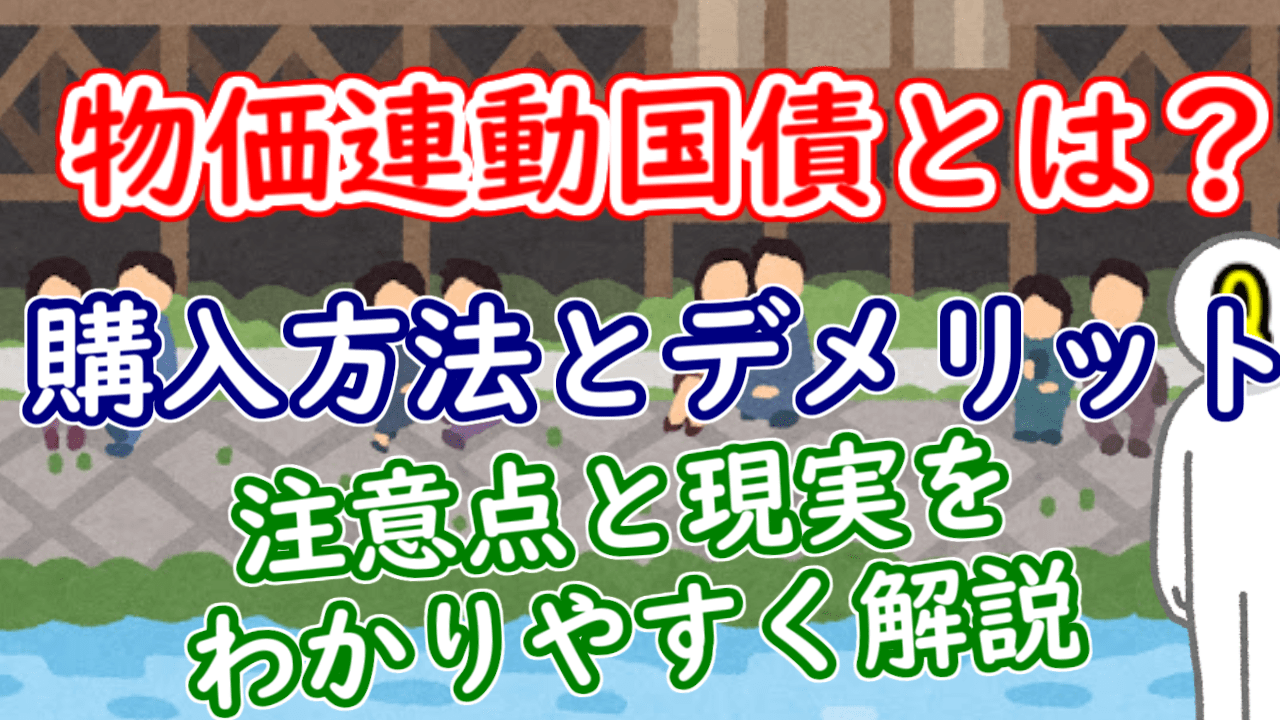
新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は物価連動国債の購入方法と注意点についてです。
本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから。
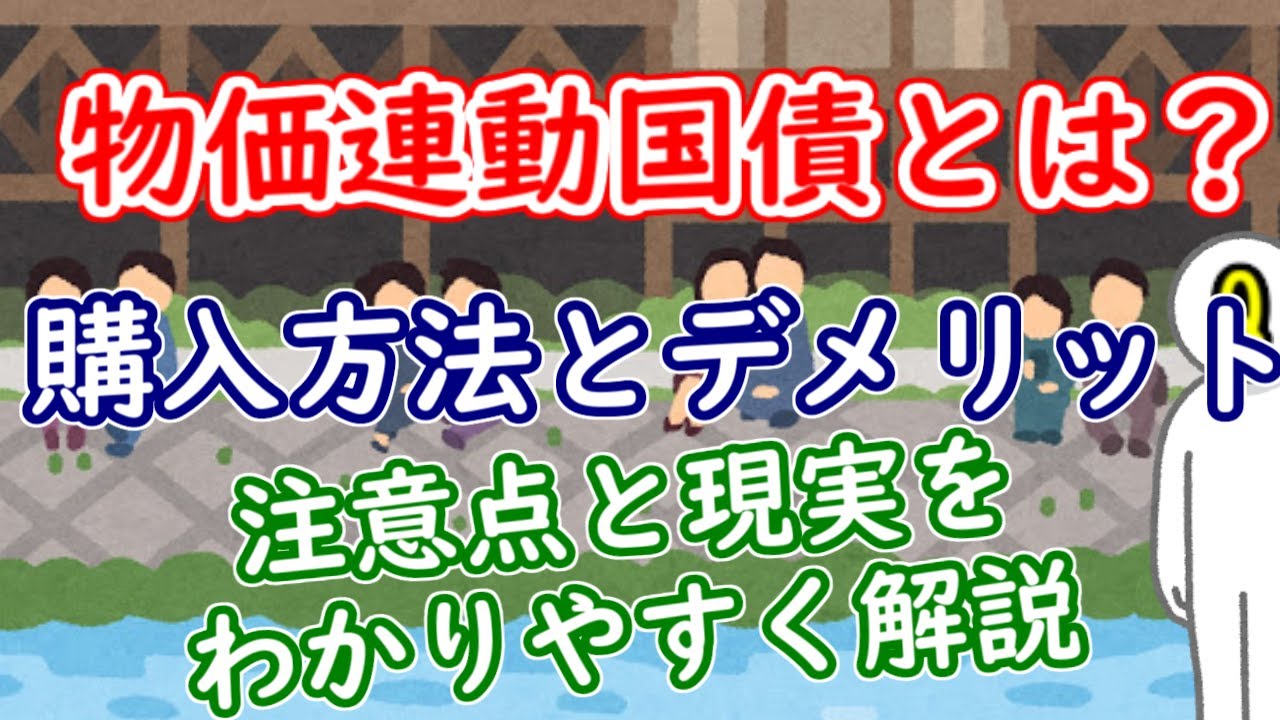
物価連動国債の購入方法と注意点
こんなご質問をいただきました。
「質問があります。 高橋洋一という経済学者の動画をよく観るのですが、各方面で物価連動国債を勧めています。
ただ物価連動国債は金融機関が買い占めてしまい一般人が買うことが難しいとのことです。
またいくつか物価連動国債の投資信託が出ているのですが債券ファンドにしては手数料が高額のようです。
Q太郎さんはバケツ戦略で安定資産は現金や国債がいいと様々な動画でおっしゃっておりますが、物価連動国債ファンドや個人向け国債の生債券について考察いただけると幸いです。 よろしくお願いします。」
とのことです。
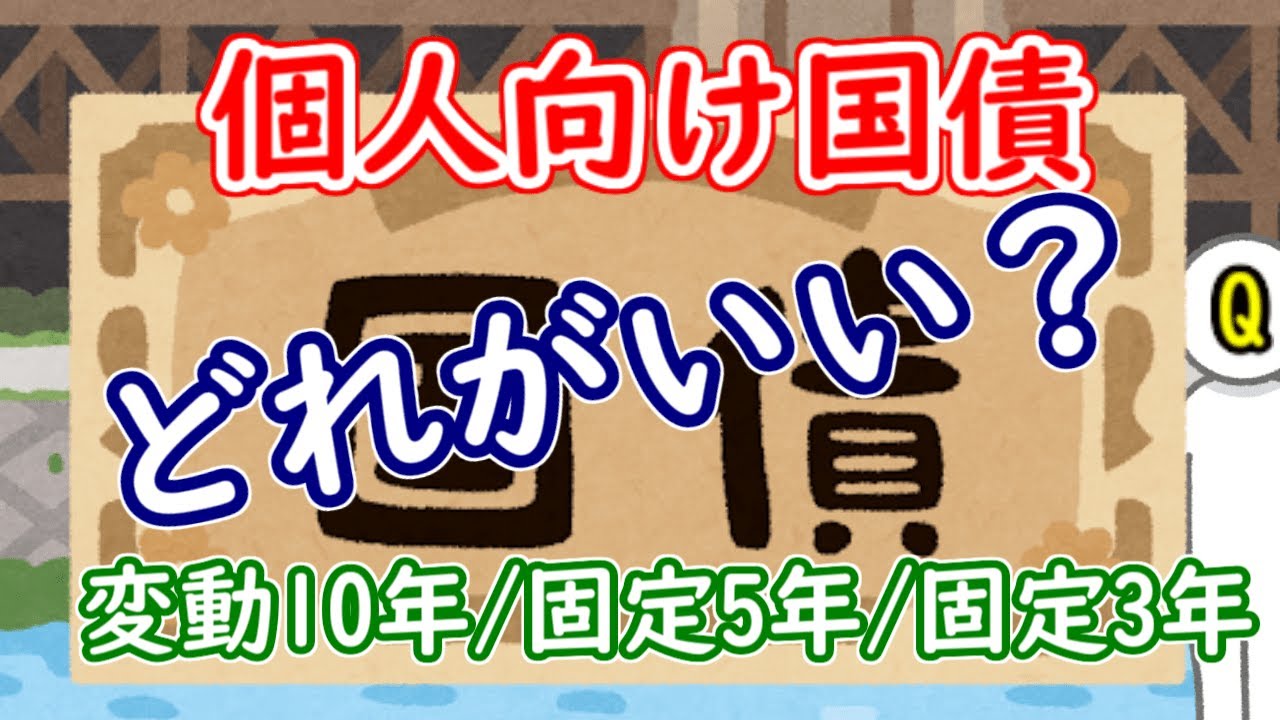
個人向け国債については以前動画で取り上げましたので、詳細はこちらをご覧ください。リンクを概要欄に貼っておきます。
簡単に説明すると、変動10年は、10年債利回りに0.66%を掛けたもので、固定5年は5年債利回りから-0.05%を引いたもの、固定3年は3年債利回りから-0.03%を引いたものになります。
変動10年:10年債標準利回り×0.66%
固定5年:5年債標準利回り-0.05%
固定3年:3年債標準利回り-0.03%
掛け算と引き算なので、利回りが大きくなると引き算のほうが有利になります。たとえば利回りが0.1%と低いのであれば、ここから固定5年の-0.05%を引くと、半分損することになります。ただ利回りが4%とか高くなったら、-0.05%なら3.95%なのでほぼフルでもらえます。
ただ固定は買った時点での金利で固定なので、金利の高い時に買わないといけないという、タイミングを見る面倒臭さがあります。そのため、Q太郎は面倒のない10年変動を年末年始あたりの募集時期に買っています。
個人向け国債は1年以上保持すればいつでも解約できますし元本保証なので、金利が低いことを除けば、買い手がかなり有利な商品なのですね。
物価連動国債について
それでもう一つのほうの物価連動国債についてですが、これには一般と個人向けで分かれています。
それで個人向けの10年ものの個人向けが2015年に解禁されて、大手銀行や大手証券会社とかで、新規募集のときに買う事ができるようになりましたが、そもそも個人向けは発行量が少ないうえに、金融機関も積極的に売る気があまりなく、結果的に購入困難のような状況になっています。
なんで売る気があまりないかといえば、仕組みが複雑なので説明が面倒だからです。
数万とか数十万単位でたくさんの人に売って、そのあとの対応が面倒になるよりも、金持っているところに数千万とか数億単位で一括で買っていただいたほうが面倒がありません。一か所に売るだけですしね。
そんなわけで証券会社はやる気がないですし、個人向けはそもそもの流通量が少ないので購入が困難というのもあります。
手軽に買いたいのでしたら、楽天証券などだと「eMAXIS 国内物価連動国債インデックス」などの投資信託を買う事により、間接的に投資をすることができます。ただ当然投資信託である以上元本保証ではないので注意が必要です。元本保証でない以上、中期バケツに置くことはできません。置くなら長期バケツになります。
この物価連動国債がどういうものかですが、額面に対して物価変動分を追加するというものなので、インフレを加味した場合に増えているわけではないことに注意してください。あくまで元本を物価変動分維持するというものです。増やす物ではありません。
物価というのはようするCPI、消費者物価指数ですね。使われるのは変動の激しい生鮮食品などを抜いたコアCPIになります。そのためスーパーの物が高くなってるからインフレ対策にと思ってこれを買うと、コアCPIなのでそれらの食品は考慮されていないわけです。あくまでそういう毎年変動の激しいものを抜いた、コアになる物価ですね。日本だと現在前年比で3%ほどの上昇になっています。
たとえば100万円分の物価連動国債を買ったとして、一年後にコアCPIが3%上がったとしたら、103万円になります。ただこれは増えているわけではなくて、あくまで1年前の価値を保存したということになります。価値自体はおなじなのですね。
ここで3%もらえるなんてすごいじゃんみたいな話になるかもしれませんが、そう簡単な話ではなく、まず今後のコアCPIの価格が高くなると予想されると、入札時の購入価格が高くなってしまうのですね。
たとえば10年間で少なくとも毎年2%ずつ物価が上がると予想した場合、単純計算で10年後には120万円になるわけです。
だとすると、120万円で入札する人が多くなり、発行金額が120万円ぐらいになってしまうわけです。仮に毎年3%ずつ物価が上がれば、10年後に130万円なので、差し引き10万円の儲けになります。すると10年間で10万円なので、実際の利回りは年間1%ということになります。
逆に日本がデフレに突入したとき、たとえば毎年1%ぐらいしかコアCPIが上がらなかったら、10年後には110万円なので、120万円で買った場合は10万円損することになります。
それで元本保証ですが、あくまで額面しか保証されません。つまり100万円までですね。これを「フロア」という言い方をします。それでフロアが100万円のものを120万円で入札したのですから、20万円の部分は自己責任となります。
そんな感じで、インフレが予想される場合には、その分入札価格も上がるので、差し引きで考えれば結果的に利回りは低くなりますし、皆さんが期待するような毎年数パーセント手に入ってがっぽがっぽというようなものではないわけです。あくまで入札時との差額ですね。しかも場合よっては損することになります。
先ほども述べたように、元本保証というのはフロア部分の保証なので、実際の入札価格との差額分については知った事じゃないわけです。10年後に、予想していたインフレ率以下だった場合は損するので、普通の国債よりはリスクが高いことになります。
それと日本自体の問題もあって、現在のインフレは経済がまわっているからインフレになっているわけではなく、円安や物不足によるコストプッシュ型のインフレになっています。
そうなると、輸入に頼っている日本のインフレ要因になるのは為替なので、これをヘッジする場合は物価連動国債よりもドルやユーロなど他国の通貨や株式を持つほうが手軽とは思います。まあ、オルカンとかS&P500を買っていれば、長期的なヘッジとしては十分とは思います。最近アメリカがアレなので、オルカンのほうが安心感が出てきていますね。
もしくはゴールドとかも、長期的には価値を保存してくれますので、長期なら物価連動国債代わりとして使えるとは思います。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・個人向けの物価変動国債は流通量が少なく、証券会社も積極的に売る気がないので入手困難。
・手軽に買いたい場合は「eMAXIS 国内物価連動国債インデックス」など投資信託を利用。ただ元本割れがあるので注意。
・物価連動国債は今後のインフレが見込まれる場合、入札価格が上がるので、結果的に高額になって年間の利回りが少なくなる可能性がある。(期待するようなバラ色の利回りにはなりづらいでしょう)。
・デフレなどで入札時の予想利回りを下回ると損失が出る。
・そもそも物価連動国債の元本保証は、フロア部分(額面)が保証されるだけで、入札時の値上がり分に対しては保証がない。
・輸入に頼る日本のインフレ要因は円安。海外通貨や海外株式など為替ヘッジが必要(オルカンやS&P500を買っていれば、長期的には十分なヘッジになるとは思います)。
・長期的な価値の保存という意味では、ゴールドへの投資も一つの方法。
となります。
そんなわけで物価連動国債は購入が難しく、手軽に投資したければ投資信託の利用になります。
そして物価連動国債自体もフロア部分しか保証されていないリスク商品なので、中期バケツ向きではないかなという感じですね。中期バケツはせいぜい数年レベルで、物価連動国債は10年でリスクも抱えているので、運用するとすれば長期バケツの中になります。
一般国債と違って、リスク込みで10年という話になると、そんな長期だったら為替ヘッジにもなるオルカンとかS&P500でよくないかという気もしてきます。実質利回りも入札価格の差額になるので、そんな期待するほどのものでもないですしね。必死で手に入れようとするほどのものでもないとは思います。
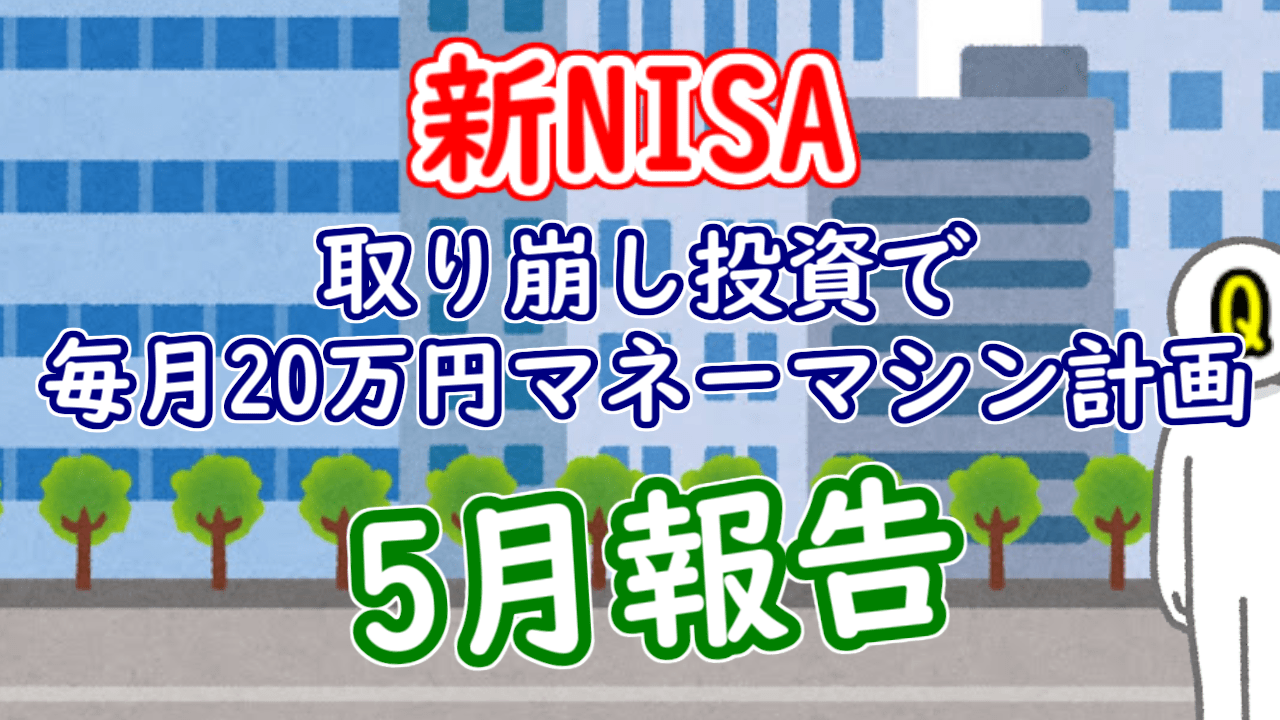
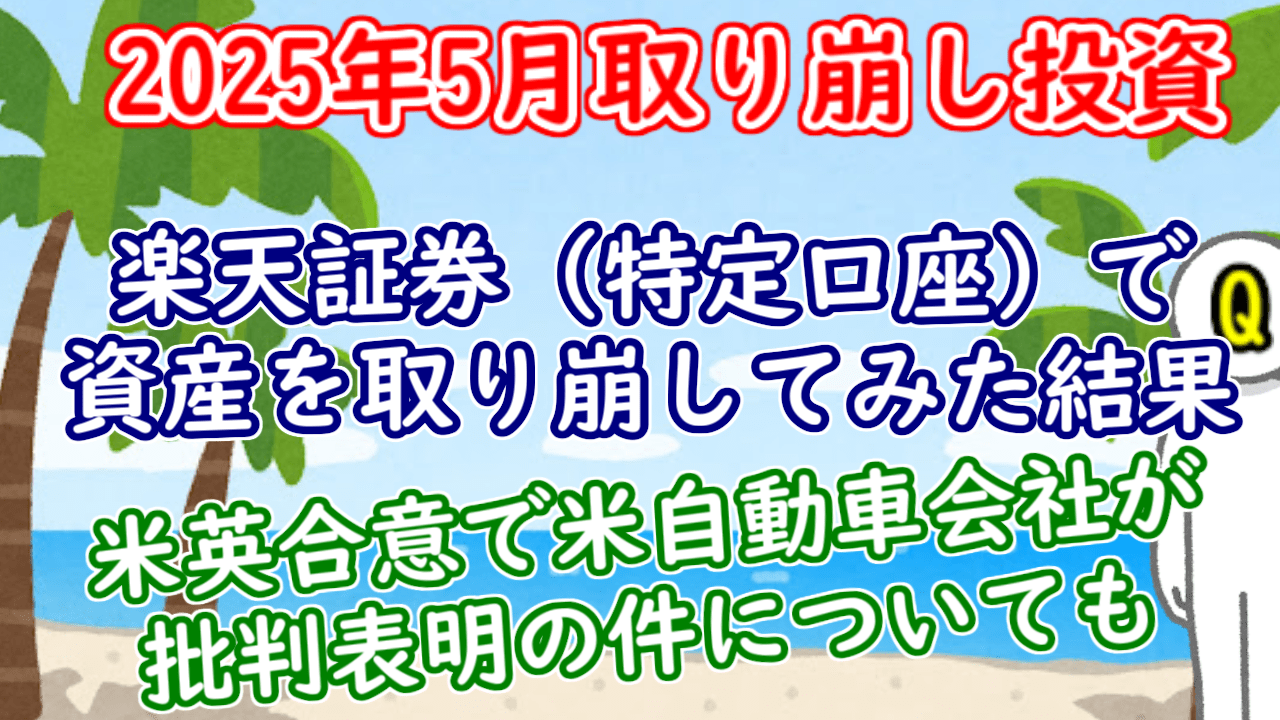
それとみなさん、物価連動国債に多大な期待をしているようですが、ぶっちゃけ利回りが低いです。せいぜい0.1%前後とかそんなレベルなので、個人的には普通に個人向け国債の10年変動買ったほうが情報も多いですし、いいと思っています。どちらにしろインフレになれば金利上がりますしね。
物価連動国債について多くの人が過大な期待を寄せていますが、利回りそんな高くないですし、
簡単