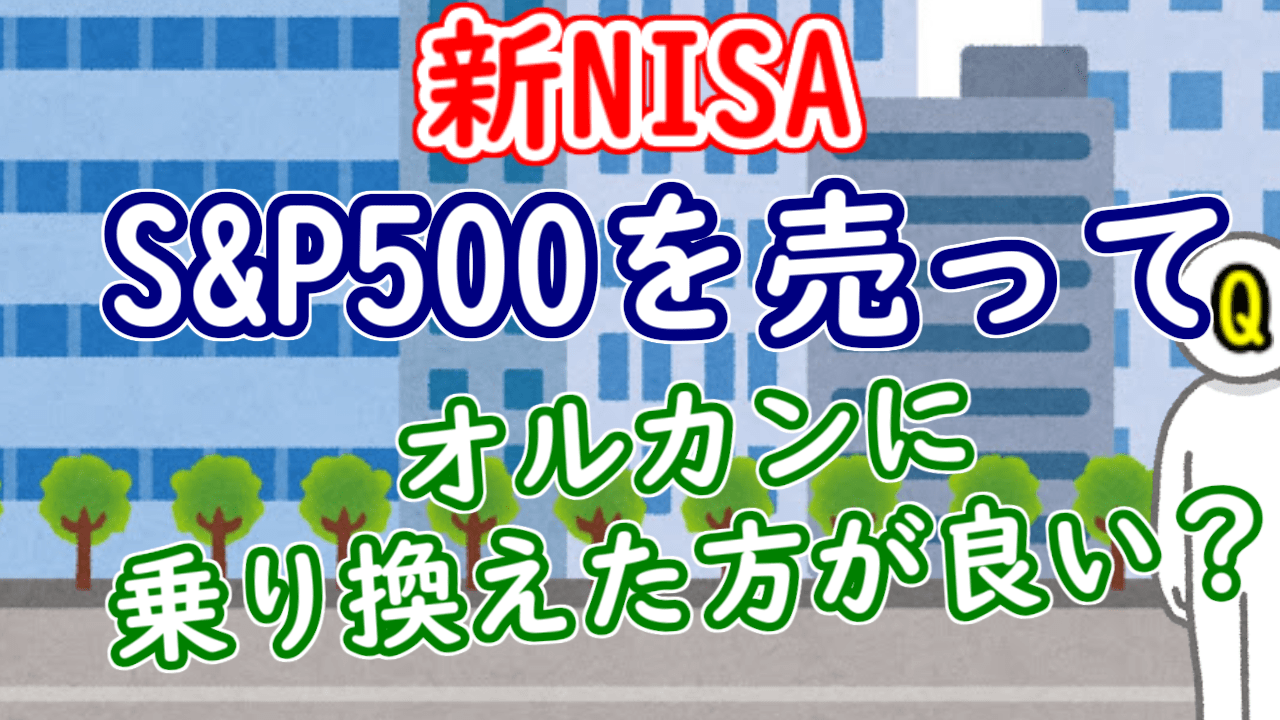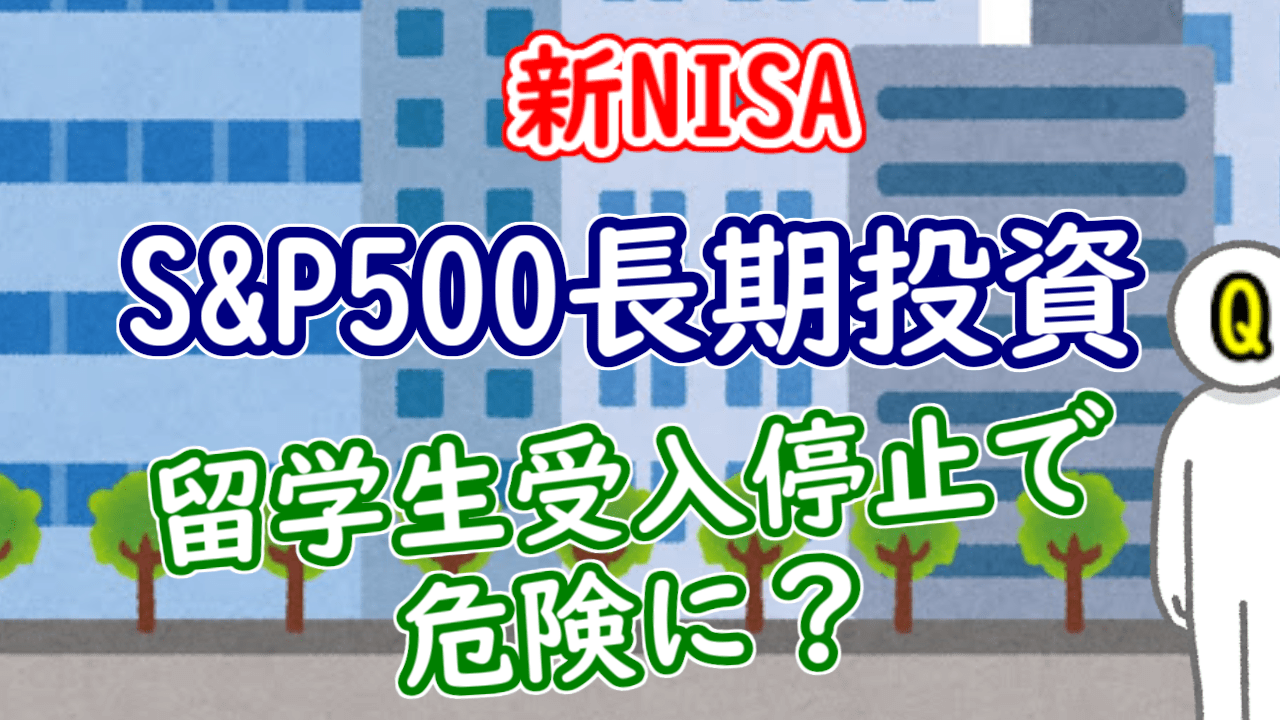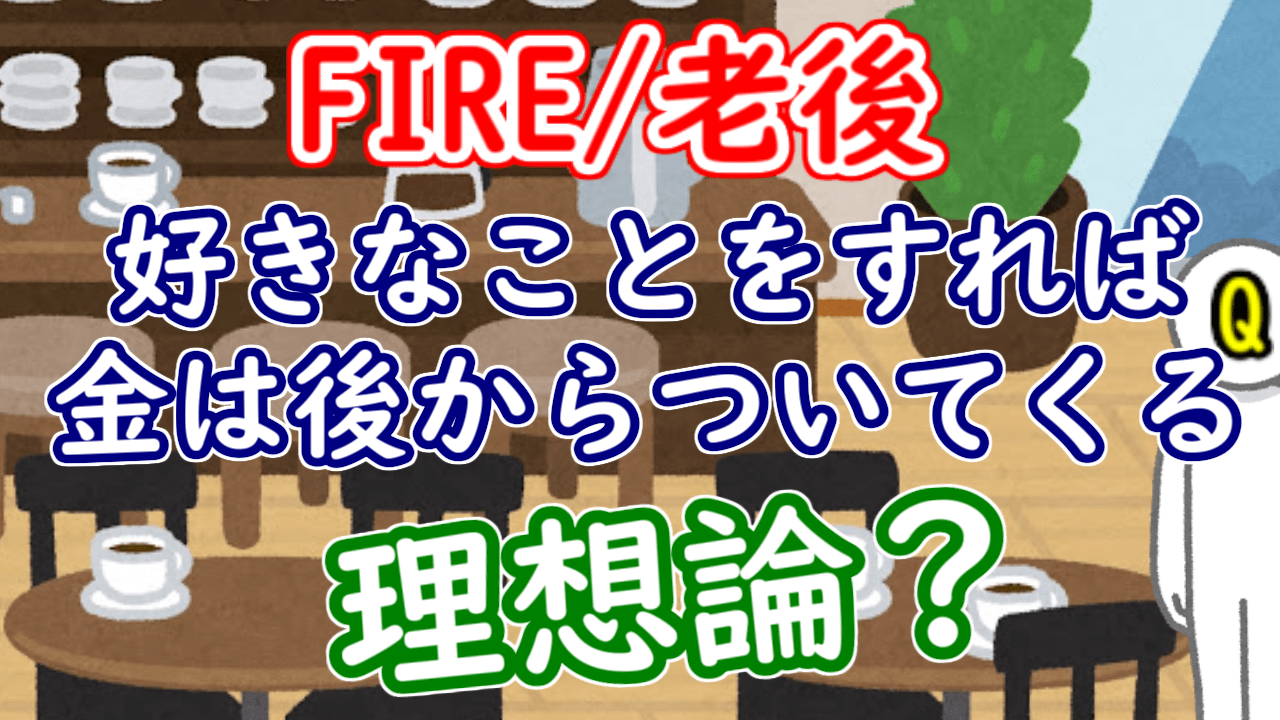
新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は、よくいわれる「好きな事をやれば、金は後からついてくる」がただの理想論ではないかとのことについてです。
本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから。
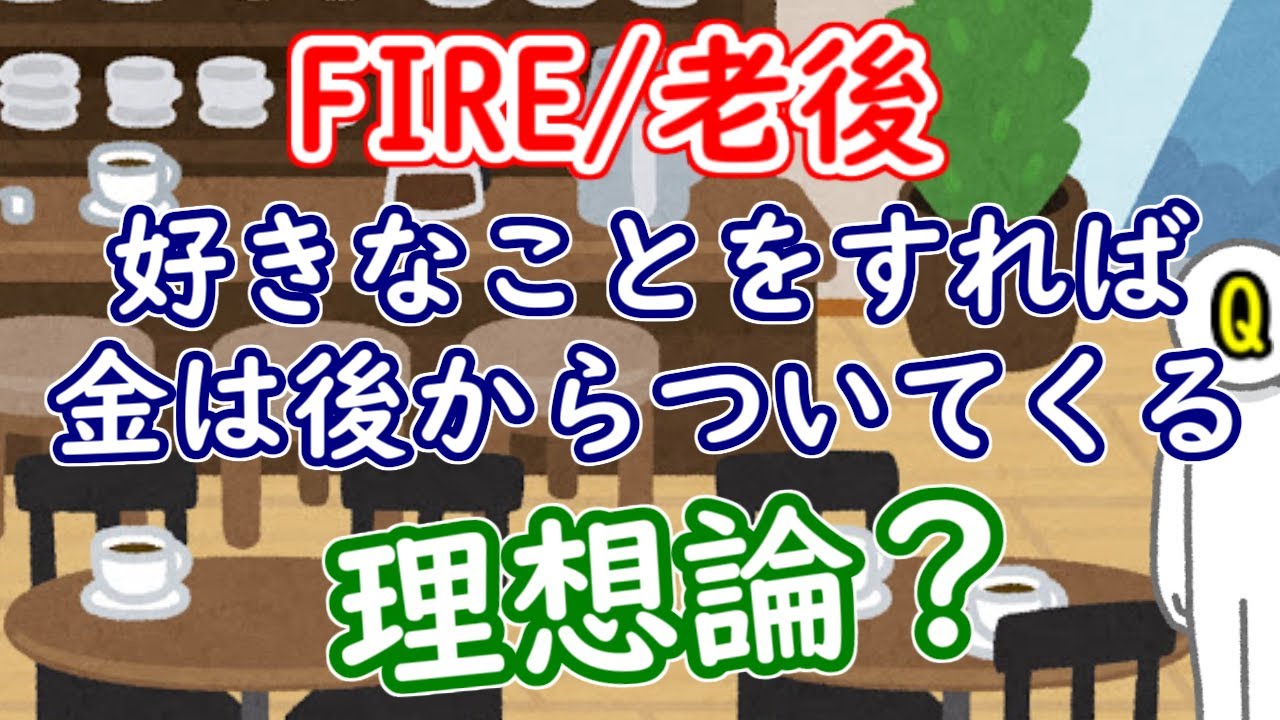
「金は後からついてくる」は理想論?
こんなご質問をいただきました。
「FIRE界隈でのよくある夢煽りで「金を気にするな。好きな事をやれば、金は後からついてくる」というのがあります。
それで成功する人もいるとは思うのですが、大半の人には無理なのではないでしょうか?
私は高校でサッカー部に入っていましたが、サッカーが好きだからと言ってそれで食っていける訳では無いです。サッカー選手になった知り合いはほぼいません。サッカーが好きでいくら練習を頑張っても、プロになれるとは限らないのです。
仮にプロになれたとしても、有名選手以外は活躍できるのは20代だけで、30代になったら別の職業を探す必要があります。好きな事をやっても、金はついてきていません。
極端な例で言えば、サッカーが好きでも足が不自由だったら、どれだけ好きだろうとそもそも選手に選ばれませんので、お金はついてきません。
「好きな事をやれば、金は後からついてくる」派の言い分としては、好きな事をずっとやっていると専門性が磨かれていき、その分野で突出した人材になれるとのことですが、多くの人がそういう事をやっているわけで、結果的には競争になって生き残った人にだけ金がついてくるという構造になっています。
単に好きな事を何年もやっても、金がついてこないどころか、貧困まっしぐらです。この事についてご意見お聞かせください。」
とのことです。
「夢煽り」という言葉は初めて聞きましたが、内容からして夢を持っている人たちを煽ってその気にさせるということだとは思います。こういうのはプラスに働く場合もあるので、一概にどうとも言えない部分もあります。
それで「好きな事をやれば、金は後からついてくる」ですが、これはいわゆる典型的な生存バイアス的発言になります。理想論というか、生存バイアスですね。
生存バイアスとは、ようするに生き残った人たちが注目されて、その裏にいる死屍累々の大多数の失敗した者たちについては語られないというものですね。そもそも生存している人しか語れませんし、その言葉だけがクローズアップされて、認識の偏りができるというものです。失敗した対象を見ずに、成功した対象のみを基準に判断してしまうということですね。
例えば「好きなことに没頭してたら仕事になった」という人がいますし、その人は実際にそうなのだとします。それはその人にとっては真実なので嘘でもありませんし、それでいいのですが、統計で見た場合、おなじように好きな事に没頭していても、仕事にならなかった人たちのほうがたくさんいるわけです。
そういう仕事にならなかった大多数はただ黙って去るだけなので、「好きなことに没頭してたら仕事になった」という人の言葉だけがクローズアップされてしまいます。統計的には失敗者が98%、成功者が2%だったとしても、世の中に広まるのは2%の言葉だけです。それを聞いて、「好きなことに没頭してたら仕事になった」が真実だと思ってしまうのが、生存バイアスというものです。認識の偏りなのですね。2%の「真実」に偏ってしまってそれが全体の真実だとしてしまい、消え去ってしまった98%の「真実」は無視されるという状況です。
ここで重要なのはどちらも「真実」ということです。ただ生き残ったほうの「真実」が全体の「真実」として認識されてしまうわけです。
例えばYoutubeで、「好きなゲームでYouTube実況をやってたら有名ユーチューバーになれた」という人がいますが、その陰で何万人が途中でやめたかは語られないわけです。
Youtubeで収益化できているチャンネルは2%程度とも言われますし、その2%の中で月収が10万円超えているのはさらに少ないでしょう。ちなみにこのチャンネルは平均して月2万円とか、よくて3万円とかそんなレベルです。前月は2万円以下でした。時給だと200円とかそんなレベルですし、趣味じゃないとやってません。
そんな感じで、ユーチューバーや小説家やミュージシャンのいう「好きなことをやっていたら、十分な収益が得られるようになった」というのは、当の本人にとっては間違いのない「真実」なので、その人を責める理由はまったくありませんが、それだけを信じるのは生存バイアスによる認知の偏りになるので、統計で見た場合はその裏に膨大な数の失敗者がいるという「真実」も合わせて理解しておく必要はあります。
どちらも「真実」なのですね。ただ片方の真実が全体の真実であるかのように思ってしまうのが生存バイアスの問題なのです。
生存バイアスでよく例に出されるのは、第二次世界大戦の戦闘機の話です。
少ない資源で戦闘機の装甲を強化するために、どこを強化するかで議論が交わされたのですね。
それで生き残って戻ってきた戦闘機を調べたところ、被弾はひどかったのですが、コックピットとエンジンだけは弾を食らっていませんでした。
ここで科学者がひらめきます。「コックピットとエンジン以外の被弾がひどいので、コックピットとエンジン以外の装甲を強化すればいいんだ!」という、笑い話のようなまじめな話があります。
コックピットとエンジンに弾が飛んできた戦闘機は、そもそも墜落して戻ってこられませんしね。
そんな感じで生き残った者の言葉だけを信じるととんでもないことになったりすることもあるので、生存バイアスにひっかからないためには、「同じことをやって失敗した事例の数や実態は?」と、全体的・統計的に考える必要があります。
音大に行ったからと言って、音楽で食っていける人があまりいないのも統計的にはわかっていることですし、統計がわかれば「好きな事をやれば、金は後からついてくる」は典型的な生存バイアス的発言というのはわかるとは思います。
そもそも「好きな物」はみんなもだいたい「好きな物」なので、むしろそれをやるためにお金を払わないといけないのが普通とは思います。
お金が発生するのは、みんながやりたくないので、代わりにやってあげるからお金が発生するのであって、やりたい人が多かったらむしろお金払わないといけないのですね。
質問者様がサッカーをやっていたとのことですが、サッカーをやるにしてもユニフォームやらボールやらいろいろ買わないといけないとは思います。やりたい人が多いので、それらが無料で提供されることはないわけです。むしろやりたい人が多いため、それを売ることが商売になるわけです。
そんなわけで、「好きなことで食っていけるのは、好きな事をずっとやっていると専門性が磨かれていき、その分野で突出した人材になれる」というのも、成功した人にとってはそれが真実なので、その人自身も嘘はついていないのですが、全体で見た場合、統計で見た場合にどうなのかということも合わせて考えないと、先ほどの戦闘機の例のように、生存バイアスにひっかかって間違った判断をしてしまうことにもなりかねないわけです。
ホリエモンのいう「有り金は全部つかえ」は、哲学的には理解できますし、ホリエモンにとっては真実なのですが、世の中には有り金を全部使って破産してしまった人たちがごまんといますので、こういうのも生存バイアスといえます。
そんなわけで、意見の一つとして聞いて良いですし、それで自分のやる気になるのであれば結構だとは思いますが、あくまで生存バイアスの一つなので、「全体ではどうなのか」という俯瞰した視点も合わせて持っておいたほうがいいとは思います。
逆に言えば、失敗者の意見だけを聞いて、やっても無駄なんだと思う事もバイアスになっています。あくまで全体ではどうなんだということと、自分の能力ではどのポジションになるのかなど、そういう分析が必要になってきますね。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・「好きな事をやれば、金は後からついてくる」は典型的な生存バイアス的発言。
・その人にとっては真実でも、全体で見た場合は少数派。ただ失敗者の言葉は広がらず、成功者の言葉だけがクローズアップされるため、認識の偏りが起こる。
・片方の真実が全体の真実であるかのように思ってしまうのが生存バイアスの問題。
・逆に失敗者の意見だけを受け止めて、「やっても無駄」と思うのも認識の偏り。
・意見の一つとして受け止める一方、「全体ではどうなのか。自分の能力ではどのポジションになるのか」などの分析が必要(そうでないと偏りが起こって、全体像が見えなくなりますしね)。
となります。
そんなわけで、成功者の意見も失敗者の意見も、片方だけ聞けばバイアスが働いてしまうので、あくまで全体でどうなのか、自分の能力でやってみたばあいどうなるのかなどを分析していく必要があります。
例えば「英語が好きで、通訳になれた」という人がいて、自分は英語が好きだけど英検2級だった場合は、まだ勉強が必要という話になります。そもそも通訳というのが日本に何人ぐらいいて、どういう経路から通訳に慣れたのかなど、本当になりたければそういうことも調べないといけなくなりますね。
そんなわけで、「好きな事をやれば、金は後からついてくる」は一つの意見で、成功した人にしてみればそれは真実なのですが、統計で見た場合はどうなのかということ、自分の能力ではどこまで行けるのかなどの、俯瞰した分析も必要になってくるとは思います。
サッカーが好きでいくら練習してもプロになれるかどうかわからないというのも、全体の分析と、それに対する自分の能力の分析をしたうえで、可能性があるかどうか考える必要があるとは思います。