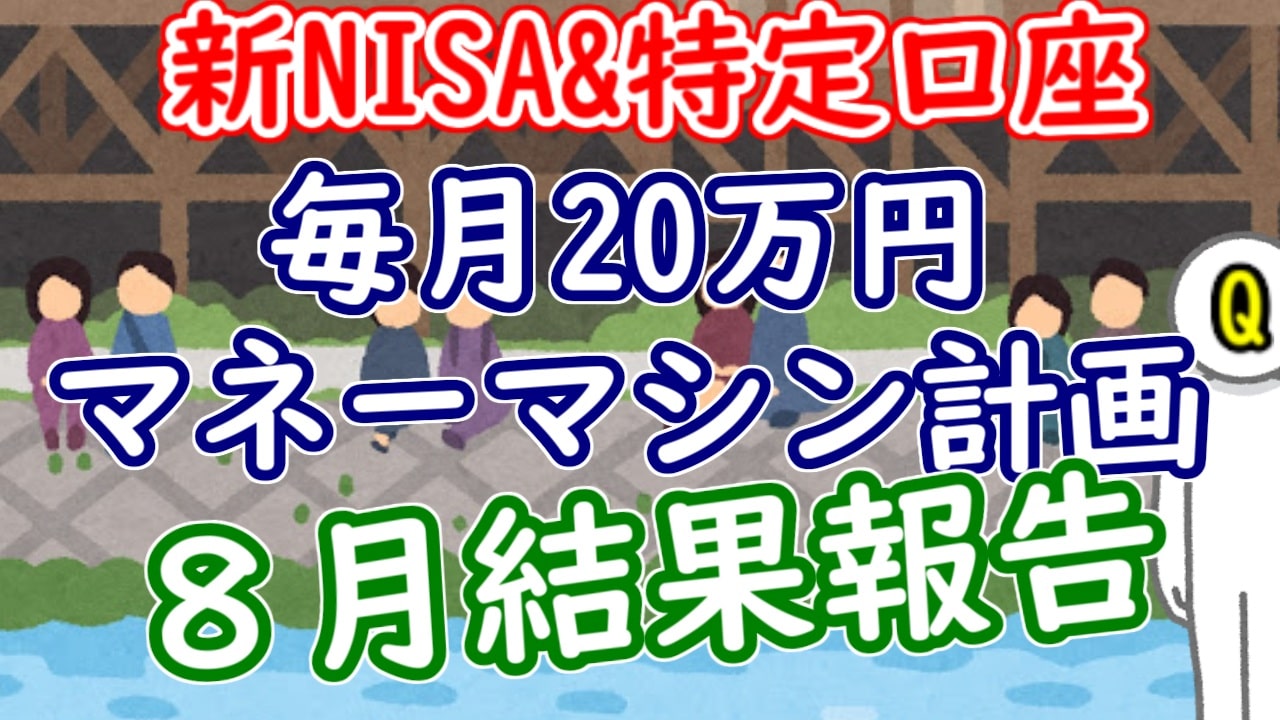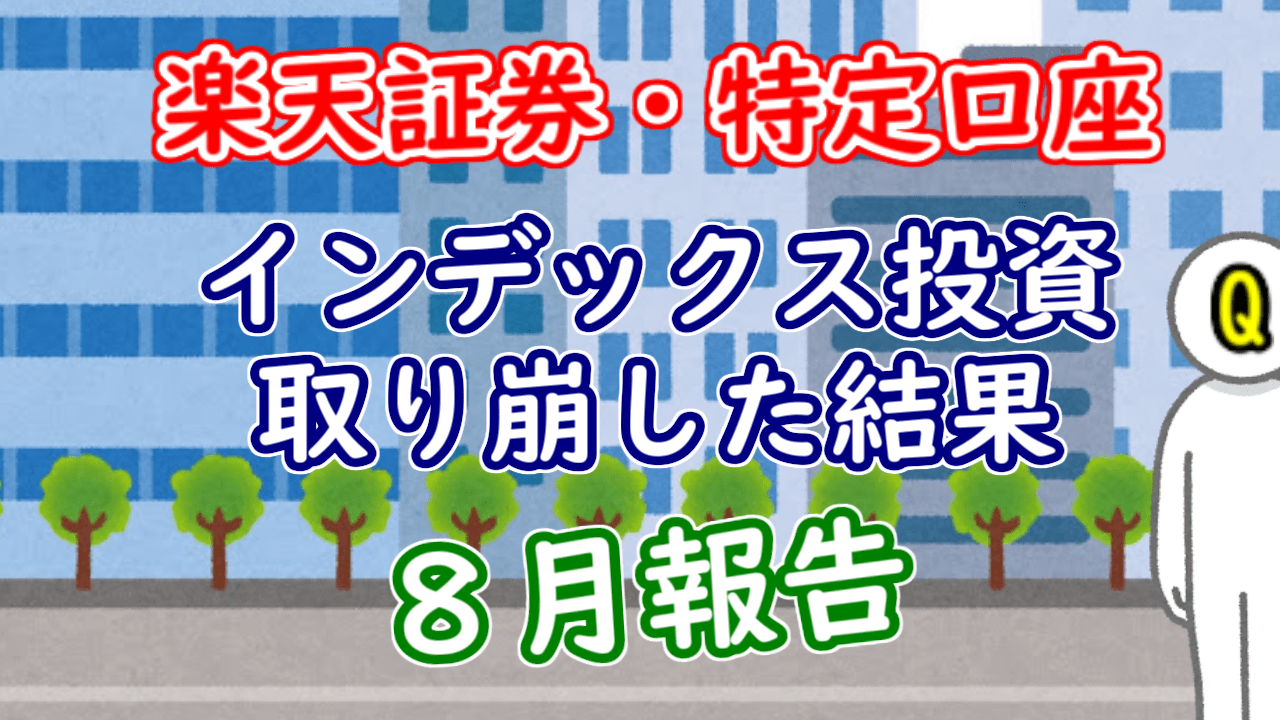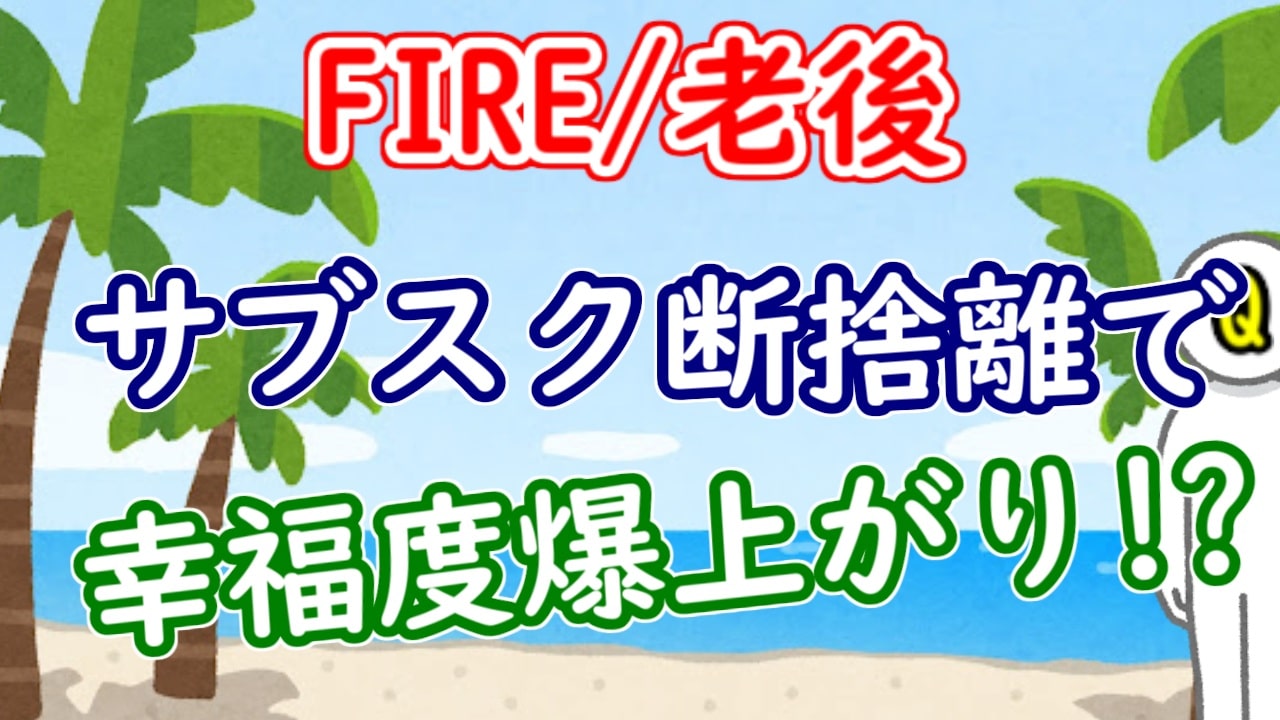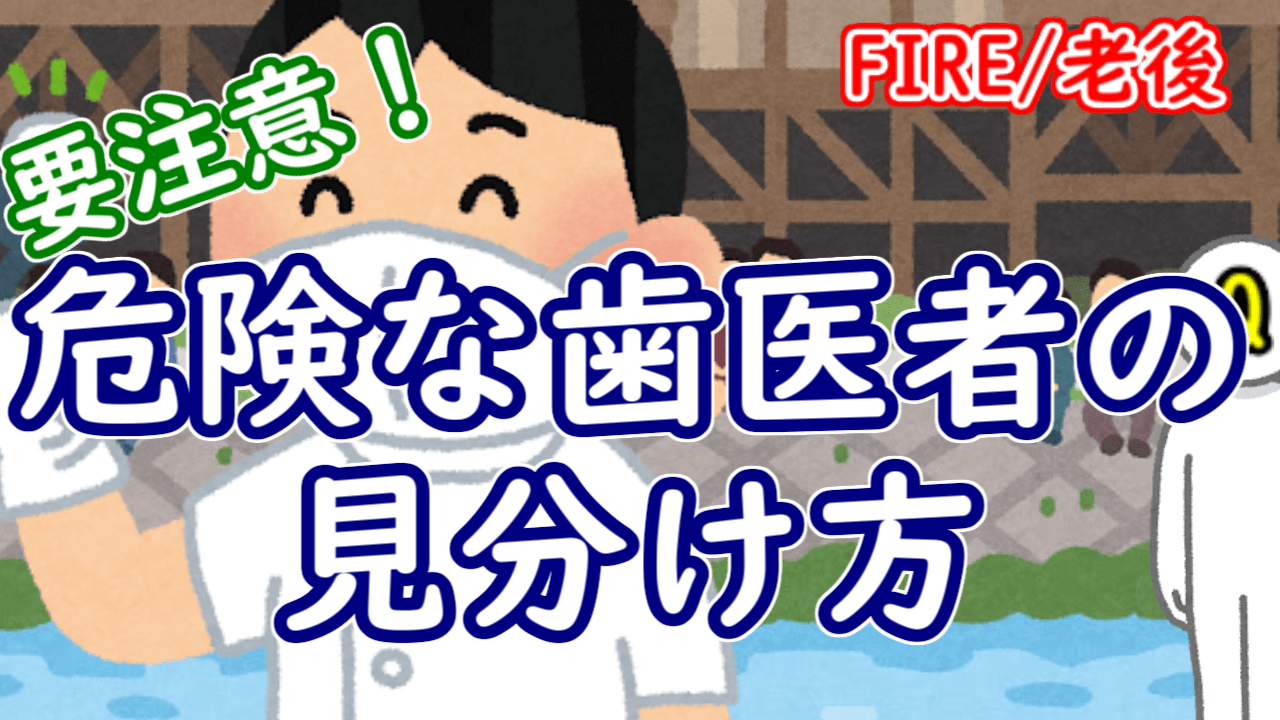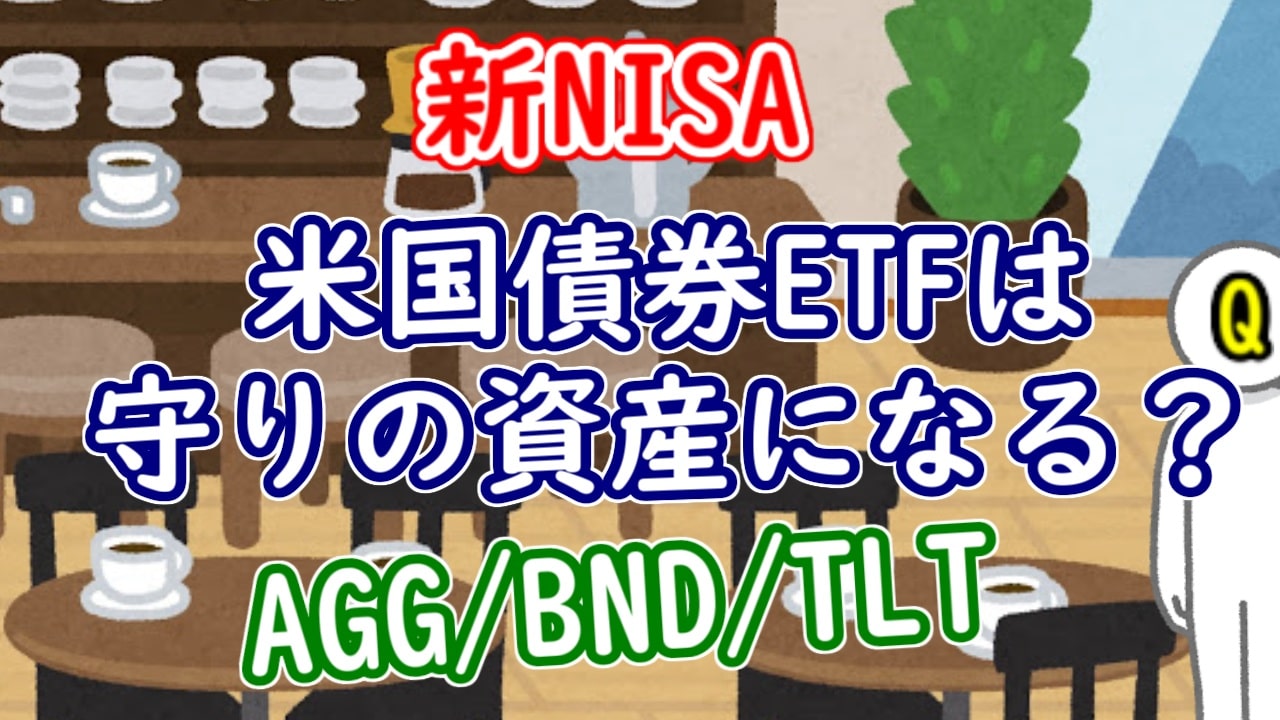
新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は、米国債券ETFや守りの資産の考え方についてです。
本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから。
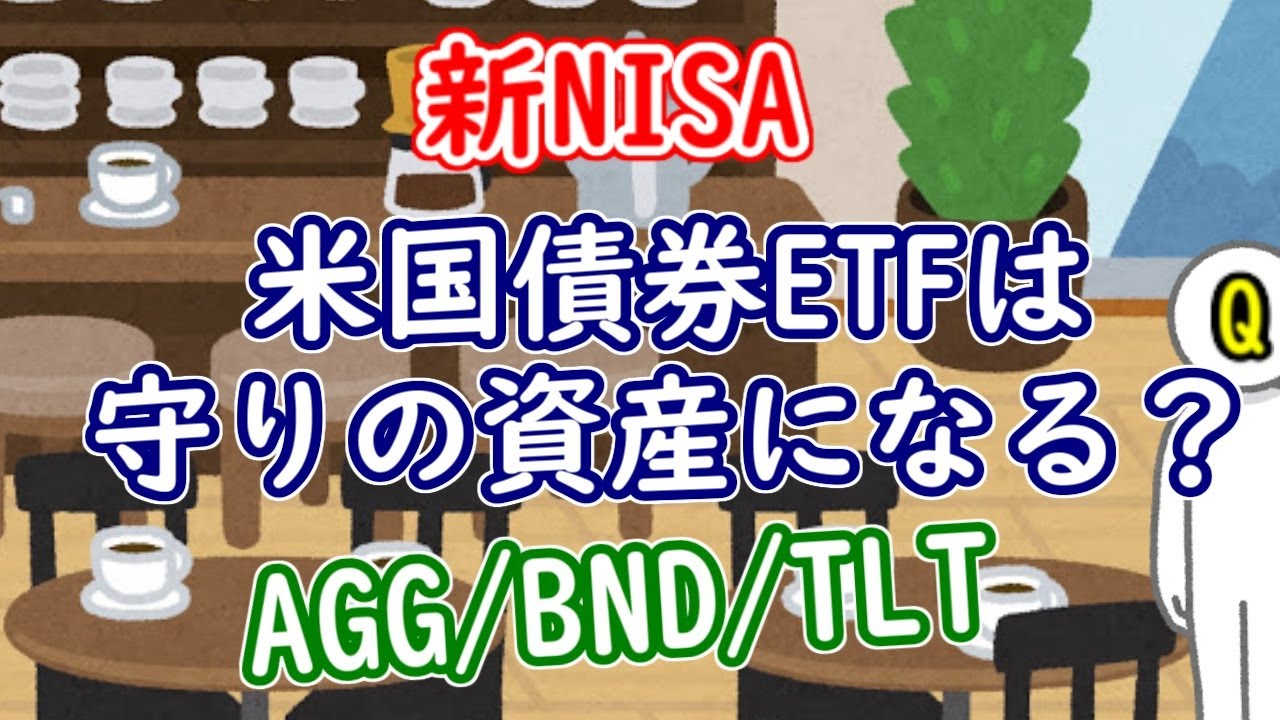
米国債券ETFは守りの資産になる?
こんなご質問をいただきました。
「Q太郎様 いつも拝見させてもらっています。
質問なのですが、守りの資産のために現在AGGとBNDを保有しております。 あと、350万円ほど、債券に投資をしようと考えていました。
AGGやTLTは債券という守りの資産になるでしょうか?
それとも、emaxisslim先進国債券という、投資信託を購入した方がいいのでしょうか?
もしくは、金、現金多めもどうでしょうか?
アセットアロケーションの為なのですが、リバランスのし易さも考えると何が良いのかわかりません?
お忙しいところ恐縮ですが返答頂けると助かります。」
とのことです。
海外債券については以前も動画で取り上げましたが、復習も兼ねて今回また取り上げます。
まず「守りの資産」というのはなにかという根本的な定義ですが、分散投資と守りの資産はまったく別物なので、これは分けて考えてください。分散はあくまで分散で、それが守りか攻めかは全く関係はありません。
また分散投資は、人によってどうしたいかで変わってきますので、これは本当に人それぞれとしかいいようがありません。「攻めのFANG+、守りのNASDAQ100」とか言ってるような人もいるぐらいなので、リスク許容度や投資に対する考え方は本当に人それぞれです。
うちの母も、今年の分の新NISAを年初一括ですべてゴールド投資信託で埋めてますし、本当に人それぞれです。これがいいというモデルケースはないものと思ったほうがいいです。
自分でいろいろ試してみて、自分にとって落ち着く部分を探していくしかないでしょう。
世の中にはオルカンを信じている人もいますし、S&P500を信じている人もいますし、そもそも投資なんて危険だから現預金でいいやっていう人もいます。
それで今回の話ですが、分散投資の一部に守りの資産を入れたいという話とは思います。
それで「守りの資産」とは何かですが、これも何度か言っていることですが、基本的には自国通貨で元本が保証されている、もしくはそれに近いような状態の資産ということになります。ようするに「リスクが極めて低い資産」ということになりますね。これは定義をしっかりしておいたほうがいいとは思います。
リスクが極めて低いということは、ボラティリティが低いということでもあります。ボラティリティが高くなればなるほど、リスクも高くなります。
それで債券は株式に比べればボラティリティが低いということになりますが、ただひとことで債券といってもいろいろな種類があります。
たとえば長期債と短期債ではまったく性質も動きも違って、債券は長期になればなるほどボラティリティは上がっていき、リスクは大きくなっていきます。
たとえば債券ETFのTLTは長期債ですが、株式並みのボラティリティを持っており、変動がけっこう激しいです。変動の激しい物は価格が安定しないということなので、守りにはならないわけです。
AGG/BNDですが、これはいろいろな債券を組み合わせたETFですが、平均デュレーションはおおよそ6〜7年程度なので、言ってみれば中期債といったところです。株式に比べれば変動は小さいですが、それでもある程度のボラティリティは持っています。
さらに外国債券には為替リスクもあります。近年の為替はボラティリティがきわめて高く、分散投資として使うのはいいとしても、守りに使うにはかなり厳しい物があります。
そんなわけで、為替なども含めると日本円換算したときの価格変動はけっこう大きいため、守りの資産とは言えなくなってしまうわけです。
emaxisslim先進国債券も、現在取り崩し実験用に購入してはいますが、動き的にはほぼ為替依存で、為替のボラティリティが大きくなると変動も大きくなるので、これも守りには厳しいものがあります。
それで現在の日本で守りと言えるのは、元本保証されている銀行預金と日本国債ぐらいになります。日本は金利が低いので利益は出しにくいですが、守りというのはあくまで守りなので、お金を稼ぐためのものではないのですね。
それでこれらを組み込むときにはアセットアロケーションで考えるよりは、バケツ戦略で考えたほうがいいとは思います。
バケツ戦略については過去の動画で何度も述べているので割愛しますが、短期バケツと中期バケツを安全資産で充実させておけば、リスク資産を入れる長期バケツのアセットアロケーションは案外好きに組んでしまってもそれほど大きな問題にはなりにくいのですね。
たとえばFIREした人のモデルケースだと、短期バケツには1年分の生活費、中期バケツには5年分の生活費、残り全部長期バケツでリスク資産を運用するという形になります。毎年のはじめに長期バケツから1年分の生活費を補充すれば、少なくともその年から6年間は生きられるということになりますね。
株式がズドンして長期バケツの資産が大きく減ったときには、中期バケツから生活費を持ってきて、その期間を耐えていくことになります。これまでのデータだとだいたいズドンして5年もあれば回復しますので、回復後にまた中期バケツを少しずつ復活させていけばいいでしょう。
そのため、守りを考えるのであれば、アセットアロケーション内で考えるのではなく、バケツ戦略全体で考えた方が良いとは思います。
もし働いているのであれば、短期バケツは生活防衛資金として生活費の半年分、中期バケツは家や車のローンの頭金や子供も学費など直近数年で使うまとまったお金、残りは長期バケツでリスク資産を運用すればいい形になります。
そもそも安全資産というのは、あなたの生活を守るための資産なので、投資とごっちゃにしてしまうと、何のための安全資産なのか目的がわからなくなります。
そんな感じで短期バケツ、中期バケツを確保して生活を守ったうえでなら、長期バケツは自分の好きなような投資をすればいいとは思います。長期バケツの中でごちゃごちゃ組み替えたとことで、生活を守ることは難しいですしね。
たんに長期バケツの分散を増やしたいというのであれば、債券を組み込んだり、ゴールドを入れたりもいいですが、それらはあくまでアセットアロケーションのボラティリティを調整するための分散投資の一環でしかないわけです。
例えばアセットアロケーションのボラティリティを半分に落としたいのであれば、アセットアロケーションの半分を現金にすればいいだけです。あくまでアセットアロケーションの分散投資というのは、全体のボラティリティの調整でしかありません。高ボラにしたいか低ボラにしたいかは自分の好みになります。これは本当に人ぞれぞれ好みとか考え方があります。
守りの資産という話になれば、それは生活を守るための資産なので、そこは長期バケツでやることではないので、分けて考えた方が良いでしょう。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・アセットアロケーションは人それぞれ考え方がある。これという答えがあるわけではなく、自分にとって最適なものを自分で見つけていかないといけない。(高ボラ大好きな人もいますし、低ボラ大好きな人もいますからね)
・「守りの資産」と「分散投資」は別物。わけて考える。
・「守りの資産」は自国通貨で元本が保証、もしくはそれに近いような状態のきわめてリスクの低い資産。
・債券は長期になればなるほどボラティリティが上がり、リスクも上がっていく。(TLTがそうですね)
・外国債券は為替リスクも受ける。近年は為替のボラティリティが大きいので、守りの資産にはならない。あくまで分散投資の一環。
・現状、日本で安全資産と言えそうなのは、銀行預金と個人向け国債ぐらい。
・「守りの資産」を考えるのであれば、バケツ戦略を使って短期バケツと中期バケツを確保し、残りを長期バケツで自由に運用する。
・そもそも守りの資産(安全資産)というのは、生活を守るための資産なので、投資とごっちゃにしてしまうと、何のための守りの資産なのか目的がわからなくなる。
・たんに長期バケツの分散を増やしたいというのであれば、債券を組み込んだり、ゴールドを入れたりと自由にやればいいが、それらはあくまでアセットアロケーションのボラティリティを調整するための分散投資の一環。守りの資産とはわけて考える。(ボラティリティを半分にしたければ、アセットアロケーションの半分を現金にすればいいだけですしね)。
となります。
そんな感じで、守りの資産というのはあくまで生活を守るためのものなので、そこは長期バケツのアセットアロケーションとはわけて考えたほうがいいでしょう。
守りの資産を持ちたいのであれば、短期バケツと中期バケツを充実させれば、それはあなたの生活を守ってくれます。アセットアロケーション内はあくまで分散投資でボラティリティをどういじくるかの話になってきますし、これは本当に人それぞれ考え方とか好みが違います。
Q太郎は低ボラがいいので取り崩し投資をしているわけです。FANG+とかレバナスとか買いまくってガチホしている人もいますし、暗号資産買いまくる人もいますし、アセットアロケーションは本当に人それぞれですね。
そんな感じで、守りを考えたいのであれば、まずは短期バケツ・中期バケツの充実からで、残ったお金は自分の好きなように長期バケツでアセットアロケーションをいじればいいとは思います。