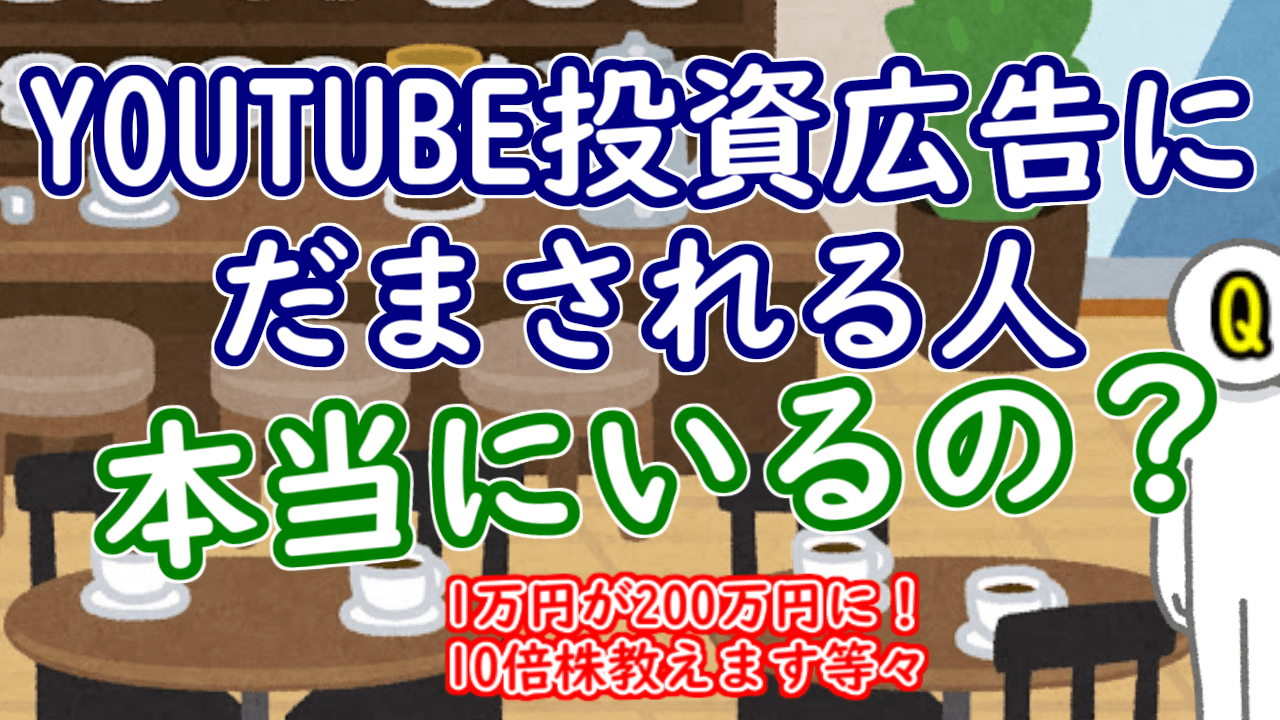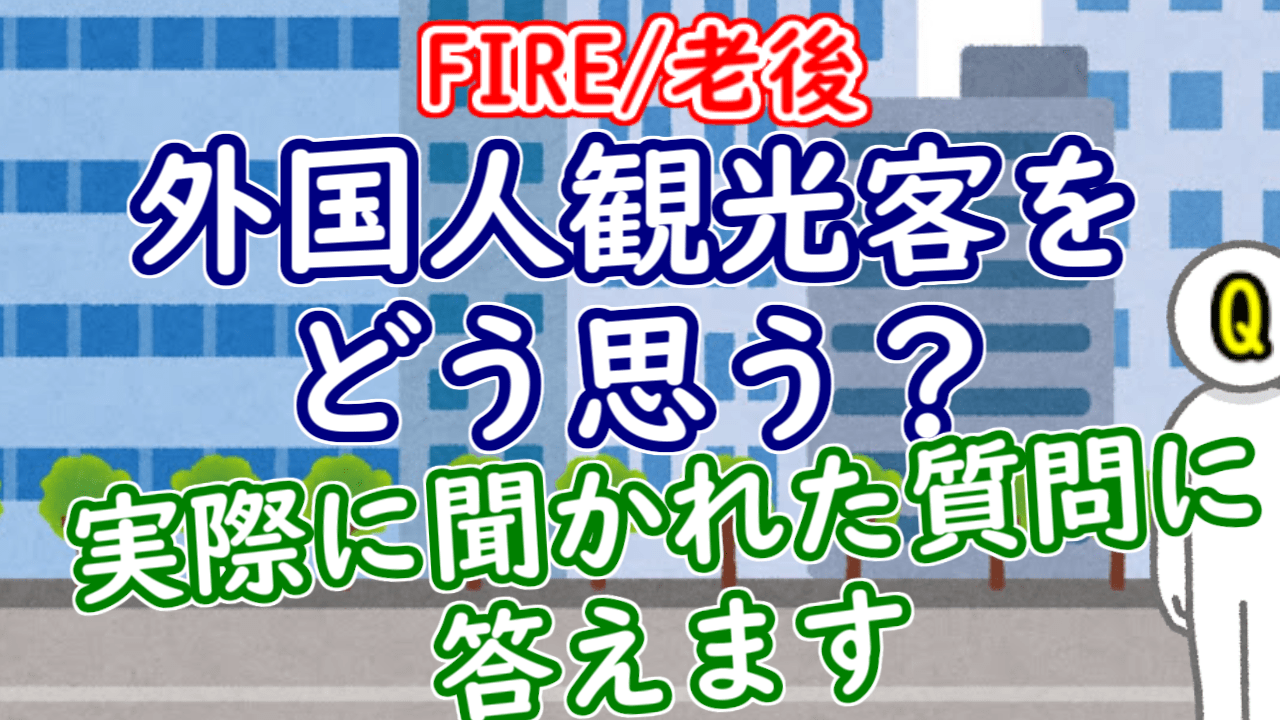新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は、節約至上主義やケチな人のほうが逆に損してしまうということについてです。
本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから。
ケチな人が逆に損する?
こんなご質問をいただきました。
「いつも動画をありがとうございます。
現在の日本はやはり困窮化してしまっており、節約志向がかなり強くなってきています。テレビ番組もおっしゃる通り、どこどこの店が安いみたいな安売り情報ばかりになってきています。
ただ節約にも限度みたいなものがあって、あまりやり過ぎてケチになっていくのもどうかと思います。
「節約=賢い」みたいな風潮がありますが、節約をするということは本来得られた経験を得ることができなかったり、自己投資をしないことで良い仕事に就けなかったり、人付き合いが広がっていかないということにもなるため、逆に損をする場合もあるので、どうバランスを取っていくかも重要になります。
また生活においても、便利なものを使わないことで生活の質が落ちてしまったり、時間を無駄にしてしまったりということもあります。
この辺りの「どこまで節約をするか」の線引きをどうお考えでしょうか。どうぞよろしくお願い致します」
とのことです。
まあ、お金を際限なく使うのはどうかと思いますが、節約をやりすぎてケチのレベルまで行くと、ひたすら自分の世界が小さくなってしまうという問題点はありますね。ミニマリストがひっかかりやすい問題点です。
ただ一方で、この節約しすぎはよくないという考え方も結構危険で、自分の無駄遣いを正当化させてしまう恐れもあります。
クレカ破産する人たちもこの考え方が多いように見受けられます。ようするに生きているうちにいろいろ楽しまないといけないと、「経験への投資」とか「自己投資」とかあれこれ理由をつけて、どんどんお金をつかってしまうという現象ですね。
とくにネット社会だと買い物が楽になりすぎてしまっているので、意識して気をつけないとお金はどんどん減っていきます。最近はネット上でのペイペイ支払いもできるようになったので、クレカがない人でもペイペイを現金でチャージしてネットで使ったりもできるようになってしまっていますしね。
Amazonポイントとかもコンビニで買えてしまいますし、とにかく昔と比べて買い物が楽になってしまっています。わざわざ店に出かけるという労力がないぶん、歯止めがききづらくなっているのですね。
質問者様がおっしゃるとおり、ケチすぎるのもいかがなものですが、現代の消費社会だと節約を意識しないとどんどんお金が吸い取られていくので、どのあたりで線引きするかも重要になってくるとは思います。
現代社会は、とにかく消費させようという社会なので、いたるところでAIDMAやAISASのマーケティング手法を使ってあれこれ買わせようとします。AIDMAやAISASについては以前の動画を参照してください。
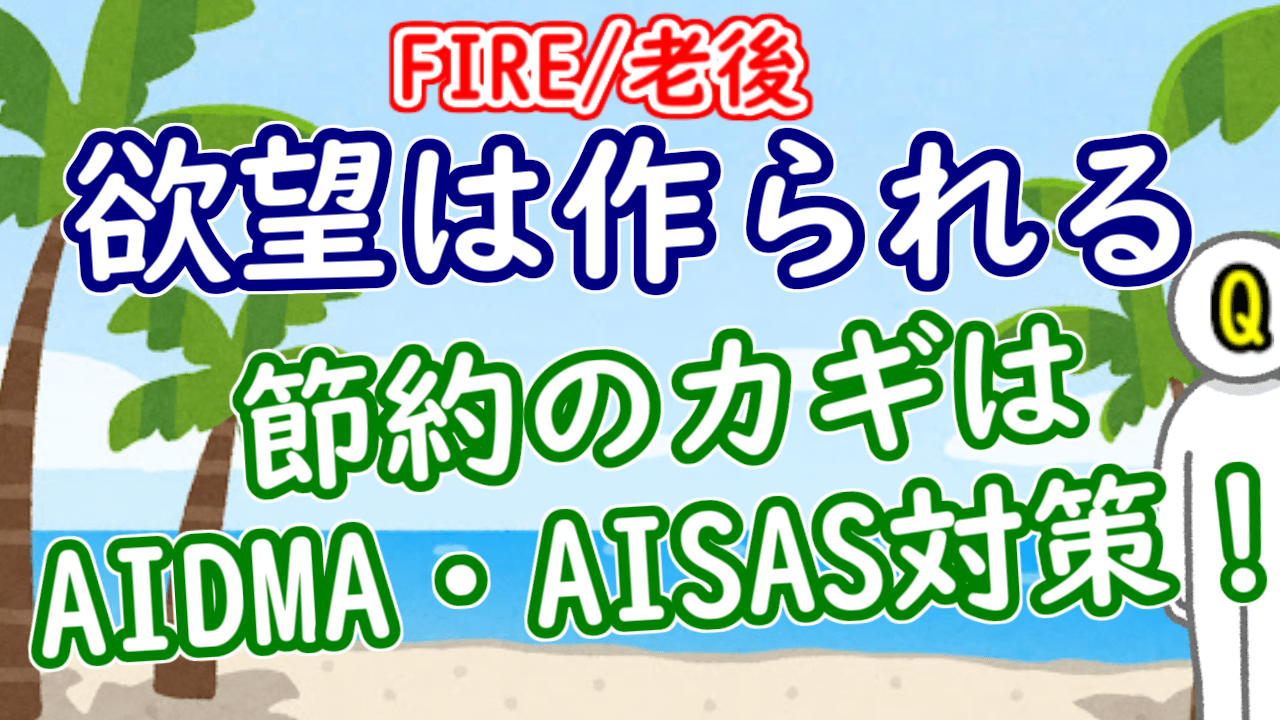
それでまず質問者様の、節約によって本来得られた経験が得られなくなるという問題ですが、これも以前いいましたが、一度目は経験だとしても、2度目以降は消費行動になってしまいます。
たとえばおいしいお菓子があって、食べたことがなければ1度目は買って食べてもいいのですが、経験自体はそれで得られたわけなので、おいしかったからリピートするとかはただの消費行動なわけですね。
人づきあいの面でも、飲み会に1回目は参加するのはいいとしても、それ以降は本当に必要かどうかはよく考えた方が良いかなとは思います。
それと食べ物というのは、お米やパスタ、野菜、肉など自分で加工しなければならないベースとなる食べ物は食べないと飢え死にしますし、水も必要なのでリピートする必要はありますが、加工された食品とかビールとかジュースとかは基本的に嗜好品なので、これは食べても食べなくてもいいものなので、リピートする必要はないわけです。外食とかも嗜好品になりますね。
お金が足りなくなる人の特徴として、ベースになる食べ物にはお金をつかわずに、嗜好品にお金を使ってしまうというのがあります。優先順位がおかしいわけです。
以前なんかのニュースで、貧しい家庭に米を10キロあげたら、それをメルカリで売って、そのお金でコンサートチケットを買ったみたいな話があって、けっきょくこれは生活のベースになるものと、嗜好品との優先順位を考えられていないのが問題なのですね。
当然生きるためには生活のベースになるものが最優先で、まずはベースになるものにお金をつかって、それであまったお金があれば嗜好品に手をつけるということをすれば、そうそうお金が足りなくなることはないのですが、お金がつねに足りない人というのはそんなことよりも自分の快楽を優先してしまうため、まず嗜好品にお金をつかってしまうのですね。優先順位が嗜好品が上で、ベースである生活必需品が下になるわけです。
ベースになるものを買うためのお金が十分なら嗜好品に手をつけていいのですが、そうでなければ嗜好品については節約していく必要があるとは思います。
さらにまずいのが、ベースになるものの節約をおこなう一方で、嗜好品についてはまったく節約しないという状況ですね。
とくに電気代を節約する人にこの傾向が強いとは思うのですが、電気代なんて本当に安いもので、電気のオンオフをこまめにやるぐらいではせいぜい数十円とかそんなレベルでしか節約にならないことはざらにあります。そんなことよりも嗜好品であるお菓子とかビールとかジュースとかを一回我慢するとかのほうがはるかに節約になるわけです。力を入れる方向がおかしいわけです。
あとお米とか最近高くなっていますが、せいぜい以前よりも1000円とか2000円とか高いぐらいでして、こんなものは嗜好品である外食1~2回分我慢すればいいだけの話です。しゅっちゅう外食に行ったり、ビールとか飲み物とか買っているくせに「お米高い」とかいう人は、正直どうなんだろうとは思います。いやまず外食のほうを節約しろと。弁当作れと。ベース品と嗜好品との順番が逆ななわけです。
そんな感じで、節約かどうかの線引きですが、まずはベースにお金をつかうことを優先させて、それであまったお金で嗜好品に手をつけるということにすればお金はそうそう減らないのですが、ここを間違えて、米とか電気代とかベースのものは節約するのに、嗜好品を節約しないという謎行動を起こしてしまうとお金はなかなかたまらないわけです。
あきらかに嗜好品を節約した方が金額ベースで考えれば節約効果が大きいわけです。ベースか嗜好品かをしっかり分けて、優先順位を考えられれば無駄遣いはかなり減ると思います。
とにかく現代社会は嗜好品にお金を使い過ぎだと思いますし、それを自己投資とか経験とかいう言葉でごまかすのもどうかとは思います。新製品なんてどんどん出てきますし、そんなものを全部経験していたらきりがありませんしね。
けっきょくのところ節約の線引きとは、このベースと嗜好品をちゃんとわけて考えて、優先順位をつけられているかどうかですね。まずベースを満たしてから、余裕があれば嗜好品に手をつければいいとは思います。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・節約をやりすぎてケチのレベルまで行くと、ひたすら自分の世界が小さくなってしまうという問題点はある(ミニマリストがひっかかりやすい点ですね)。
・ただ一方で、「節約しすぎはよくない」という考え方も危険。「自己投資」「経験」などを理由に自分の無駄遣いを正当化させてしまう恐れがある。
・1度目は経験、2度目以降は消費行動。(お菓子とかも味のわかっている2度目以降はなんの経験もありませんので消費行動になります。人付き合いの飲み会も、2度目以降は注意が必要ですね)。
・ベースとなる生活必需品と、嗜好品は分けて考える。ベースを優先させる。(生活必需品は生きるためにはリピートしなければなりませんので、こちらを優先させるのは当然のことです)
・お金の貯まらない人はベースを節約して、嗜好品を節約しない。優先順位が逆転している(電気代や米の代金を節約するわりには、外食とかお菓子とか飲み物とか娯楽とかは全然節約しないわけです。金額ベースで考えれば、嗜好品を節約するのが一番効率がいい)。
・新製品はどんどん出てくる。そんなものを全部経験していたらきりがない。
・結局のところ節約の線引きとは、このベースと嗜好品をちゃんとわけて考えて、優先順位をつけられているかどうか。
となります。
そんなわけで、嗜好品にはお金使うけど、ベースはケチるみたいな消費活動をしているとお金はガンガンなくなっていきます。お米が1,000円高くなっているだけで文句を言う割には、なんの躊躇もなく外食しているとかビール飲んでいるとかタバコ吸っているとかですね。優先順位が逆だろうという話です。
そんな感じで、物事の優先順位を間違えず、余ったお金を嗜好品とか自由につかえばいいんじゃないかとは思います。そのあたりが節約の線引きとは思います。