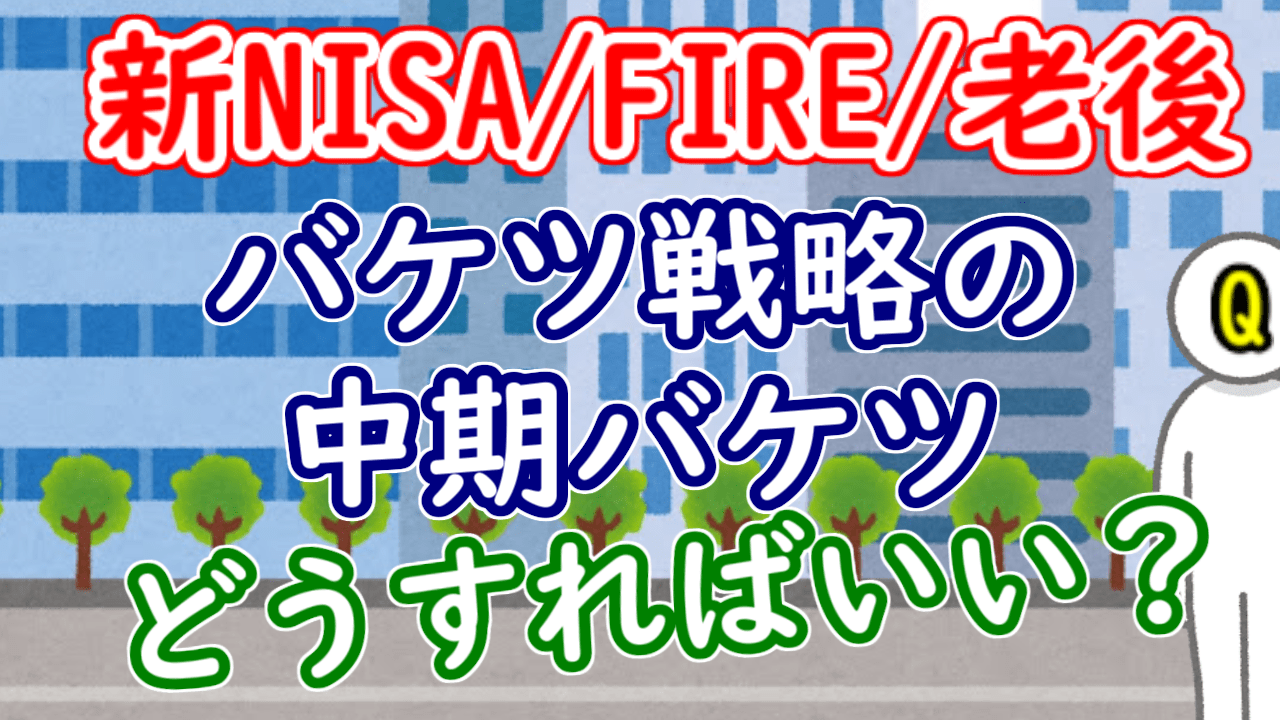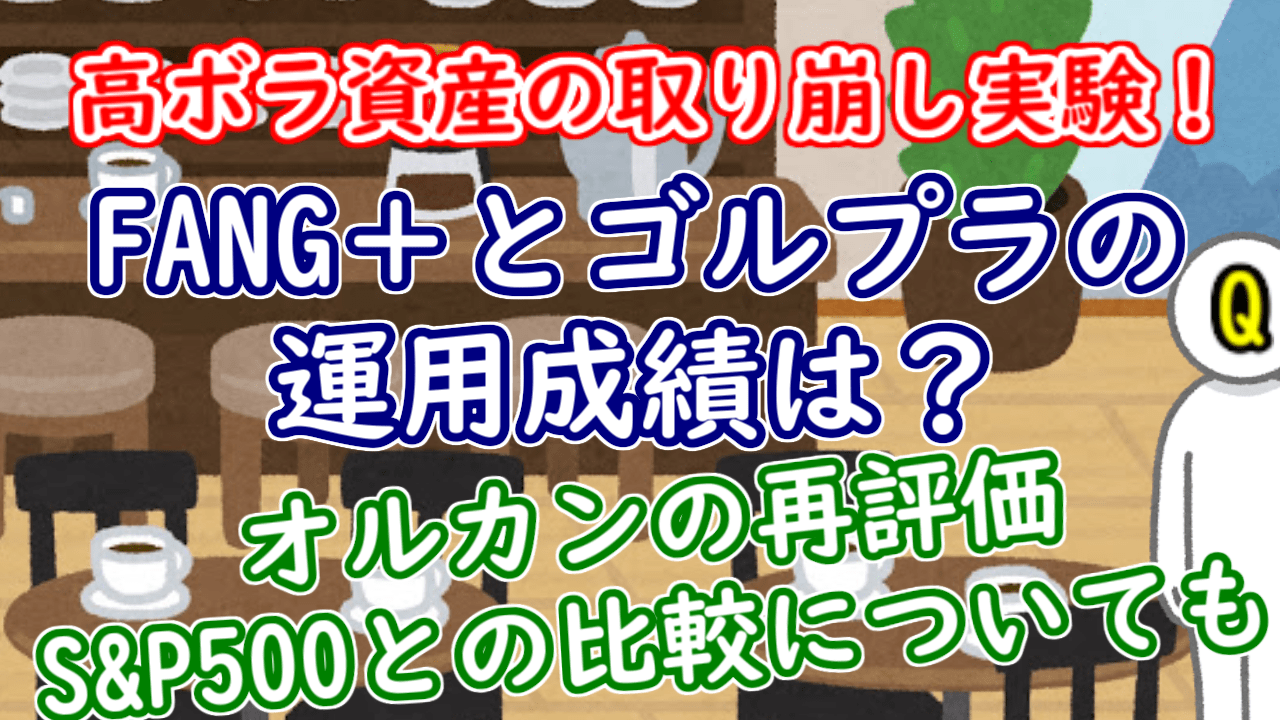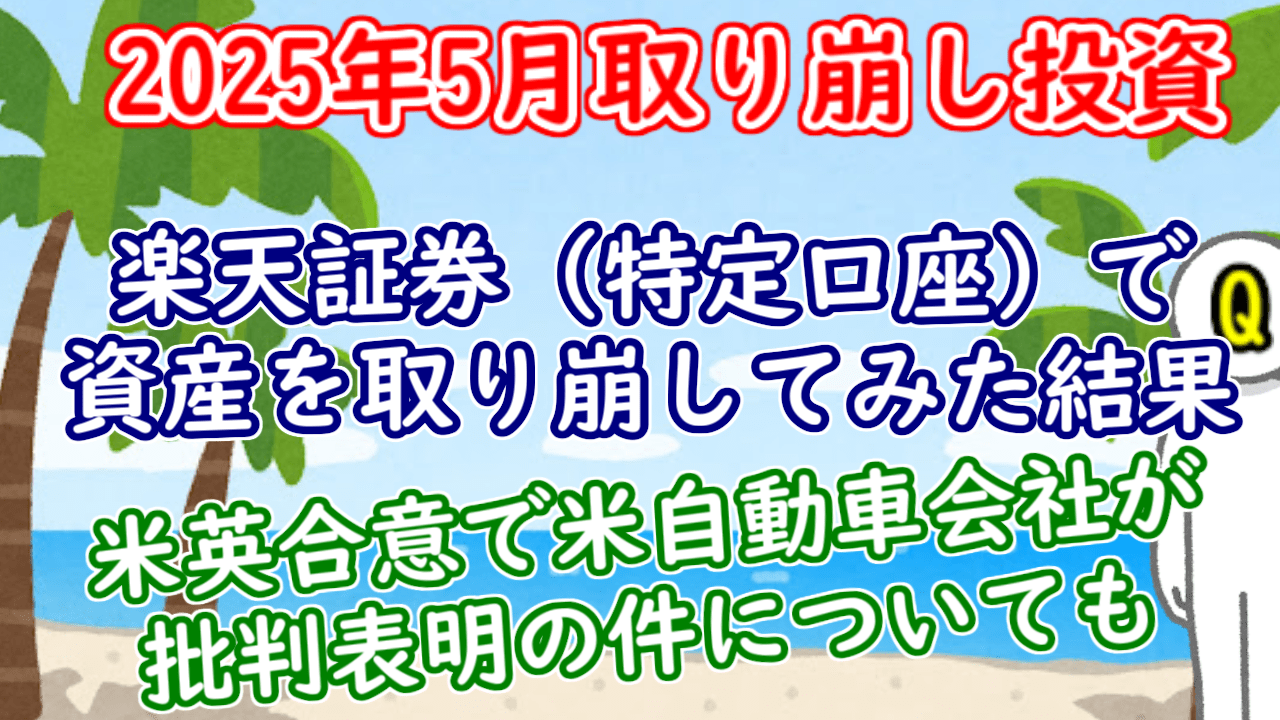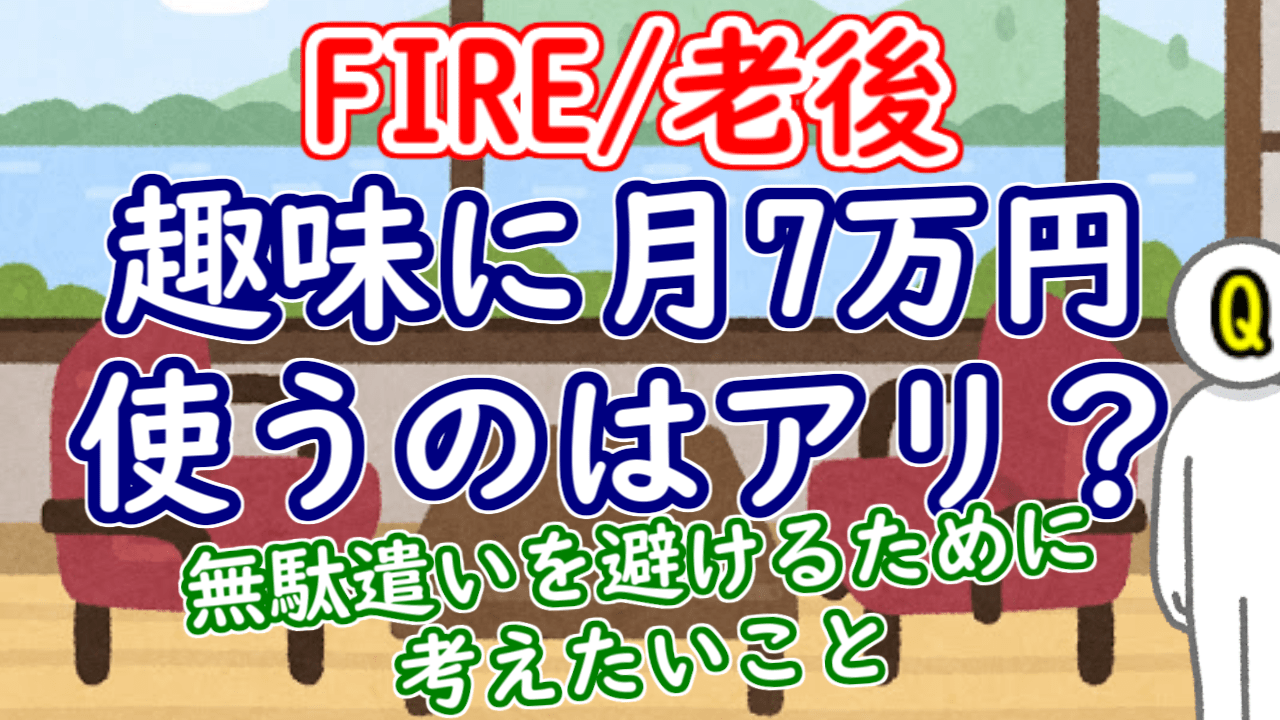
新NISA一括投資→即毎月定率取り崩し運用中のQ太郎です。
今回は趣味に月7万円使うのはありかどうかとの質問についてです。
本記事をYouTube動画で観たい方はこちらのリンクから。
趣味に月7万円使うのはアリ?
こんなご質問をいただきました。
「「欲しい物は我慢しないで買え」とのことですが、それを実践した結果、ゲームなど趣味に使うお金が月7万円を超えました。
確かに今は楽しいのですが、一方で将来お金が足りなくならないか心配です。
今のところお金に困ってはいないのですが、貯金すべきか欲しい物を買うべきかの境界線はどこにあるのでしょうか?」
とのことです。
なんか以前も似たような質問があったと思いますが、お金が多い少ないはあくまで相対的なものです。そのため月7万円が多いかどうかは質問者様の収入や家族構成、一か月の生活費によります。
月100万円稼いでいるなら、7万円ぐらいは収入の7%ぐらいなので大した金額ではありませんし、逆に月14万円でしたら、7万円は収入の2分の1なので、いろいろと厳しいんじゃないかとは思います。
それで一般的に7万円がどれぐらいの金額なのかということですが、総務省統計局の家計調査結果だと、ここ数年で平均生活費がかなり上がっていて、単身世帯の1カ月の平均生活費は18万9,250円となっています。約19万円ですね。
5年前の2019年の時点だと15万8,911円と約16万円だったので、5年間で3万円という、割合で言えばたった五年で約19%アップと、相当な急ペースで上がっているのがわかるかと思います。円安などによってインフレがかなり進んでいますね。このペースだと銀行預金だけで長期のインフレに対抗するのはかなり厳しいものがあるとは思います。
18万9,250円の内訳を見てみると、
住居費(家賃):約5万3,690円
食費:約3万9,202円
光熱費:約1万1,814円
交通・通信費:約2万4,618円
教養娯楽費:約1万8,943円
その他(家具・医療・被服など):約4万1,983円
となっています。
平均的な教育娯楽費がだいたい2万円弱ぐらいなので、7万円という金額は、平均から見れば3倍強といったところで、多いといえば多いですね。
そんなわけで、質問者様の収入がどうかはわかりませんが、一般的には多いとは思います。ただ多い少ないは個人的な問題なので、7万円が多いかは一概にいう事はできません。
それよりも問題なのは、7万円というお金がちゃんと自分の好きな物にピンポイントに使われているかどうかですね。なんとなく浪費しているものが無いかのチェックが必要です。
よく「ゲームが好きです」とか「読書が好きです」とか「映画が好きです」という人がいますが、この回答は全然具体性がなくて、たとえば読書でも歴史小説とかビジネス書とか哲学書とかいろいろジャンルがあるわけです。あたりまえのことですが、読書が好きな人でも全部のジャンルを読んでいるわけではありません。
さらに突き詰めれば、自分としては大して好きでもないジャンルなのに、流行っているからみたいな理由で購入して、けっきょく読まないみたいなのも多いとは思います。
よくあるのが直木賞とか芥川賞とかで本が売れるのですが、最後まで読破している人は3割にも満たないともいわれています。そもそも日本だと1か月に1冊も本を読まない人の割合は47.3%とほぼ半数なので、たまに本買っても、そりゃ最後まで読まないよねみたいな話です。
そんなわけで、世の中で流行っているとかではなくて、ちゃんと自分はどんなジャンルが好きなのか、どんなものだったら最後まで読めるのかを突き詰めて、そこに資金を投資していけば無駄にならないわけです。
これを突き詰めをちゃんとしていないと、無駄なものをたくさん買わされてしまいます。
多くの人は自分の好みぐらいわかっていると思い込んでいますが、本の読破率が3割だったり、多くのRPGのクリア率が3割以下だったりとかで、実際は合わないものを買っている人が多いのですね。Q太郎は本読むのが好きですが、読むのが苦手だったらそこに資金を投じるより自分の価値観にとってプラスのものに資金を投じたほうがいいでしょう。ただこれが思ったより気づかないものなのです。
たとえばQ太郎はゲームが好きですが、あきらかに合うゲームと合わないゲームがあります。
たとえば世間で流行っている『モンスターハンター』とか、何度挑戦しても全然面白いと思えないわけです。ゲーム中で恐竜の卵みたいなのを運んでいて、「なんでこんなことやってるんだろ。時間の無駄じゃね?」と思ってしまって、どうしてもゲームに入り込めないわけです。とにかく理解しようと、何度も挑戦しましたが、やっぱり駄目なわけです。
これは明らかに自分に合わないゲームなわけですね。
それで「このゲームは面白い、このゲームは面白くない」みたいな分け方ではなくて、抽象化してジャンルでわけてしまうのですね。
つまり『モンハン』が面白いかどうかではなくて、「3Dのアクションゲームが苦手」というふうに、大きなくくりで抽象化できれば、今後は3Dのアクションゲーム自体を買わなければいいわけです。どんなに魅力的な宣伝やパッケージでも、どうせ買っても合わないのはわかっているので時間とお金が無駄になりません。
あとRPGも「ストーリーを読むのが面倒」とか「やらされている感があるゲームは苦手」ということに気づいて、RPGを買うのはやめました。アドベンチャーゲームも「ストーリーを読むのが面倒」に当てはまるので買いませんね。抽象化して、ジャンルごと排除してしまうのです。
シューティングゲームについても、『スターソルジャー』のような縦方向のシューティングゲームと、『グラディウス』のような横方向のシューティングゲームがあるのですが、好きなシューティングゲームを仕分けしていくと、どうも横方向の方が多いので、縦方向はあまり好きじゃないんじゃないかという気付きがあるわけです。
これを突き詰めると、縦方向から敵が降ってくるというのは精神的な圧迫感を感じるので、どうも自分の性格には合わないということになります。そこから広げていくと、『テトリス』や『ぷよぷよ』のような落ち物パズルゲームも合わないということになります。実際、あまり長くプレイしたいとは思わないので、この推測は合っているような気はします。
これで縦シューティングと落ち物パズルゲームも排除できたわけで、今後買わなくていいわけです。
そうやってどんどん突き詰めていけば、自分に合う分野と合わない分野が突き詰められていきますので、無駄な出費はどんどん減っていきます。出費だけでなく、時間も節約できますね。
「欲しい物は迷わず買え」はいいのですが、本当に欲しい物かどうなのかという部分は重要です。
無駄遣いというのは、自分にとって必要のないものを買う事です。
自分にとって必要であれば、他人から見れば無駄遣いに思えたりするものでも買えばいいのですが、問題は世間で流行っているからとか、みんなが買っているからとか、宣伝で面白そうだからとかで、自分の価値観に合わない必要のないものを買ってしまうのは無駄遣いです。これは案外自分でわかっていなくて、周囲に踊らされるケースがけっこうあるので、客観的に突き詰める必要があります。
それらを知るために、ある程度投資して失敗してを繰り返す必要がありますが、そのたびに突き詰めて絞り込んでいかないといけないわけです。ゲームも本もそんなに高い物でもありませんので、一か月7万円も使っている状態が続いているとなると、絞り切れていなくて、面白そうな新作が出たら買うみたいなざっくりした状態で消費しているように感じます。ちゃんと突き詰めれば、時間とともに使うお金はどんどん減っていくはずです。失敗が減りますしね。そのあたりをちゃんと検証したほうがいいでしょう。
日本で一時期たまごっち流行ってましたけど、いま遊んでいる人はほとんどいないわけです。当時は行列までつくってみんな買ってたわけです。タピオカミルクティーとかもそうですね。「べつにそこまでおいしくなくね?」というような、まわりではなく、自分の感覚を大事にしてほしいわけです。大阪万博とかもべつに行きたくないけど、みんな行ってるからとりあえず行ってみるみたいな、そういう「とりあえず」とか「なんとなく」を排除していかないといけないのですね。行きたくないなら行かなきゃいいだけで、自分の価値観に従えばいいだけです。
人生の時間は限られてしますし、お金も限られていますので、いまの7万円も、適当な出費になっていないのか、ちゃんと突き詰めていく作業をしたほうがいいとは思います。
「貯金すべきか欲しい物を買うべきかの境界線」ですが、本当の欲しい物を突き詰めれば、余ったお金を貯金すればいいでしょう。ちゃんと突き詰めれば無駄が減るのでお金は余ります。お金を使うこと自体は悪いことではありませんので、自分にとって正しく使うことが重要です。目的もなく貯金だけしても意味がありませんしね。
まとめ
そんなわけでまとめると、
・7万円が多いかどうかは収入や生活費など個々人で違う。
・ただ日本の平均教養娯楽費が約2万円なので、それに比べれば多い。
・自分はなにが合うのか合わないのか、抽象化して検証。ざっくりとさせない。(「読書が好きです」とか「ゲームが好きです」とかざっくりさせずに、ジャンルなどを突き詰めて、それ以外をそぎ落としていく作業が必要です)。
・流行っているとか、みんなが買っているからとかでで、自分の価値観に合わない必要のないものを買ってしまうのは無駄遣い。
・逆に自分の価値観に合うのであれば、他人が無駄だと思う物でも買えばいい。
・買う物をちゃんと絞り込めば、使うお金はどんどん減っていく(最初のうちはトライ&エラーなのでそれなりの投資は必要ですが、毎回ちゃんと検証すれば、だんだん自分自身の傾向がわかってきて、買い物の失敗も少なくなり、無駄な出費が減っていきます)
・使うお金が減れば、貯金も自然に貯まっていく。
となります。
そんなわけで「好きなものを買うか、貯金するか」の2択ではなくて、まず買っているものが本当に好きなものなのかどうかを検証していくのがいいでしょう。
そんなに面白くないけどプレイしているみたいなものは、その理由を突き詰めて抽象化して、そのジャンルを排除しくという作業さえできれば、お金自体そんなにつかわなくなるとは思います。
多くの人が自分の好みがわかっていると思い込んでいるのですが、実際ほとんどのRPGがクリア率3割だったり、本も読破率3割だったりで、実際は合わないものを買っている場合が多いのですね。
そこさえ抽象化できれば、欲しい物は迷わず買えをしていても貯金もしっかりできるという状態になるとは思います。使うお金がどんどん減っていきますしね。